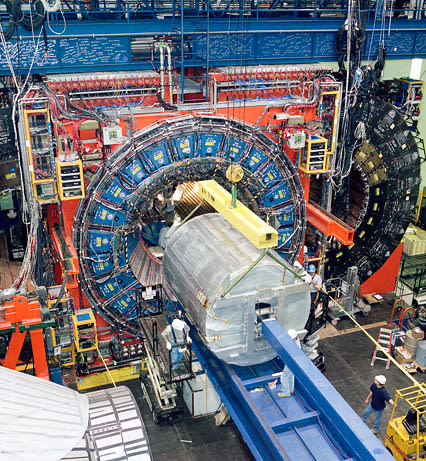アラスカ州南部にある活火山のリダウト山(Mount Redoubt)が22日、火山灰を噴出する噴火を起こした。噴火活動がその後、23日までに合計6回に渡って観測された他、噴火によって生じた降灰は火山から15キロ離れた地域にまで及ぶ状況となっている。
リダウト山が噴火するのは1989年の大噴火以来、ちょうど20年ぶりとなる。
リダウト山はアラスカ州南部のレイク・クラーク国立公園にある標高3108メートルの活火山。リダウト山は1902年、1966年、1989年に噴火を起こしており、1989年の大噴火では火山灰が高度1万4000メートルの上空にまで巻き上げられ、付近を飛行していた旅客機がアンカレッジ飛行場に緊急着陸を起こすという事態も起きていた。
アラスカ火山観測所(Alaska Volcano Observatory)では火山警報レベルを「注意(WATCH)」から最上位の「警戒(WARNING)」に引き上げた上で、周辺地域の住民は火山付近の上空を飛行する航空機に対して警戒を呼びかけている。
ここより怖いのはイエローストーン国立公園。
ここがレベル5以上の噴火を起こして、カルデラ噴火に発展すると…
人類が滅亡しかねないと言われてますし、ドラマもやってましたな。
リダウト山が噴火するのは1989年の大噴火以来、ちょうど20年ぶりとなる。
リダウト山はアラスカ州南部のレイク・クラーク国立公園にある標高3108メートルの活火山。リダウト山は1902年、1966年、1989年に噴火を起こしており、1989年の大噴火では火山灰が高度1万4000メートルの上空にまで巻き上げられ、付近を飛行していた旅客機がアンカレッジ飛行場に緊急着陸を起こすという事態も起きていた。
アラスカ火山観測所(Alaska Volcano Observatory)では火山警報レベルを「注意(WATCH)」から最上位の「警戒(WARNING)」に引き上げた上で、周辺地域の住民は火山付近の上空を飛行する航空機に対して警戒を呼びかけている。
ここより怖いのはイエローストーン国立公園。
ここがレベル5以上の噴火を起こして、カルデラ噴火に発展すると…
人類が滅亡しかねないと言われてますし、ドラマもやってましたな。