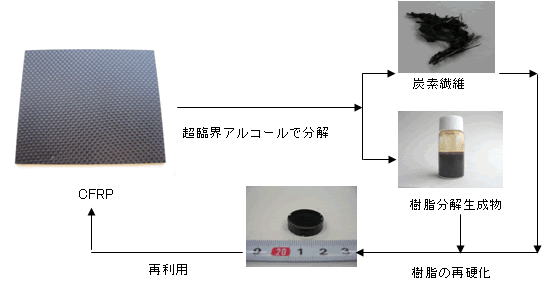清水建設がロシア科学アカデミー陸水学研究所、北見工業大学及び北海道大学と共同で、バイカル湖水深約400メートルの湖底にて、湖底表層に閉じ込められたメタンハイドレートから、ガスを解離・回収する実験に成功したとのことです。これによってメタンハイドレートの新たなガス回収技術に確立に向けて、大いなる第一歩を踏み出したとしています。
メタンハイドレートは、石油などに代わる次世代エネルギーとして注目を集めており、通常の深層メタンハイドレートは地下100メートルから300メートルの場所に豊富に存在しています。日本のメタンハイドレート資源開発のメインターゲットとなっているのは東部南海トラフ海底深部にある膨大なメタンハイドレートですが、今回の技術によって、日本近海の深層だけでなく、オホーツク海や日本海の表層にあるメタンハイドレートも利用することができるようになるため、今回の技術は日本の将来にとっても非常に有効であるというわけです。
今回回収されたのは深層メタンハイドレートではなく、表層メタンハイドレート。深層メタンハイドレートは温度・圧力条件をごくわずかに変化させるだけで相平衡状態を崩すことができるため、加熱や減圧などの方法を使って、ガスを解離・回収することができるのですが、表層メタンハイドレートは海底に近い分だけ、低温で安定状態にあるため、その状態を崩して効率的にガス回収するのに工夫が必要であり、そのための技術が今回、実験されたというわけ。
掘削・攪拌用ウォータジェットを装備したハイドレート解離チャンバー。内部にウォータージェット・ノズル32本(水平ジェット及び垂直ジェット各16本)を装着した鋼鉄製・茶筒状のチャンバーとなっており、下部は開口しています。ウォータージェットで湖底表層のメタンハイドレート層を掘削、攪拌することによってメタンハイドレートは水に溶解、この溶解水を湖上へポンプで揚水すると、水に溶解したメタンハイドレートが揚水過程で海水圧の減少によってガスが水から分離、この分離したガスを湖上で回収し、作業完了。
約100分間攪拌した結果、回収できたガスの90%はメタンやエタンなどの炭化水素ガスで、ガスの組成や性質としては、メタンハイドレート解離ガスとほぼ同一だったそうです。
ちなみに、海底または湖底を含め、表層メタンハイドレートからガスの解離・回収に成功したのは今回の実験が世界で初めてとなっており、今回の成功は日本の資源開発にとって多様な埋蔵資源の確保という観点から、大きな意味を持っているとのことです。
メタンハイドレート。
この資源、将来的にめっちゃ重要です。
魔のトライアングル、これの原因のひとつといわれてますが…
コスト面及び安全性を確保すれば、貴重なエネルギー源ですな。
メタンハイドレートは、石油などに代わる次世代エネルギーとして注目を集めており、通常の深層メタンハイドレートは地下100メートルから300メートルの場所に豊富に存在しています。日本のメタンハイドレート資源開発のメインターゲットとなっているのは東部南海トラフ海底深部にある膨大なメタンハイドレートですが、今回の技術によって、日本近海の深層だけでなく、オホーツク海や日本海の表層にあるメタンハイドレートも利用することができるようになるため、今回の技術は日本の将来にとっても非常に有効であるというわけです。
今回回収されたのは深層メタンハイドレートではなく、表層メタンハイドレート。深層メタンハイドレートは温度・圧力条件をごくわずかに変化させるだけで相平衡状態を崩すことができるため、加熱や減圧などの方法を使って、ガスを解離・回収することができるのですが、表層メタンハイドレートは海底に近い分だけ、低温で安定状態にあるため、その状態を崩して効率的にガス回収するのに工夫が必要であり、そのための技術が今回、実験されたというわけ。
掘削・攪拌用ウォータジェットを装備したハイドレート解離チャンバー。内部にウォータージェット・ノズル32本(水平ジェット及び垂直ジェット各16本)を装着した鋼鉄製・茶筒状のチャンバーとなっており、下部は開口しています。ウォータージェットで湖底表層のメタンハイドレート層を掘削、攪拌することによってメタンハイドレートは水に溶解、この溶解水を湖上へポンプで揚水すると、水に溶解したメタンハイドレートが揚水過程で海水圧の減少によってガスが水から分離、この分離したガスを湖上で回収し、作業完了。
約100分間攪拌した結果、回収できたガスの90%はメタンやエタンなどの炭化水素ガスで、ガスの組成や性質としては、メタンハイドレート解離ガスとほぼ同一だったそうです。
ちなみに、海底または湖底を含め、表層メタンハイドレートからガスの解離・回収に成功したのは今回の実験が世界で初めてとなっており、今回の成功は日本の資源開発にとって多様な埋蔵資源の確保という観点から、大きな意味を持っているとのことです。
メタンハイドレート。
この資源、将来的にめっちゃ重要です。
魔のトライアングル、これの原因のひとつといわれてますが…
コスト面及び安全性を確保すれば、貴重なエネルギー源ですな。