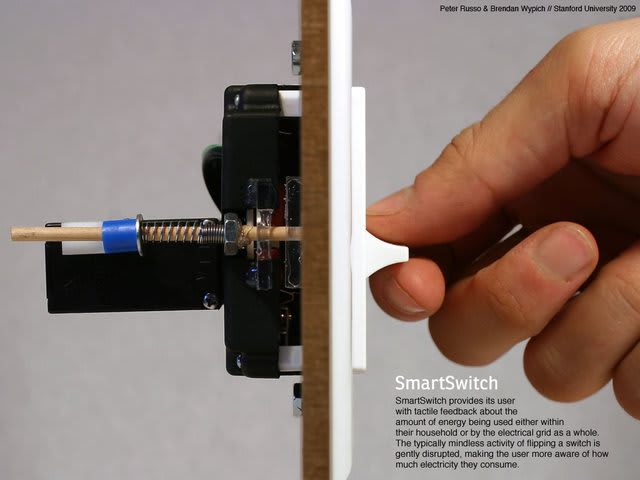ドイツのRUF(ルーフ)社は、ジュネーブモーターショーで『eRUFグリーンスター』を発表した。最大出力367psのモーターを搭載。0-100km/h加速5秒、最高速320km/hとスポーツ性能を大きく引き上げて登場した。
ルーフ社はポルシェのスペシャリストとして知られ、ポルシェベースのコンプリートカーを数多く製作。ドイツでは正式な自動車メーカーとして認められている。ルーフ社は2008年10月、『911カレラ』をベースにしたEV、『eRuf911プロトタイプ』を開発。試作段階ながら、0-100km/h加速7秒以下、最高速度224km/hという性能を実現した。
今回発表したeRUFグリーンスターはその進化形。EVシステムをドイツの大手電子機器メーカー、ジーメンスと共同開発し、運動性能と実用性を大幅に高めているのが特徴だ。
タルガ風に見えるボディは、実は『911カレラカブリオレ』がベースとなっており、シルバーのロールオーバーバーと、軽量樹脂製リアウインドウを採用。セラミックブレーキと19インチアルミホイールも装備された。
「eドライブ」と呼ばれるパワートレーンは、モーター、ジェネレーター、コントロールモジュール、リチウムイオンバッテリーが一体設計されており、小型軽量にまとめられた。その効果もあって、車重は1695kgとeRuf911プロトタイプよりも200kg以上軽くなっている。
モーターは最大出力367ps、最大トルク96.9kgmと非常に強力。2次電池はリチウムイオンバッテリーで、充電は400Vコンセントに接続して約1時間で完了するという。動力性能の進化も目覚ましく、0-100km/h加速5秒、最高速320km/hを達成。プロトタイプと比較すると0-100km/h加速は2秒、最高速度は100km/h近く上回る。ちなみに、ベースとなった911カレラカブリオレが、0-100km/h加速5.1秒、最高速289km/hだから、この性能も超えたことになる。
ルーフは911ベースのEVを2010年に少量生産する計画。本家の911を脅かすほどのスポーツ性能を持った電気自動車は、要注目の存在だ。
ルーフ社はポルシェのスペシャリストとして知られ、ポルシェベースのコンプリートカーを数多く製作。ドイツでは正式な自動車メーカーとして認められている。ルーフ社は2008年10月、『911カレラ』をベースにしたEV、『eRuf911プロトタイプ』を開発。試作段階ながら、0-100km/h加速7秒以下、最高速度224km/hという性能を実現した。
今回発表したeRUFグリーンスターはその進化形。EVシステムをドイツの大手電子機器メーカー、ジーメンスと共同開発し、運動性能と実用性を大幅に高めているのが特徴だ。
タルガ風に見えるボディは、実は『911カレラカブリオレ』がベースとなっており、シルバーのロールオーバーバーと、軽量樹脂製リアウインドウを採用。セラミックブレーキと19インチアルミホイールも装備された。
「eドライブ」と呼ばれるパワートレーンは、モーター、ジェネレーター、コントロールモジュール、リチウムイオンバッテリーが一体設計されており、小型軽量にまとめられた。その効果もあって、車重は1695kgとeRuf911プロトタイプよりも200kg以上軽くなっている。
モーターは最大出力367ps、最大トルク96.9kgmと非常に強力。2次電池はリチウムイオンバッテリーで、充電は400Vコンセントに接続して約1時間で完了するという。動力性能の進化も目覚ましく、0-100km/h加速5秒、最高速320km/hを達成。プロトタイプと比較すると0-100km/h加速は2秒、最高速度は100km/h近く上回る。ちなみに、ベースとなった911カレラカブリオレが、0-100km/h加速5.1秒、最高速289km/hだから、この性能も超えたことになる。
ルーフは911ベースのEVを2010年に少量生産する計画。本家の911を脅かすほどのスポーツ性能を持った電気自動車は、要注目の存在だ。