作品情報⇒https://eiga.com/movie/80277/








以下、アラン・ギロディ特集公式HPからあらすじのコピペです。
=====ここから。
夏、美しくブルーに輝く湖。ここは男性同士が出会うためのクルージングスポットになっている。
ヴァカンス中に訪れた若い青年フランクは魅力的なミシェルと出会い恋に落ちる。ある夕方、フランクは湖で喧嘩する2人を目撃する。
その数日後、ミシェルの恋人だった男性が溺死体で発見された。捜査の手が入った男たちの楽園は一転して不穏な空気が立ち込める。情熱が恐怖を上回る瞬間、自らの欲望に身を任せてゆく——
=====ここまで。
イメージフォーラムでの<特集上映>アラン・ギロディ特集にて鑑賞。今回初めての劇場一般公開。
☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆
この特集の告知を見てから、ちょっと興味があったので、ほぼ予備知識なく見に行ったのでありました。
私、あんましゲイ映画は得意じゃなく、本作は、無修正な上にかなりハードなシーンも多くて、本来なら私の苦手なジャンルのはずなのに、何ということでしょう! ……スゴい映画を見てしまった、、、という感じであります。
◆モザイク無し、フリー○ンのオンパレードで困惑、、、。
舞台は、フランスのとある湖畔で、いわゆるハッテンバという所だろう。ハッテンバという単語は耳にはすれども、実際どういう場所なのかは分からなかった。本作を見て、こういうもんなのか、、、と勉強(?)になった。
もう、いきなり男の全裸がモザイク無しでこれでもかとスクリーン上に溢れかえり、正直、目のやり場に困るシーン多々。演技を超えていると思われるセックスシーンもあり、すんません、半目or薄目で、ところどころは目を閉じておりました(正視に耐えない)。男女のセックスシーンもあんまし見たいものじゃないけど、男同士のハードプレイは、申し訳ないけど見たくない。ここまでこんなシーンが多い作品とは思っていなかった、、、ごーん。
けれども、中盤からサスペンス度がググッと上がり、さらには終盤にかけて、それらのシーンが(量の多寡はともかく)本作ではある程度必要だったのだな、、、と納得させられる展開に。見終わってみれば、実に面白い、満足度の高い作品となったのだった。
ストーリーはシンプル。ハッテンバ湖畔に舞台は固定されていて、単調になりそうなところを、ユーモアあふれるセリフや、欲望を満たそうとする男たちの本能むき出しな行動、理性と欲望のせめぎ合い等々が見事に調和して、過激シーンだけでなく、見る者を退屈させない。
過激シーンが必要だったのだなと感じたのは、終盤でフランクがとった行動にある。あのような状況で、フランクがミシェルとの情事を続けたことに説得力が増すからだ。もし、通り一遍の“匂わせ”シーンで誤魔化していたら、やはり、フランクの行動に、見ている者たちは疑問を抱くし、ストレスが溜まると思う。でも、むき出しの欲望の交わるシーンがあったからこそ、嗚呼、、、と見る者は腑に落ちる。……というか、私はそう感じた、ということだけど。
◆“ゲイ”を切り札にしない。
このブログでも時々書いているけど、ゲイの恋愛モノを見るとき、それが異性愛者であったらメチャメチャ陳腐な話になるような映画(やドラマや小説)ってのは、私は好きではない。ゲイであることの葛藤だけにフォーカスされたゲイの恋愛モノは多いが、ゲイじゃなくても、そもそも恋愛には葛藤は付き物なのであって、ゲイでなければ葛藤がないかのようなストーリーは、安易にゲイをネタにしているだけと感じるからだ。
そういう意味では、本作は、登場人物たちがゲイであることはあまり重要ではない。女性は一人も出て来ないが、それも問題ではない。
パンフの監督のインタビューを読むと、監督は「愛」と言っているが、これはただの愛というよりは、「性愛」だろう。愛とはセックスが枯れてからも残る相手を尊重する深い愛情だと思うので。性愛に支配されているとき、人間は理性が吹っ飛ぶものだし、本作はまさにそれを描いている。
フランクとミシェルのキャラの違いも、男女のラブストーリーによく見られるもの。常に一緒にいてベタベタしたいフランクと、ドライなミシェル。人が溺死した湖で泳ぐことにゼンゼン抵抗がないと言い放つミシェル。恋人が死んで悲しくないの?と聞くフランクに「悲しくはない」とサラッと答えるミシェル。その距離は縮まらないけど、お互い肉体的な欲望はぶつけ合う。
やはり、恋愛を描くということは、そういうことだろうなと、改めて思う。同性同士であろうが異性同士であろうが、恋愛の持つ物語性に違いはない。ゲイであることは、それだけをフォーカスする要素ではない。
本作でキーマンとなっているのは、しかし、ミシェルではなく、アンリという中年男。彼は小太りで見た目もイケオジとは言い難いのだが、何とも言えない愛嬌のあるオッサン。ハッテンバに来ても、服も脱がず、泳ぎもせず、ただただゲイたちの戯れや湖畔の自然を眺めているだけ。でも、フランクとの会話は、劇場でも笑いが起きる様なユニークさがあり、フランク自身、アンリを恋の相手とは認識しないまでも、良い友人候補とは思っているふうである。
男しか出て来ないゲイ映画だけど、相手が同性か異性かが違うだけで、人間の多面性や矛盾を真っ向から描いた恋愛サスペンスとして、素晴らしいシナリオだと感じた次第。
◆その他もろもろ
本作を面白くしたのは、その秀逸なシナリオだけではなく、俳優陣たちの演技にもあるのは言うまでもない。みなさん、かなり大変だったのでは、、、。
主演のピエール・ドゥラドンシャン、誰かに似ている気がするが、、、誰だろう?? なかなかキレイで、ゲイのラブシーンも、彼ならば画になる。「私はモーリーン・カーニー 正義を殺すのは誰?」にも出ていたのか、、、。
ミシェルを演じたクリストフ・パウは、トルコ系(?)なルックスでちょっとワイルド。優男風のフランクが惹かれるのも、何だか分かる気がしてしまう。このミシェルが終盤にかけて見せる豹変ぶりがなかなかに怖ろしい。
日が変わるのを、駐車場のシーンで分かる様に描いているのが面白い。溺死事件が起きて以降は、溺死した男の赤い車が何日か止まったままになっていて、ある日、その車がなくなって、死体が上がったことが分かるようになっている、、、とか。日によって、止まっている車の数が多かったり少なかったり。ある日は、フランクの車以外見当たらなかったり。
また、湖畔ハッテンバの、昼間のあけっぴろげな明るさと、夜間の漆黒の闇の対比が良い。同じ場所なのに、これほどの明暗の落差、陰影の濃さは、サスペンスの演出として抜群だと感じた。
ラスト、あの終わり方は賛否ありそうだが、私はかなり好きである。あの後、フランクはどうなるのだろう、、、と考えてしまう。私は割と最悪な展開を想像してしまうのだが、、、。
「裸になってもイイ?」「裸は禁止されているんじゃ?」「どこでも禁止だよ(とパンツを脱ぐ)」
……ハハハ。










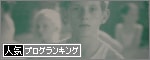
 て感じでした。
て感じでした。



