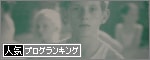作品情報⇒https://moviewalker.jp/mv88040/






以下、公式HPからあらすじのコピペです(青字は筆者加筆)。
=====ここから。
1940 年 8月、ベルリン。18 歳のステラ・ゴルトシュラーク(パウラ・ベーア)は、アメリカに渡りジャズシンガーになることを夢見ていたが、ユダヤ人の両親を持つ彼女にとって、それは儚い夢だった…。
3年後、工場で強制労働を強いられていたが、ユダヤ人向けの偽造パスポートを販売するロルフ(ヤニス・ニーヴナー)と出会い、恋に落ちると、同胞や家族が隠れて生活する中、ロルフの手伝いをしながら街中を歩き、自由を謳歌していた。
しかし、ゲシュタポに逮捕されると、アウシュヴィッツへの移送を免れるため、ベルリンに隠れているユダヤ人逮捕に協力を強いられる。生き残るために同胞を裏切ったステラは、終戦後、裏切ったユダヤ人仲間から裁判をかけられる…。
=====ここまで。
☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆
2月アタマの旅行前にインフルとかに罹りたくなかったので、映画館行きは自重しておりました。だって、ものすごいインフル流行ってたんですよ、東京。なので、本作は1か月半ぶりの劇場鑑賞となりました。まあ、またナチものです。食傷気味だのなんだの言いつつ、見に行ってしまうのでありました、、、ごーん。
◆サバイバルなんかしたくない。
宣伝の惹句には「“被害者”から“加害者”へ」とある。あの時代、ユダヤ人でも積極的にナチに協力していた人たちは大勢いた。
ユダヤ警察のように、大っぴらにナチの手足となって動いているユダヤ人たちもいれば、ステラのように、表向きは同胞として振るまいつつ、密告者としてナチの手先となっていた人々もいたわけだ。今読んでいる本『クラクフ・ゲットーの薬局』(タデウシュ・パンキェヴィチ著、田村和子訳、大月書店)でも、密告者の存在が書かれている。
私は、本作を見ていて、ステラが被害者か加害者かということにはあまりアンテナが働かなかった。全編で、こんな状況でそれでも“生きよう”とするステラに、ただただ驚愕していた。前述の『クラクフ・ゲットーの薬局』にも出てくるが、ゲットーに押し込められていたユダヤ人たちの中には、青酸カリをいつも持ち歩いていた人たちも多かったとある。その類の話はよく聞く。スクリーン内のステラの姿を見ながら、私はそのことが脳内でぐるぐるしていた。
ステラは度々ナチの親衛隊に「アウシュビッツに送らないで!!」と泣き叫びながら懇願する。そして、密告を重ねる。
私だったら、、、ナチに拷問される前、取調べを受けると分かった時点で青酸カリを飲むかな、、、とぼんやり考えていた。アウシュビッツに行くのはもちろん嫌だが、ナチに拷問されたり、怒鳴られたり、殴られたり、パシリさせられたりするのも同じくらい嫌である。密告者になりたくないとかではなく、正直、あんな状況で生きていたくないと強く感じたし、私はサバイバル能力がないという自覚があるのだ。
サバイバルゲームとか映画とかで、一人また一人と死んで行く展開はよくあるけれど、私はああいうの見ていると、一番最初に死んじゃいたいと思うのだ。だって、生き残るほどに苦痛と恐怖が指数関数的に増えるだけじゃん。おまけに、仲間はどんどん減っていくし孤独になる。死んだもん勝ちってヘンな言葉だけど、まあ、そんな感じ。ゲームや映画は、最後に生き残った一人が英雄扱いになるんだけど、現実にそんなことになったら、生き残ったって地獄やろ、、、と考えちゃうのは、悲観的に過ぎるかしらん?
新卒で就職した同期で、それとは正反対の考えの女性がいて「私は地球が滅んでも最後の一人になる自信がある!」と言うのを聞いて、のけぞった。「だから、大事故とか大災害に遭っても、自分だけは助かると信じてる」と言うのだ。私は「えー、すごいね」としか言えなかったが、生命力が強い人の思考というのは、こういうものなのかも知れん、、、と思った。……その後、その女性は早々に会社を辞めて音信不通になったが、今どうしているんだろう。
ステラもある意味、その同期のような思考回路の人なのかな、、、とも感じた。死ぬことへの恐怖が強いというより、生きることへの執着がもの凄い。とにかく、どんな状況でも生きようとするのである。「もういいや、、、」ってのがない。これはスゴい。
『戦場のピアニスト』で生き残ったシュピルマンとは、ステラはまたちょっと違うように感じる。シュピルマンもただただ生きようとするだけなのだが、どこかに諦念があり、“とりあえず生かされているから生きる”という印象である。が、ステラは“とにかく生きるために生きる”なのである。諦念の有無の差は大きいと感じさせられた。
◆チクりはダメですか?
密告、、、非常に卑劣な行為のように見える。が、人間、いざとなったらいくらでも卑劣になれるんじゃないか、とも思う。
ステラを批判するってことは、死ねってことと同義だと思うが、密告などしなくても生き残った人もいるではないか、と反論されるだろう。あの状況で、ステラのように“積極的に”生き残ることを考えた人は、大なり小なりナチに協力したんではないか。国外逃亡という手もあるけど、それだって、同胞を見捨てたことと同じ、、、と言えるのでは。だからと言って、批判などできようはずもない。
独裁社会では、必ず使われる、密告という手法。まんまタイトルになっているクルーゾー監督の『密告』もナチ占領下で作られた映画だが、とにかく社会が暗くなる。そらそうだよね、皆が、家族や友人同士でも疑心暗鬼になってしまうのだから。
ステラが生きるために喜んで密告に精を出していたとは、、、やはり思えない。それは、戦後の彼女の生き様を見ると、そう思う。最期も自死だしね。
本作内では、戦後、ステラが裁判にかけられるシーンが出て来て、彼女は完全アウェー状態。ナチの手先として動いていたとき、ステラは1人だけ、密告をしなかった人物がいる。ジャズバンド仲間の男性アーロン。恋愛関係ではないが、彼女はアーロンをナチに売ることはしなかった。できなかったのではなく、しなかったのであり、アーロンのドイツ脱出の手助けもしている。それでアーロンは戦争を生き延びることが出来た。
アーロンは、戦後、ステラが仲間にして来た裏切り行為を知って「君は怖ろしいことをして来た」「悔いてくれ」と冷たく彼女を突き放すのだ。けれど、ステラもジャズバンド仲間の女性に密告されている。彼女は多くの同胞を裏切ったが、裏切られてもいる。裏切った数の方が多ければ、裏切られたことは相殺されるのか。
私がアーロンだったらどうするかなぁ、、、と考えてしまった。彼女の密告によって、自分の大切な人たちが収容所送りにされていたら、やはり許せないだろうか。でも、自分は彼女によって助かっているのだよなぁ、、、。あんな風に彼女を切り捨てられるだろうか、、、せめて裁判で、自分のことは密告しなかった、彼女のおかげで命拾いした、、、という証言くらいはしたかも知れない。
密告というとおどろおどろしいけど、要はチクりである。チクりなんて、平和な世の中でも日常茶飯事やん。
チクりというとネガティブ感が強くなるが、これが「内部告発」となると、急に意味が変わるのだよな。往々にして、内部告発者は卑怯者のレッテルを貼られるそうだが、卑怯者の最たる者って、チクりを歓迎し、内部告発を毛嫌いする人やない? 卑怯というより、卑劣か。そんな奴だから、人にチクりを強要し、人に告発されると逆切れするんだよって、どっかの知事見てると思うよね。
◆その他もろもろ
ステラのパウラ・ベーアは相変わらず体当たり演技であった。彼女はあまり好みではないのだが、本作を見ても印象は変わらなかった。序盤のジャズシンガーとして歌っているシーンは良かったけど。
中盤で登場するロルフを演じるヤニス・ニーヴナーは、やはり美しい。ワルいヤツが妙にハマっているヤニスくんであった。「コリーニ事件」(2019)ではSSの将校を演じていたが、本作ではユダヤ人役。ベルリン大空襲のシーンが良かった。爆弾が雨霰と降って来る中で狂ったように踊るロルフとステラ。狂気そのものの時代と社会そのまんまだった。
パンフに載っているステラ・ゴルトシュラークの年表を見ると、かなり忠実にそれに沿って本作は進行しているようである。戦後の展開は若干違うようだが。前述したが、戦後の彼女はやはり少し壊れていたのだと思われる。家族のため、生きるためとはいえ、やはり、彼女のあの行動は、彼女の精神に相当な負荷がかかっていたことの証左だろう。
しかし、、、ナチもの映画はあとどんくらい作られるんでしょうか。そして、私はあとどんくらい見るんでしょうか??
ステラは、改宗し、反ユダヤ主義を標榜するようになった。