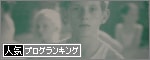作品情報⇒https://moviewalker.jp/mv32492/








以下、TSUTAYAの紹介ページよりあらすじのコピペです(青字は筆者加筆)。
=====ここから。
1923年、ロンドン郊外。作家ヴァージニア・ウルフ(ニコール・キッドマン)は病気療養のためこの地に移り住み、『ダロウェイ夫人』を執筆していた。午後にはティー・パーティが控えている…。
1951年、ロサンジェルス。『ダロウェイ夫人』を愛読する妊娠中の主婦ローラ・ブラウン(ジュリアン・ムーア)は、夫の望む理想の妻を演じることに疲れながらも、夫の誕生パーティを開くためケーキを作り始める…。
2001年、ニューヨーク。『ダロウェイ夫人』と同じ名前の編集者クラリッサ・ヴォーン(メリル・ストリープ)は、親しい友人でエイズ患者の作家リチャードが栄えある賞を受賞したことを祝うパーティの準備に取りかかっていた…。
=====ここまで。
☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆
本作は、公開時に劇場には行かなかったが、DVDで見るのは2回目。前に見たのは、DVDリリース直後だったので、多分、20年ぶりくらいに見たのだけど、今回改めて見ようと思ったのは、METライブビューイング(後述)で上映されていたから、予習のためと思いまして。何しろ、内容ほとんど覚えていなかったもので、、、。
~~以下、ネタバレしています(結末に触れています)。~~
◆いつの時代も女はメンドクサイ。ええ、ええ、そーでしょうとも。
そもそもヴァージニア・ウルフにあまり良いイメージがなく、最初に見たときもピンと来なかったのだが、今回は、感動した、、、というのとはちょっと違うが、ものすごくグッと来た。これって、私が年とったからですね、間違いなく。
最初に見たときは、鬱映画というか、救いがない感じがしたが、それは私の理解力の低さの問題だったのだなと感じた次第。
肝心のヴァージニア・ウルフ本人のエピソードは一番印象が薄く、ローラの巻はひたすら辛い。クラリッサの巻では、リチャードが見ていて苦しく、一番哀しかった。で、最後の最後に、リチャードの実母がローラだと分かり、トドメを刺された感じであった。
ネットの感想を見ると、3人の女性たちが何をあんなに悩んでいるのかがよく分からん、というのが結構目に付いた。いつの時代も女はメンドクサイ、とか書いている人(男)もいた。悪かったね、メンドクサくて。
特にローラについては、あんなに恵まれた環境で生活できているのに、何が不満なのか?と。
しかし、これは、30代以降の女性ならかなり分かるんじゃないだろうか。ただ、今回の“分かる”は、初回のときのそれとは全然レベルが違う。正確に言えば、前回は、分かるというより“想像できる”だったが、今回はもう、肌感覚でリアルに分かる。嗚呼、、、ツラい、、、見ていて胸抉られる感じで分かる。
ローラは、おそらく、一般的に女性に求められるケア能力というか、そういう適性がものすごく低い人なんだよね。そもそも好きじゃないんだと思うが、世間は(夫も)女はそんなもんとしか見ない中で、自分の在り様に強い違和感を抱きながら日々を生きて行かなくてはならない辛さ。時代の要請に従わざるを得ないがために、まったく自分に合わない鋳型に嵌められる。こんな苦しみってあるだろうか。そら、死にたくもなるわ、、、と。
子供を捨てることで、辛うじて自死を免れたわけだが、こういう人を世間は“母性本能がない”とか言って責めるんですよ。捨てられた子からすればトンデモな話に違いないけど、そもそも母性本能をみんな信じ過ぎ。母性とか母性本能とか、科学的な確からしさをもって世間は言うけれど、それで苦しんでいる母親は世界中にごまんといるのだ。出産を経験した女でも、母親でいることが苦しいと感じるのは、別に不思議でも何でもないと思うのだが、なぜ世間は母親にばかり家族のケアの役割を負わせようとするのか。
ローラは、むしろ、子を捨てることで、自分だけでなく、子も守ったと言えるかも知れない。結果的に息子のリチャードは自死したが、自死の直接的な原因はエイズの進行であり、遠因として母親の喪失はあるに違いないが、ローラが我慢してあのまま母親を続けていたら、もっと歪な親子関係が形成されて、リチャードの人生はもっと悲惨だった可能性もある。ローラは、最善ではないが、最悪ではない“マシな”選択をしたのだ、多分。
私の母親も、結局のところ、あまり母親に向いていない人だったのだと思うが(実際、自分は生まれ変わったら結婚なんか絶対しないとしょっちゅう言っていた)、それでも周囲の圧力に反発する気力も能力もないから母親で居続けざるを得ず、引き換えに娘二人を過剰に支配・抑圧することで辛うじて自分を保っていたのだろうと、娘の私はこの歳になってようやく冷静に分析できるようになってきた。
◆オペラ化された「めぐりあう時間たち」
で、今回、本作を見た後に、METライブビューイングの同タイトルを見たのだが、このお話は、圧倒的に舞台向き、しかも、オペラ向き(あるいはミュージカルでも良いのだろうが)だということを見せつけられた感じだった。
つまり、本作は、3つの時代に生きるそれぞれのダロウェイ夫人(orウルフ)を描いているのだけど、映像だとそれをうまく表現する演出が難しい。画面を3分割して3人の女優たちに語らせるなんてのは、かなり違和感があるし、陳腐になるだろうから。本作について難解だとか、訳が分からんとかいう感想が並ぶのも、ココに理由があるのだろう。
けど、舞台だと、それが容易に表現できる。同じ舞台上に3人を配し、それぞれが別の時空にいると設定しながら、同じアリアを歌うことで融合させることが出来るのだよ。すげー!
ここで大事なのは、“歌う”ということ。3人の心情をそれぞれが独白で表現する演劇よりも、同じ歌を3人が歌うことで、時代を超えて共通の苦悩を抱えながら生きるというテーマが、見る者にダイレクトに伝わることがよく分かった。これこそ、歌で表現する意味があるのだなあ、、、と。
いつもは、突然歌い出すミュージカルはヘンだ、と書いているのだけど、それはオペラでもまあ似たような感じを持っていたのだが、今回、初めてオペラがオペラでなければならない理由がちょっと分かった気がする。
今シーズンのMETライブビューイングの演目の中に「めぐりあう時間たち」とあるのを見て、正直驚いた。あの話をオペラでどーやって??と。けれど、今は、オペラ化した人の英断に驚くばかり。世界初演とのことだが、これは定番で今後も度々上演されてほしい。世界初演だからだろうけど、主演3人はルネ・フレミング、ケリー・オハラ、ジョイス・ディドナートと、豪華そのもの。映画では一番印象の薄かったウルフだが、オペラではディドナート演ずるウルフが一番印象に残った。
映画を見て、オペラを見て、相乗効果で感激。こういうのって、滅多にないことだから、幸せな時間でございました。
『ダロウェイ夫人』と原作を読んでみるか、、、。