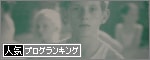上田秋成の「雨月物語」から、「蛇性の婬」「浅茅が宿」を下敷きにした物語。
時は戦国時代、思いがけないことから欲をかいた源十郎(森雅之)は、ある日、不思議な姫・若狭(京マチ子)と婆やに誘われ朽木屋敷へと足を踏み入れる。そこは、何とも不思議な邸宅で、源十郎は、若狭たちに歓待され、すっかり夢心地に。若狭との享楽の日々に現を抜かす。
が、源十郎は国元に妻・宮木(田中絹代)と息子を置いて来た身。ある日、買い物に出た折に出会った一人の老僧に「死相が顔に出ている。早く元の家に帰れ」と言われ、ふと宮木のことを思い出し帰ろうとするのだが、、、。
京マチ子がキレイだが、かなりコワい。溝口健二監督作品の中でも随一と言われる名作。
☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜
雨月物語は、小学生の頃読んで(もちろん子ども用に書き直されたもの)、一時期、かなりハマった記憶があります。怖いけど面白い、ついつい読んでしまう、という感じだったかなぁ。もちろん、一番印象的だったのが、本作の基となった2つのお話。どっちも、あると思っていたものが、実はなかった、という幽霊譚。
前半は、源十郎が若狭に出会うまでの、宮木との夫婦としての話で、割と長い。まあ、ここで、宮木の人となりをしっかり描いているのが、後半に効いてくるのですが。
若狭の登場シーンですが。若狭の顔が、コワいです、マジで。なんていうのか、こう、、、こけしみたいで、およそこの世ならざるもの、という感じを、その1ショットで表しているのがスゴイです。
まるで憑かれたように(って実際憑かれているんですが)、若狭の後を着いて朽木屋敷へ入って行く源十郎。そして、それに続く宴のシーン。若狭は謡とともに舞い、途中から謡に低い男の声が交じりだし、これの不気味なこと。正直、見ている方も最初は「え? 空耳?」という感じで、若狭も聞こえているんだかいないんだか、舞い続けていたかと思うと、突然、「はっ! この声は!!」みたいになって恐れおののく。その声は、無念の死を遂げた若狭の父なんですが、それを説明するときに映る鎧とか、映像的に非常に不気味です。
一番怖かったのは、源十郎が夢から覚めて、朽木屋敷を出たいと若狭に言ったところ。若狭の御付きの婆やが、地獄の底から絞り出すかのようなしわがれた、それでいてドスの利いた声で、「妻子がありながら、なぜ契りを交わされた!」とかなんとか言って、源十郎をしつこくしつこく攻め立てます。「帰してください」と哀願する源十郎の背に「いいや、返さぬ!!」と唸るような叫ぶその声は、もう、おぞましいの一言。このシーンが一番怖かった。
そして、何と言っても最大の見どころは、源十郎が宮木の所に帰って来たシーンでしょうねぇ。宮木と息子に再会し喜ぶ源十郎は、ようやく心安らかに床に就くけれど、翌朝目覚めればそこに宮木はおらず、、、。
朽木屋敷でのことにしても、宮木との再会にしても、源十郎の妄想、幻想だった、ってことです。
まあ、浦島太郎とも通じるというか、夢のような日々の後に待っている恐ろしい現実ってやつです。こういう幽霊譚でなくても、普通に我々も、もの凄く楽しくて幸福な時間を過ごしたかと思った直後に突き付けられる自分の置かれた状況、、、ってのは経験していますけれども。幽霊よりもそっちの方がコワい、とも言えます。
みんシネにも書いたけど、ルイ・マル監督、ビノシュ&ジェレミー・アイアンズの『ダメージ』のラストで、アイアンズ演じる元エリート男が、思いがけず空港か駅かで見かけた、自らが身を滅ぼす原因となった、かつて狂うほど愛してしまった女(もちろんビノシュ)を「普通のオンナだ・・・」と思うシーンで、私はこの「蛇性の婬」を連想しちゃうのです。
結局、夢心地なほどの幸せな満ち足りた時間など、幻想でしかないのが人生、というものなのでは。大体、人生でそんな風に感じる時間、てのは、仕事で成功したとか、何か必死で頑張ってきたことがようやく世間に認められたとか、そんな晴れがましい時ではなく、もっと本能的な、、、そう、つまり恋愛においてしかないんじゃないでしょうか。心底好きな相手と2人だけで濃密な時間を過ごしている時、まさにその時以外にないでしょう。でも、そんなのは、幻想でしかないんだよ、と。
そして、それはある意味、真実だとも思うわけです。そんな陶酔にも似た心境は、そう、度々あっては困ります。そして長くは続かないものなのです。その後には、恐ろしいほどに冷徹な現実が横たわっているわけです。
田中絹代って、決して美人ではないけれど、独特の雰囲気がありますね。一人息子を背負い、川岸でずーっと夫の源十郎を見送るシーンが切ないです。今生の別れとなることが暗示されているシーンのように思います。
ほかにも、義弟の藤十郎夫婦の話とかもあるんですが、でもまあ、やっぱり、本作は、京マチ子と田中絹代、そして、魔物に憑かれて妻を失うことになった源十郎を演じた森雅之の3人が素晴らしいです。
また「雨月物語」読みたくなってきた。
★★ランキング参加中★★