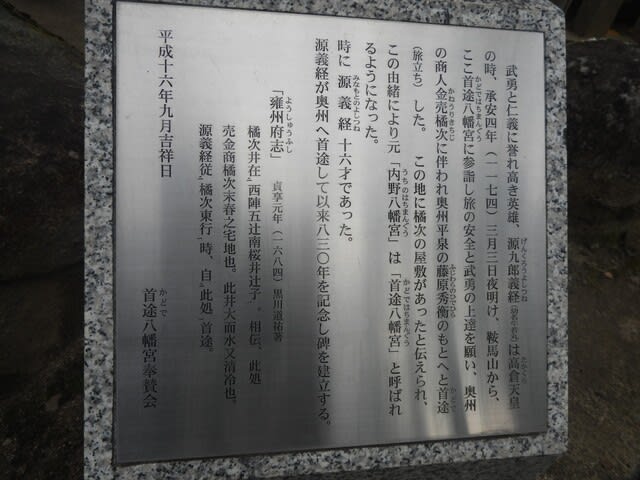昨日、真如堂の次におとずれたのはお隣の金戒光明寺です。
ここは何年か前に娘と来たことがありました。
娘が新選組が好きなので来たがっていたのですが、私はその時は全く知識がなくて、なぜ壬生寺でなくて、金戒光明寺が関係しているのか分かっていませんでした。
今から思えは、恥ずかしい限りです。



ここは、元々は法然上人が比叡山を降りてから初めて草庵を営まれた場所なんですね。
比叡山の黒谷にいたので、この場所は新黒谷とも呼ばれたそうです。



この立派な山門がなんと言っても迫力満点ですね。


前回は会津藩の墓地もお参りさせていただいたのですが、今回は別に見たい場所がありました。
京都検定の過去問題で、西翁院という塔頭の中に茶室があって名前が澱看席(よどみのせき)というそうなんです。
なぜかというと、京都の南部の方面まで見渡せて、淀競馬場がある淀まで見渡せるからだそうです。





ほんとうに淀が見えるかどうか確かめようとしましたが、、、?


公開寺院ではないので、中には入れなくて、外からではよくわかりませんでした。
まあ、仕方ありません。
もう一つ、じっくり見てみようと思っものが、、、。
通称アフロヘアーの阿弥陀様とも言われる「五劫思惟阿弥陀仏」でした。



この阿弥陀様は、阿弥陀様になる前の菩薩の時代に、ひじょーーーに長い時間考えに考えていたので、髪の毛が伸びきってアフロのようになったそうです。
どれだけ長い時間かというと「五劫」(ごこう)という時間です。
説明すると長くなるのですが、一劫というのは、空から天女が舞い降りて、天女の衣で一辺が160kmある岩をさっと撫でます。
3年に一度、天女が舞い降りてきて、その岩が全て擦り減ってしまうくらいの長ーい時間が1劫だそうです。
それを5回も繰り返すくらい永い時間考えていたそうです。
落語の「寿限無寿限無五劫の擦りきれ」というのはそのことらしいです。
気が遠くなりそうですが、面白い話なので、この機会に見ておこうと思っていました。
新選組あり、法然上人あり、よどみのせきあり、アフロ阿弥陀仏ありの金戒光明寺は、なかなかの見どころ満載の寺院でした。
金戒光明寺は私の一押しです。