
大事の思案は軽くすべし。~鍋島直茂『直茂公壁書二十一箇条』
今回は戦国時代、西国一、二の名将と称された鍋島直茂の名言をご紹介します。
大事の思案は軽くすべし。
原典は、佐賀藩に伝わる、直茂の訓戒を箇条書きにした『直茂公壁書二十一箇条』(元禄五年、石田一鼎編)です。
同書の同句は『葉隠』話者、山本常朝の家にも伝えられたようで、『葉隠』本文では次のように取り上げられました。
直茂公のお壁書に、
「大事な思案は軽くすべし」
とある。一鼎の注には、
「小事の思案は重くすべし」
としている。大事というものは、せいぜい二、三箇条くらいのものであろう。これは普段詮議しているものなので皆よく知っているはず。前もってよくよく思案しておき、いざ大事の時には取り出して素早く軽く一決せよ、との意味と思われる。事前に考えておかなければ、その場に臨んで、軽く分別することも成り難く、図に当たるかどうかおぼつかない。しかれば前もって地盤を据えておくことが
「大事な思案は軽くすべし」
といった箇条の基本だと思われる。
(『葉隠 現代語全文完訳』聞書一/四六 能文社2006)
一般的に分別や事の大きさ、人の評価などにおいて、「軽さ」は否定的に、「重さ」は肯定的に
比喩されることが多いものです。しかし、軽さはすべて悪で、重さがすべて良いというわけでもありません。文化、思想、芸術の領域では、“重さを突き抜けた軽さ”が最上位をあらわすことが往々にしてあります。偉人の言動や名人芸などには、シンプルで、どことなく飄々とした軽さが感じられるものです。
とりわけ日本文化の諸相において、「重さ」「軽さ」が修行の指標として示される例が少なくありません。たとえば、茶道では次のような「軽さ」「重さ」の案配を教えています。
◆利休百首、「所作の軽さ」
何にても道具扱ふたびごとに取る手は軽く置く手重かれ
利休の道歌を茶の湯修業の標語として集めた、とされる「利休百首」。上は道具の扱い、所作の「軽さ」「重さ」について指導したものです。
これは、たとえば道具をひょいと軽く取る、ということではなく、その後の所作もすべて見通したうえで躊躇なく一直線にまず道具を手にする。そして、床であれ畳であれ、置く場所にて道具のすわりをしかと見届けて、そっと手を放せ、と教えたのです。
◆山上宗二記、「薄茶が真の茶」
一 点前
薄茶を点てることが、専らの大事となる。これを真の茶という。世間で、真の茶を濃茶としているが、これは誤りである。濃茶の点てようは、点前にも姿勢にもかまわず、茶が固まらぬよう、息の抜けぬようにする。これが習いである。そのほかの点前については、台子四つ組、ならびに小壺・肩衝の扱いの中にある。
(『山上宗二記 現代語全文完訳』追加十体 能文社2006)
ここは「軽さ」「重さ」の代わりに、芸道でよく用いられる位の概念「真」「行」「草」をあてたもの。真の位がもっとも重く、草の位は軽い。本来、格式の高い濃茶が「真」、侘びの心で茶を喫する薄茶が「草」のはずですが、宗二は、薄茶こそ真の茶であるとしています。これは草庵小座敷では、侘びの心をなによりも尊ぶゆえに、粗茶である薄茶こそ侘び茶の根本であるとする、利休の教えを表したものでしょう。
◆芭蕉の「軽み」讃
元禄三年のとしの大火に庭の桜もなくなりたるに
焼けにけりされども花は散り済まし 北枝 (『卯辰集』)
十銭を得て芹売りの帰りけり 小春 (『卯辰集』)
蕉門金沢俳壇の二人の句です。北枝は芭蕉が『奥の細道』の旅の途次、金沢で出迎えた門人、小春(しょうしゅん)は、同じ時に芭蕉門に弟子入りした地元の薬種商。元禄三年、金沢の大火により北枝の家は燃え、庭の桜木も焼け失せてしまいました。「しかし花も散り失せた後でしたし」と自ら慰める句。そして二句目の小春に対し、芭蕉は書簡を寄せて
「両御句珍重、中にも芹売りの十銭、生涯かろきほど、わが世間に似たれば、感慨少なからず候」
と激賞するのです。
侘び寂びと評される芭蕉の句風。晩年の芭蕉はさらに句境を進め、「軽み」を追求していきます。古い門人たちに、なかなか理解されなかった芭蕉の「軽み」を入門したばかりの新弟子が巧まず吟じたのです。ちなみに江戸時代の十銭は現代の貨幣価値では約250円。わが世間に似たれば(自分の人生と同じだ)と、芭蕉はこの句に称賛を惜しみません。
たとえば俳句や文芸では、技術や経験の蓄積に応じて「軽→重→軽」と成長、発展していくのかもしれません。「行商人は今日も250円もらって帰った」には、人のなりわい、人生の歩みが言い尽くされて、初心の「軽」から、究極の「軽」へと一息にはばたく自在の翼があるのです。
大事の思案を「重く」することは、一所を堂々巡りする死に手です。何事にもとらわれぬ自在の境地を先人は「軽み也」と教えてくれました。















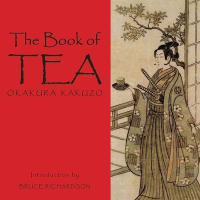










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます