
【おくのほそ道】
八日、月山に登る。木綿しめ を身に引きかけ、宝冠に頭を包み、強力と
いうものに導かれて、雲霧山気の中に、氷雪を踏んで登ること八里。この
まま日月の軌跡に乗り、雲関に入ってしまうのではないかと不安となり、
息もあがり身も凍えて頂上に至れば、日は沈み月が現れる。笹を敷き、篠
を枕に伏して、夜明けを待つ。日が出て雲が消えたので、湯殿山へと下った。
谷のかたわらに鍛治小屋 というものがある。この国の鍛治は、霊水を選
び、ここに潔斎沐浴して剣を打つ。最後に「月山」と銘を切り、世間に賞せ
られる名刀となる。かの竜泉に剣を鍛えると聞く、干将・莫耶の故事 にな
らうものか。道の達人、執心浅からぬことを思い知らされる。岩に腰掛け
しばらく休んでいると、三尺ほどの桜のつぼみが半ば開いている。降り積も
る雪の下に埋もれても、春を忘れぬ遅桜の花の心がいじらしい。炎天の梅花 、
ここに香るようである。行尊僧正の歌 の哀れも思い出され、それにさえ勝
って感じられる。そもそもこの山中の詳細は、行者の法度として他言を禁じ
ている。よって筆をとどめ、記すわけにはまいらぬ。坊に帰れば、阿闍梨の
求めに応じて、三山巡礼の数句短冊に書く。
涼しさやほの三か月の羽黒山
鑑賞(すっとした三日月が、黒々とした羽黒山にかかっている。里に下りて
もなお高山の冷気が思い起こされ清々しいものだ)
雲の峰幾つ崩れて月の山
鑑賞(昼間は湧き上がる入道雲の峰に隠されていたが、夜となって冴え冴えと
月光が雲を割り、厳かな山の峰を顕した)
語られぬ湯殿にぬらす袂かな
鑑賞(法度により語ってはならぬ湯殿山中の神々しさを、思うにつけてもあ
りがたく、袂もこうして濡れるのだ)
湯殿山銭ふむ道の涙かな 曾良
鑑賞(山中の禁制に地に落ちたものは、拾ってはならぬという。道に落ちた
賽銭の上を無心に歩む道者の尊さに自ずと感涙をもよおすばかり)
【曾良旅日記】
○六日。天気よし。登山する。三里で強清水 。二里で平清水 。二里で高
清水に着く。ここまでは馬でも登れる道である(人家、小屋がけあり)。弥
陀原 に小屋あり。昼食をとる。(ここから、補陀落、にごり沢、御浜など
へかかるという)難所となる。御田がある。行者戻り には小屋がある。申
の上刻、月山頂上に至る。まず御室を拝して、角兵衛小屋に行く。雲が晴
れて、御来光は見えなかった。夕方には東に、明け方には西に見えるとい
う。
○七日。湯殿山へ行く。鍛冶屋敷に小屋あり。牛首 (これより本道寺へも、
岩根沢 へも行ける)に小屋あり。不浄垢離の場、ここで水浴びする。少し
行ったところで草鞋を履き替え、木綿締めをかけなどして湯殿山神社神前
に下る(神前よりすぐのところに注連掛口(しめかけ)の注連寺・大日坊 を
通って鶴が岡へ出る道がある)。ここから奥は、所持した金銀銭を持って
帰ることはできない。下に落としたものすべて、拾うことも禁じられる。
浄衣・法冠・木綿しめだけで行くのだ。昼時分、月山に帰る。昼食をとり、
下向。強清水まで光明坊から弁当を持たせ、逆迎えにくる。日暮れに及ん
で南谷に帰る。はなはだ疲れる。
△草鞋脱ぎ替え所より、志津 というところへ出て、最上へ行く。
△道者坊 に一泊。宿賃は、三人で一歩。月山では一夜宿。小屋
賃、二十文。あちこちの拝観料が二百文以内。賽銭も二百文以内。あれや
これやで、銭は一歩もあまらなかった。
【奥細道菅菰抄】
木綿しめを身に引きかけ、宝冠に頭を包み、強力というものに導かれて(中
略)日月の軌跡に乗り、雲関に入ってしまうのではないかと不安となり(中
略)日は沈み月が現れる
月山・湯殿に登るには、潔斎修行しなければ許されない。
木綿しめは、こよりで仕立てた修験袈裟のこと。当山へ登る人は、潔斎中よ
り下山まで、これを襟にかける。この木綿しめ、および旅硯・銭袋・蓑笠な
ど、後に翁の門人、惟然坊に伝わり、その弟子、播州姫路千山に帰属する。
千山の子、寒瓜が、同国増位山に風羅堂を造立し、これらの調度ならび、惟
然坊作の翁の木像を納めた。
宝冠は、白い布で頭を包むことをいう。
強力は、修験の弟子で、笈などを担がせ従わせた者。すなわち登山の案内先
達である。ゆえに、別名先達ともいう。
日月の軌跡に乗り、雲関に入るとは、『詩経』に、「平歩雲霄に入る、
というがごとし」。高山に登るさまを、雲を凌ぐ、とたとえたのだ。雲関は、
道家の説に、天上の六関などという。(例が多いので他は記さず)
谷のかたわらに鍛治小屋というものがある(中略)かの竜泉に剣を鍛えると聞
く、干将・莫耶の故事にならうものか。道の達人、執心浅からぬことを思い
知らされる
鍛治は、本字、鍛冶。たんやと読むべき。日本の俗字、瑕治と混同し、その
音にて誤って綴ったものであろう。月山の鍛冶小屋は現在後嗣が絶え、ただ
名のみ残って、道者の宿となっているばかり。
竜泉に剣を鍛えるとは『史記』、荀卿の伝の註、晋の太康の地理記にいう。
「汝南の西、平原に、竜淵水あり。刀剣を用いて淬すべし」とある。淬すと
は、俗にいう水で刀を鍛えることである。
干将(かんしょう)・莫耶(ばくや)は、いにしえの鍛冶の名工の名。『呉越
春秋』にいう。「干将は呉の人である。欧冶子と同じ師につき、闔閭(こうり
ょ)より二本の剣を作るよう命ぜられる。その一を干将といいい、二を莫耶と
いう。莫耶は干将の妻の名である。金鉄を炉に入れたが、なかなか溶けぬ。
干将夫妻は、すなわち髪を断ち、指を切って、炉中に投じる。たちまち溶け、
ついに剣となった。陽剣には干将が亀紋を刻み、陰剣には莫耶が縵様を入れ
る。干将は陽剣を隠し、陰剣をもって闔閭に奉じた」。『太平広記』にいう。
「干将・莫耶の剣はすべて銅をもって鋳る。鉄ではない」と。
炎天の梅花、ここに香るようである
この句はきっと出典があるはずだ。いまだ判明せず。
(訳者注 『禅林句集』(坤巻)の中の「雪裏芭蕉摩詰画。炎天梅蘂簡斎詩」に
よる。「雪裏芭蕉摩詰画」は、雪の中の芭蕉の株は摩詰(唐代の詩人・画家)が
描いたもの、「炎天梅蘂簡斎詩」の、炎天の梅花は簡斎(宋代の詩人)が詩で
詠んだものといった意味である。「雪裏芭蕉」と「炎天梅蘂(花)」は、いずれ
も現実には見られないもの。ところが、禅宗ではこれを鍛錬によって心眼で見
えるものとし、一般には珍しいものの例えとされている)
行尊僧正の歌の哀れも思い出され
行尊は『元享釈書』にいう。「諫議大夫。行尊は源の基平の子である。十二
の年、三井寺の明行に預け、出家させられる。もとより托鉢修行を好む。十
七の年、ひそかに園城寺を出て、名山霊区を跋渉する。永久四年、園城寺の
に補せられる。保安四年、延暦寺の座主を任じ、長承三年、勅を受け衆
僧の上座となる」と。
僧正は、日本の僧爵。(行基より始まることは前述)
歌の哀れとは、『金葉集』に、大峰にて思いがけず桜の咲く景色を見て詠む、
とある。
「もろともにあはれと思へ山ざくら花より外にしる人もなし」行尊。
湯殿山銭ふむ道の涙かな 曾良
この山中の掟で、下に落ちた物を拾うことはできない。ゆえに道者の投げ捨
てた金銀は、小石のごとく、銭は土砂に等しい。人は、その上を行き来する
のだ。
芭蕉の名言講座 7/14より
http://bit.ly/doMKCP
八日、月山に登る。木綿しめ を身に引きかけ、宝冠に頭を包み、強力と
いうものに導かれて、雲霧山気の中に、氷雪を踏んで登ること八里。この
まま日月の軌跡に乗り、雲関に入ってしまうのではないかと不安となり、
息もあがり身も凍えて頂上に至れば、日は沈み月が現れる。笹を敷き、篠
を枕に伏して、夜明けを待つ。日が出て雲が消えたので、湯殿山へと下った。
谷のかたわらに鍛治小屋 というものがある。この国の鍛治は、霊水を選
び、ここに潔斎沐浴して剣を打つ。最後に「月山」と銘を切り、世間に賞せ
られる名刀となる。かの竜泉に剣を鍛えると聞く、干将・莫耶の故事 にな
らうものか。道の達人、執心浅からぬことを思い知らされる。岩に腰掛け
しばらく休んでいると、三尺ほどの桜のつぼみが半ば開いている。降り積も
る雪の下に埋もれても、春を忘れぬ遅桜の花の心がいじらしい。炎天の梅花 、
ここに香るようである。行尊僧正の歌 の哀れも思い出され、それにさえ勝
って感じられる。そもそもこの山中の詳細は、行者の法度として他言を禁じ
ている。よって筆をとどめ、記すわけにはまいらぬ。坊に帰れば、阿闍梨の
求めに応じて、三山巡礼の数句短冊に書く。
涼しさやほの三か月の羽黒山
鑑賞(すっとした三日月が、黒々とした羽黒山にかかっている。里に下りて
もなお高山の冷気が思い起こされ清々しいものだ)
雲の峰幾つ崩れて月の山
鑑賞(昼間は湧き上がる入道雲の峰に隠されていたが、夜となって冴え冴えと
月光が雲を割り、厳かな山の峰を顕した)
語られぬ湯殿にぬらす袂かな
鑑賞(法度により語ってはならぬ湯殿山中の神々しさを、思うにつけてもあ
りがたく、袂もこうして濡れるのだ)
湯殿山銭ふむ道の涙かな 曾良
鑑賞(山中の禁制に地に落ちたものは、拾ってはならぬという。道に落ちた
賽銭の上を無心に歩む道者の尊さに自ずと感涙をもよおすばかり)
【曾良旅日記】
○六日。天気よし。登山する。三里で強清水 。二里で平清水 。二里で高
清水に着く。ここまでは馬でも登れる道である(人家、小屋がけあり)。弥
陀原 に小屋あり。昼食をとる。(ここから、補陀落、にごり沢、御浜など
へかかるという)難所となる。御田がある。行者戻り には小屋がある。申
の上刻、月山頂上に至る。まず御室を拝して、角兵衛小屋に行く。雲が晴
れて、御来光は見えなかった。夕方には東に、明け方には西に見えるとい
う。
○七日。湯殿山へ行く。鍛冶屋敷に小屋あり。牛首 (これより本道寺へも、
岩根沢 へも行ける)に小屋あり。不浄垢離の場、ここで水浴びする。少し
行ったところで草鞋を履き替え、木綿締めをかけなどして湯殿山神社神前
に下る(神前よりすぐのところに注連掛口(しめかけ)の注連寺・大日坊 を
通って鶴が岡へ出る道がある)。ここから奥は、所持した金銀銭を持って
帰ることはできない。下に落としたものすべて、拾うことも禁じられる。
浄衣・法冠・木綿しめだけで行くのだ。昼時分、月山に帰る。昼食をとり、
下向。強清水まで光明坊から弁当を持たせ、逆迎えにくる。日暮れに及ん
で南谷に帰る。はなはだ疲れる。
△草鞋脱ぎ替え所より、志津 というところへ出て、最上へ行く。
△道者坊 に一泊。宿賃は、三人で一歩。月山では一夜宿。小屋
賃、二十文。あちこちの拝観料が二百文以内。賽銭も二百文以内。あれや
これやで、銭は一歩もあまらなかった。
【奥細道菅菰抄】
木綿しめを身に引きかけ、宝冠に頭を包み、強力というものに導かれて(中
略)日月の軌跡に乗り、雲関に入ってしまうのではないかと不安となり(中
略)日は沈み月が現れる
月山・湯殿に登るには、潔斎修行しなければ許されない。
木綿しめは、こよりで仕立てた修験袈裟のこと。当山へ登る人は、潔斎中よ
り下山まで、これを襟にかける。この木綿しめ、および旅硯・銭袋・蓑笠な
ど、後に翁の門人、惟然坊に伝わり、その弟子、播州姫路千山に帰属する。
千山の子、寒瓜が、同国増位山に風羅堂を造立し、これらの調度ならび、惟
然坊作の翁の木像を納めた。
宝冠は、白い布で頭を包むことをいう。
強力は、修験の弟子で、笈などを担がせ従わせた者。すなわち登山の案内先
達である。ゆえに、別名先達ともいう。
日月の軌跡に乗り、雲関に入るとは、『詩経』に、「平歩雲霄に入る、
というがごとし」。高山に登るさまを、雲を凌ぐ、とたとえたのだ。雲関は、
道家の説に、天上の六関などという。(例が多いので他は記さず)
谷のかたわらに鍛治小屋というものがある(中略)かの竜泉に剣を鍛えると聞
く、干将・莫耶の故事にならうものか。道の達人、執心浅からぬことを思い
知らされる
鍛治は、本字、鍛冶。たんやと読むべき。日本の俗字、瑕治と混同し、その
音にて誤って綴ったものであろう。月山の鍛冶小屋は現在後嗣が絶え、ただ
名のみ残って、道者の宿となっているばかり。
竜泉に剣を鍛えるとは『史記』、荀卿の伝の註、晋の太康の地理記にいう。
「汝南の西、平原に、竜淵水あり。刀剣を用いて淬すべし」とある。淬すと
は、俗にいう水で刀を鍛えることである。
干将(かんしょう)・莫耶(ばくや)は、いにしえの鍛冶の名工の名。『呉越
春秋』にいう。「干将は呉の人である。欧冶子と同じ師につき、闔閭(こうり
ょ)より二本の剣を作るよう命ぜられる。その一を干将といいい、二を莫耶と
いう。莫耶は干将の妻の名である。金鉄を炉に入れたが、なかなか溶けぬ。
干将夫妻は、すなわち髪を断ち、指を切って、炉中に投じる。たちまち溶け、
ついに剣となった。陽剣には干将が亀紋を刻み、陰剣には莫耶が縵様を入れ
る。干将は陽剣を隠し、陰剣をもって闔閭に奉じた」。『太平広記』にいう。
「干将・莫耶の剣はすべて銅をもって鋳る。鉄ではない」と。
炎天の梅花、ここに香るようである
この句はきっと出典があるはずだ。いまだ判明せず。
(訳者注 『禅林句集』(坤巻)の中の「雪裏芭蕉摩詰画。炎天梅蘂簡斎詩」に
よる。「雪裏芭蕉摩詰画」は、雪の中の芭蕉の株は摩詰(唐代の詩人・画家)が
描いたもの、「炎天梅蘂簡斎詩」の、炎天の梅花は簡斎(宋代の詩人)が詩で
詠んだものといった意味である。「雪裏芭蕉」と「炎天梅蘂(花)」は、いずれ
も現実には見られないもの。ところが、禅宗ではこれを鍛錬によって心眼で見
えるものとし、一般には珍しいものの例えとされている)
行尊僧正の歌の哀れも思い出され
行尊は『元享釈書』にいう。「諫議大夫。行尊は源の基平の子である。十二
の年、三井寺の明行に預け、出家させられる。もとより托鉢修行を好む。十
七の年、ひそかに園城寺を出て、名山霊区を跋渉する。永久四年、園城寺の
に補せられる。保安四年、延暦寺の座主を任じ、長承三年、勅を受け衆
僧の上座となる」と。
僧正は、日本の僧爵。(行基より始まることは前述)
歌の哀れとは、『金葉集』に、大峰にて思いがけず桜の咲く景色を見て詠む、
とある。
「もろともにあはれと思へ山ざくら花より外にしる人もなし」行尊。
湯殿山銭ふむ道の涙かな 曾良
この山中の掟で、下に落ちた物を拾うことはできない。ゆえに道者の投げ捨
てた金銀は、小石のごとく、銭は土砂に等しい。人は、その上を行き来する
のだ。
芭蕉の名言講座 7/14より
http://bit.ly/doMKCP

















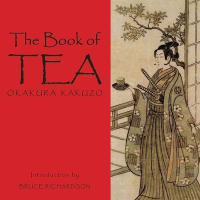








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます