今回は、用土城への再訪問についてレポートいたします。
調査日は、2018.01.29です。
今回もしつこく絡んでみたつもりなのですが、なかなか絡む余地が少なかったです。
前回、訪問は1985年頃のことでした。
当時はこのような状況でした。

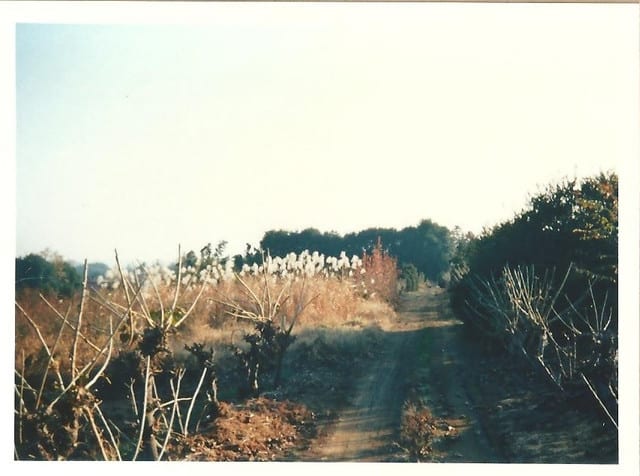
用土城は深皿を伏せたような、なだらかな丘の上にあります。
その丘の北東の隅にある、小さな公園は今も健在で、用土城の石碑もありました。

正直、開発の波に耐えきれず、状況が大きく変化していると思ったのですが、そんなことも無く、
地元の人たちの努力で、守られているようです。





城と推定される範囲は広いので、遺構の存在を期待してしまうのですが、通りがかりの地元の人は
「この一帯が城跡だっつーんだけど、なんにも残ってねーな」とつれない返事です。
まあ、実際、わたしも資料を漁った結果、「何にも残って無さげ」だとは思っていましたけどね。
ススキの生えた土の道も、今やりっぱな舗装道路です。

ここから私の無駄な抵抗の始まりです。
折角、丘の上に立ったのですから、斜面の状況くらいは観察しないとね。




上の写真は、東側斜面の写真なのですが、城特有の一種の険しい表情が全くないのですね。
遠方、駐車場わきに土の盛り上がりがあったりしますが、残土を積んだもののように見えますね。すごく。
城址碑は丘の中腹にあるので、今度は丘の頂上に上がってみます。


いまでも、立派に農業が営まれているのはいいことです。
緩やかな坂をアッというまに登り切ります。

頂上ということのほども無く下り坂です。
写真はその坂下から城跡を見上げて撮ったものです。

丘のすそ、平地との接続部分には、一段下がった荒れ地があり、もともとが低湿地だった可能性をうかがわせています。


直接に堀跡だと言えませんが、用土城の防衛機構というのは、こうした自然地理的条件の利用にあったのかもしれません。
さて、このまま大通りに出ては、調査が終わってしまうので、一度城址碑まで戻り、
今度は、かつて泥道だった道を南に走ります。
かつては用土城の南端にちょっとした林があっったので、遺構が残っているとすればその辺りだろうという読みです。
少し走ると水路がありました。
この付近がかつて林だった場所なのです。





上の写真はいずれも、同じ水路を橋の左右から撮影したものです。
もし水堀があったとすれば、この堀などは有力な遺構の候補でしょうね。
この水路の脇に竹林があるのですが、その中に土塁状の盛り上がりがありました。



城址碑のあった方が本丸でしょうから、外側に土塁、内側に水堀は防衛機構としては逆になるので、
すると、この水路は単なる水路なのか?などと思いました。
もう少し、城跡に付属した低地などを観察して、大胆な視点を打ち出したかったのですが、
そうそう、うまく行くものではないです。
調査日は、2018.01.29です。
今回もしつこく絡んでみたつもりなのですが、なかなか絡む余地が少なかったです。
前回、訪問は1985年頃のことでした。
当時はこのような状況でした。

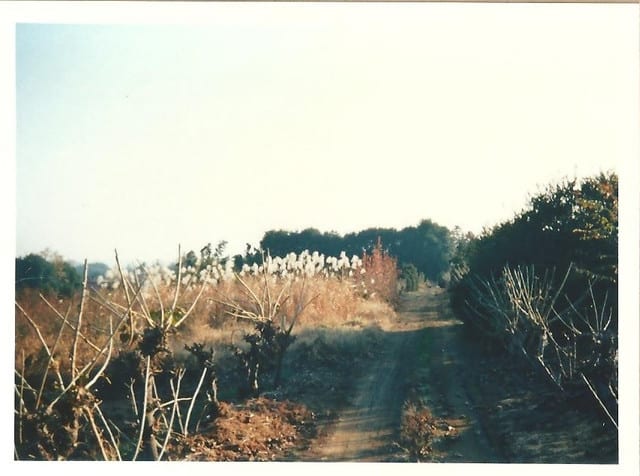
用土城は深皿を伏せたような、なだらかな丘の上にあります。
その丘の北東の隅にある、小さな公園は今も健在で、用土城の石碑もありました。

正直、開発の波に耐えきれず、状況が大きく変化していると思ったのですが、そんなことも無く、
地元の人たちの努力で、守られているようです。





城と推定される範囲は広いので、遺構の存在を期待してしまうのですが、通りがかりの地元の人は
「この一帯が城跡だっつーんだけど、なんにも残ってねーな」とつれない返事です。
まあ、実際、わたしも資料を漁った結果、「何にも残って無さげ」だとは思っていましたけどね。
ススキの生えた土の道も、今やりっぱな舗装道路です。

ここから私の無駄な抵抗の始まりです。
折角、丘の上に立ったのですから、斜面の状況くらいは観察しないとね。




上の写真は、東側斜面の写真なのですが、城特有の一種の険しい表情が全くないのですね。
遠方、駐車場わきに土の盛り上がりがあったりしますが、残土を積んだもののように見えますね。すごく。
城址碑は丘の中腹にあるので、今度は丘の頂上に上がってみます。


いまでも、立派に農業が営まれているのはいいことです。
緩やかな坂をアッというまに登り切ります。

頂上ということのほども無く下り坂です。
写真はその坂下から城跡を見上げて撮ったものです。

丘のすそ、平地との接続部分には、一段下がった荒れ地があり、もともとが低湿地だった可能性をうかがわせています。


直接に堀跡だと言えませんが、用土城の防衛機構というのは、こうした自然地理的条件の利用にあったのかもしれません。
さて、このまま大通りに出ては、調査が終わってしまうので、一度城址碑まで戻り、
今度は、かつて泥道だった道を南に走ります。
かつては用土城の南端にちょっとした林があっったので、遺構が残っているとすればその辺りだろうという読みです。
少し走ると水路がありました。
この付近がかつて林だった場所なのです。





上の写真はいずれも、同じ水路を橋の左右から撮影したものです。
もし水堀があったとすれば、この堀などは有力な遺構の候補でしょうね。
この水路の脇に竹林があるのですが、その中に土塁状の盛り上がりがありました。



城址碑のあった方が本丸でしょうから、外側に土塁、内側に水堀は防衛機構としては逆になるので、
すると、この水路は単なる水路なのか?などと思いました。
もう少し、城跡に付属した低地などを観察して、大胆な視点を打ち出したかったのですが、
そうそう、うまく行くものではないです。









































































