阿久悠からの影響は大きいと思う。
阿久悠の書いた詞というか歌が最も輝いていたとき、私は最も歌が好きだった頃だったからである。
その歌は、かっこよかったり、さわやかだったり、熱かったり、醒めていたり、包み込んでいたり、突き放していたり、共感できたり、反発したり・・・ありとあらゆるものがあったような気がする。
そして、ありとあらゆる感情というのを一人の人間が持っているのだ、ということを知ったりしたのである。
この本を読むと、阿久悠の心のうちを吐き出したものだけが詞となっているのではなく、作詞の依頼があって、その依頼に沿ったものを書いたり、あるいは歌を歌う人間に合わせてひねり出したりして書いていたものが多い。
ゆえに、色々なタイプの詞が出てきたんだと思う。
とはいえ、こんなに色々なタイプの詞を書くというのはすごいことである。
この本は阿久悠の書いた詞を題材にその詞の書かれた時代と現代とを論じている。エッセイとなっているが、実は比較時代史のようなのである。
そして、その比較される時代の双方を経験している私はすごく共感できるのである。
巻末の解説は近田春夫で、この人選もすばらしい。
そしてこの解説もすばらしい。
ということで読み終えた途端に文春文庫の「夢を喰った男たち」を買ってきて読み始めたのである。
「ブログ村」というところにこのブログを登録しています。読書日記を探しているかた、下のバナーをクリックするとリンクされていますので、どうぞご覧ください。またクリックしてもらうと私の人気度が上がるということにもなります。そのへんもご考慮いただき、ひとつよろしくお願いします。

阿久悠の書いた詞というか歌が最も輝いていたとき、私は最も歌が好きだった頃だったからである。
その歌は、かっこよかったり、さわやかだったり、熱かったり、醒めていたり、包み込んでいたり、突き放していたり、共感できたり、反発したり・・・ありとあらゆるものがあったような気がする。
そして、ありとあらゆる感情というのを一人の人間が持っているのだ、ということを知ったりしたのである。
この本を読むと、阿久悠の心のうちを吐き出したものだけが詞となっているのではなく、作詞の依頼があって、その依頼に沿ったものを書いたり、あるいは歌を歌う人間に合わせてひねり出したりして書いていたものが多い。
ゆえに、色々なタイプの詞が出てきたんだと思う。
とはいえ、こんなに色々なタイプの詞を書くというのはすごいことである。
この本は阿久悠の書いた詞を題材にその詞の書かれた時代と現代とを論じている。エッセイとなっているが、実は比較時代史のようなのである。
そして、その比較される時代の双方を経験している私はすごく共感できるのである。
巻末の解説は近田春夫で、この人選もすばらしい。
そしてこの解説もすばらしい。
ということで読み終えた途端に文春文庫の「夢を喰った男たち」を買ってきて読み始めたのである。
「ブログ村」というところにこのブログを登録しています。読書日記を探しているかた、下のバナーをクリックするとリンクされていますので、どうぞご覧ください。またクリックしてもらうと私の人気度が上がるということにもなります。そのへんもご考慮いただき、ひとつよろしくお願いします。











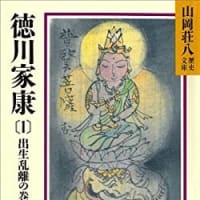
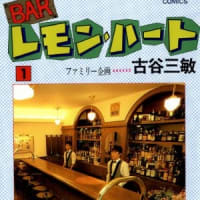
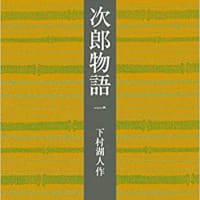
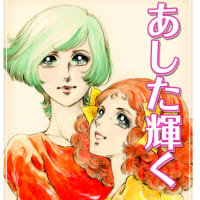
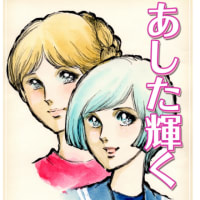
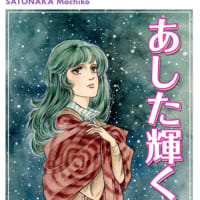
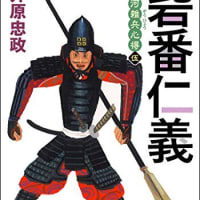
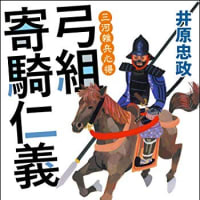
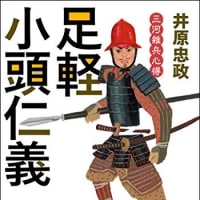
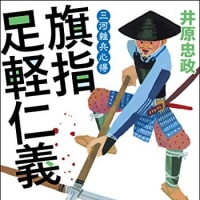





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます