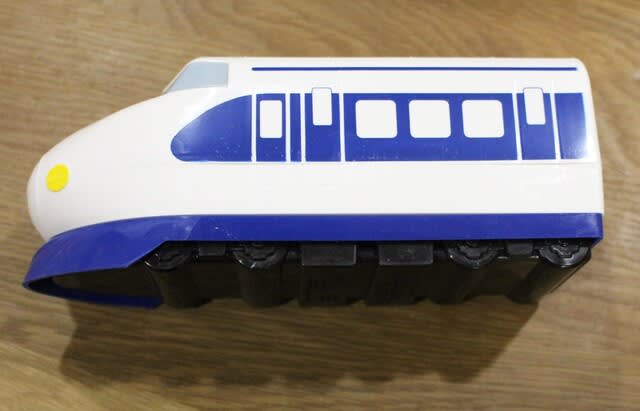とれいん誌に関連して東急の話を先日もこのブログ内でしましたが、世田谷美術館では、東急100周年に関連して「東急 暮らしと街の文化」という展覧会が開催されており(2/2まで)、私も観てきました。


(上の入り口の手前にあって、最初に現れるのがこのレール。東横百貨店解体の際、工事現場から「発掘」された玉電渋谷駅のものです)

(台車の大型模型もありました。かつての7000形のパイオニアⅢ台車です。)
東急の路線を構成する目黒蒲田電鉄から100年ということで、まずは社業のメインである鉄道について、電車とバスの博物館の収蔵品を中心に、写真、模型、昔の沿線案内、記念乗車券などの展示に多くの人が集まっていました。沿線案内などは書物で見たことがあるものが多かったのですが、実物がこれだけ多く展示されますと、なかなか見どころがあります。記念乗車券もいろいろな種類が出ていたのですね。

(ガラス越しになりますが、戦前の沿線案内の表紙はこちらのキハ1形。これは話せば長くなりますが、戦前の一時期、東横線では急行運用に気動車が使われていました)

(電車、バスの模型も多く展示されていました。こちらは1923年当時の目黒駅と周辺の模型)

(暗くて恐縮ですが、1966年当時の溝の口駅。当時は溝ノ口と「の」がカタカナ表記でした)

(こちらは1958年当時の蒲田駅。いずれのジオラマもデフォルメなし、省略なし、スケールに忠実という感じですので、どこかの「えせジオラマ」とはリアルさが違います。手前に記念乗車券が見えます)
車輛の写真も数多くありました。写真も1970年頃ですと、7000形が中心選手で、デビューしたばかりの8000形は「末弟」という感じなのがおもしろいですね。
貴重な図面などの展示もあって、中身の濃い展示です。写真撮影が可能なのはここまでです。

(名車・3450形の形式図です)

(7000形の図面もありました)
東急と言いますと沿線開発とともに伸長したということもあり、都市開発について章を割いています。田園都市構想など、東急沿線と言いますと有名なものもありますが、建築家・蔵田周忠によるバウハウス建築などに影響を受けた住宅群の建設(結局住宅群にはならず、数件が建築されたのみでした)などの話は貴重ですね。
美術館ということもあり、東急沿線にゆかりのある画家などの美術作品の展示もあります。向井潤吉、野見山暁治、舟越桂、長谷川町子とさまざまな作品が並び、美術館らしい感じがします。また、岡本太郎は上野毛にアトリエを持ち、前衛芸術運動「夜の会」がそこで生まれたと述べています。
沿線風景を中心に街を撮った写真も展示されています。桑原甲子雄の撮った渋谷は「地元」だった亡父も見た風景だったことでしょうし、アラーキーこと荒木経惟の1980年代の渋谷は、私が見た風景でもあります。アラーキーの撮る東京の風景は、都市のリアルを足し算も引き算もしないで見せている感があります。
東急というと文化事業、教育事業にも力を入れており、古くは多摩川河川敷にあった「多摩川スピードウェイ」の展示もあります。戦前にあったオーバルコースの「サーキット」であり、昭和11年のレースのエントリーリストなども展示されていますが、若き日の本田宗一郎の名前が載っていたりします。サーキットの観客席だった部分は戦後も河川敷の石段として、最近まで健在でした。

(こちらのリーフレットの写真は鉄道関連の展示の中で、沿線案内などとともに写真で展示されていたもの)
また、東横劇場に東急文化会館と今は無い施設についても紹介があります。文化会館のプラネタリウムの丸屋根も渋谷のランドマークでした。高校生の頃、父と三者面談の帰りに文化会館の中の蕎麦屋に入ったことを思い出しました。方向感覚が分からなくなるくらい再開発が進む今の渋谷と違い、駅前に高層建築もなく、東急文化会館や東急プラザがランドマークだった頃が、ちょっと懐かしくも感じます。どうも今の渋谷は・・・と思ってしまうのは、私が年を取ったからですね。
東横劇場も「東横落語会」のポスターが出ていましたが、さよなら公演では小朝、談志、円楽、志ん朝、小さんと団体を越えたオールスター勢ぞろいだったようですね。
エンタテイメントについては「Bunkamura」が後年誕生し、ホールやミュージアムに足を何度か運んでいます。コロナ前でしたが、ジプシー・キングスの公演がオーチャードホールだったように記憶しています。さまざまな演目のポスターが並び、東京のさらに先端たらんと、とんがったことを発信し続けていることが分かります。今は休館中の施設もあると聞きますが、美術展の帰りに家人と二人でお茶したこともありましたし、以前ここのお洒落な書店でパスタのレシピ集を買って今でも愛用しています。
東急と言えばプロ野球にも関わっていた時期もあり、扱いは小さいですが駒沢球場の写真もあります。今の北海道日本ハムファイターズのご先祖様だったフライヤーズにも東急は関わっていました。以前、職場で一緒だった方が幼少期に駒沢球場の近くに住んでいて「あのあたりは暗くて風紀もあまりよくなく、子供だけでは球場に遊びに行けないような感じだった」と語っていました。あの頃の職業野球(特にパ・リーグ)は今ほど明るくなく、健全とは言い難いところもあったのでしょう。球場完成は昭和28年、ナイター照明が整ったのは昭和30年で、対トンボユニオンズ戦の写真がありました。ユニオンズは短命の消滅球団でした。
スポーツでは他にも田園コロシアム(懐かしい!)の写真もあります。テニスだけでなく、格闘技にコンサートと屋外のイベント会場というイメージでした。
また、東急の文化事業として五島美術館からも出展がありました。創業者の五島慶太は美術品の蒐集もしており、当時の財界人らしく茶道の器などもあるほか、書や棟方志功の作品が紹介されています。五島の遺志を受けて美術館として公開されることになりますが、現代の作家の作品も多く収蔵しています。前述の岡本太郎の作品も石原慎太郎蔵を経て寄贈されたというものがありました。
と、長々書いてまいりましたが、鉄道・バス、沿線開発、文化事業とそれぞれのテーマで分けてもいいくらいの内容でした。電車の形を模した箱に入った羊羹をお土産に、帰宅いたしました。東急の100年史も(大著でお値段もしますが)限定販売されています。

左がつり革型のキーホルダー。昔は「東横お好み食堂」の広告の入ったつり革でしたね。羊羹の箱は食べ終わったら豚児の玩具です。形式によって味も違いますが、美味しかったです。

図録も史料価値いっぱいです。