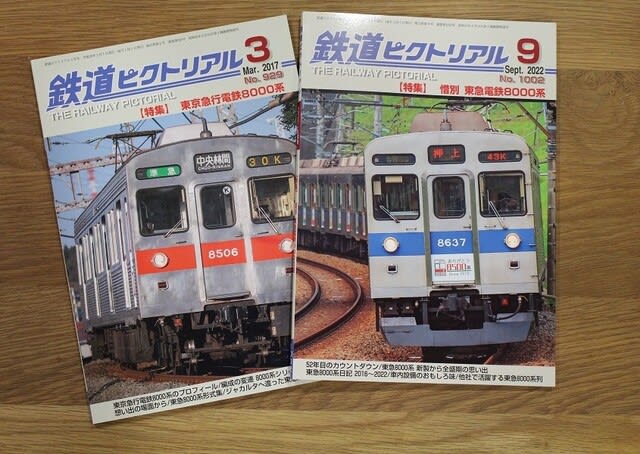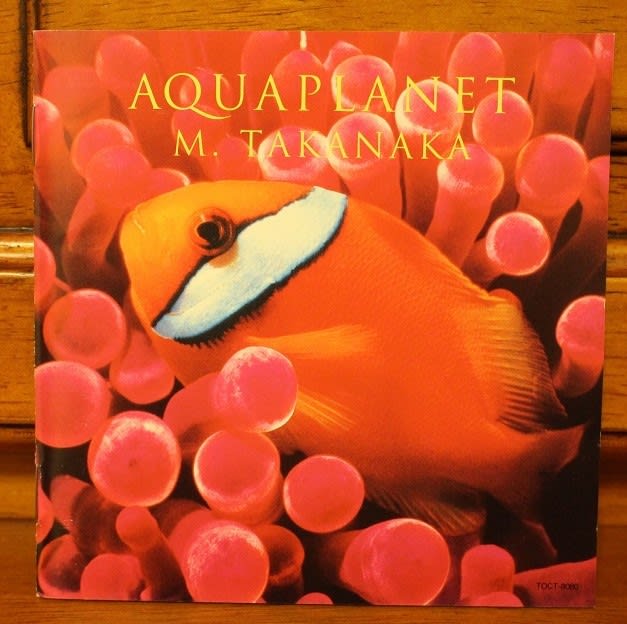落語家として長年活躍され、テレビでもおなじみだった三遊亭金翁師匠が亡くなりました。私などは三遊亭金馬という名前の方がなじみがありますし、私よりもっともっと上の世代ですと、小金馬の時代から知っているよ、となりましょう。その三遊亭小金馬時代には、テレビ草創期の人気番組「お笑い三人組」で知られ・・・というのは新聞等でも書かれているところですが、もう一つモデラーにとっては伝説的な番組に出演されていました。
その番組は「陸と海と空」といい、フジテレビで日曜の朝10:00~10:30に放送され、スポンサーはプラモデルメーカーのマルサンでした。昭和34年6月から2年間も放送され、その司会が三遊亭小金馬でした。もともと模型が好きだったということで白羽の矢が立ったようですが、当時の人気落語家でありタレントを起用していたというのも番組スポンサーのマルサンの力の入れようが分かります。番組の内容はそれぞれの放送日にゆかりのあるゲストをスタジオに迎え、番組のタイトル通り自動車や船舶、航空機の話題などを放送していたようです。この番組の効果もあって、マルサンのプラモデルは放送開始後から数か月経った秋頃から爆発的に売れたと伝えられています。
日本初の国産プラモデルは何か、というのは諸説あるようですが、マルサンのノーチラス号がその一つであり、現在も童友社から再販されていることは多くの方がご存じでしょう。しかし、プラモデルについては当初、問屋筋の評判も芳しくなかったといいます。それでも当時のマルサンの社長は「これはきっと売れる」と信じて希望小売価格の設定など、当時としては強気の商売をしておりました。それでもなかなか売り上げが伸びない中で、テレビと言う当時の新しいメディアでプラモデルを知ってもらう、というある意味「賭け」に出たわけです。フジテレビもまだ開局して日が浅く(開局は昭和34年3月)、新しいメディアに子供たちの新しい娯楽がマッチしたのかもしれません。こうして、マルサンとプラモデルの名前は全国に知れ渡っていくことになりました。
番組は2年で終了し、マルサンというメーカーも消滅しましたが、司会の小金馬は金馬を襲名して以降も模型好きの著名人として知られ、タミヤニュースの「模型ファンを訪ねて」にも登場しています。
私にとってはマルサンという名前は生まれる前の話でしかなく、マルサンのプラモデルについても中古屋さんのガラスケースに収まっているのを見る程度ではありますが、マルサンから他メーカーに金型が渡った製品はあちこちで見かけましたし、私自身が組んだものもあります。それが1/50のF-86Dでした。これは幾度か再販され、私が手にしたのは1980年代前半、中学生の頃「アルカンシエル」のブランドで発売されたものでした。今でいう「情報量の多いキット」といったところで、オール可動でノーズコーンを外せば当然レーダーが顔をのぞかせ、前後に分かれる胴体にはエンジンも入っていて、パイロットに整備士のフィギュアもあります。固定武装のロケット弾とランチャーももちろん入っています。中学生の工作能力ですから、大したことはできませんし、可動部分の多いキットの悪いところであちこちガタガタになってしまうおそれもあり、そこは適宜妥協しながら作った記憶があります。
昭和から令和まで活躍された人気落語家の話から、飛行機のプラモデルの話で着地、いや着陸いたしました。なお、本稿の執筆にあたっては、モデルアート社刊「モデルス プラスチック'60」(平野克己 編著)、「タミヤニュースの世界」(田宮模型編 文春ネスコ発行)を参考にしました。特に前者の「マルサン物語 昔マルサンと云うメーカーがあった」では、平野克己氏がマルサンの石田實・元社長をはじめ関係者への取材を通して、プラモデル誕生から「陸と海と空」、そしてマルサンの最後に至るまでを詳しく書いています。
その番組は「陸と海と空」といい、フジテレビで日曜の朝10:00~10:30に放送され、スポンサーはプラモデルメーカーのマルサンでした。昭和34年6月から2年間も放送され、その司会が三遊亭小金馬でした。もともと模型が好きだったということで白羽の矢が立ったようですが、当時の人気落語家でありタレントを起用していたというのも番組スポンサーのマルサンの力の入れようが分かります。番組の内容はそれぞれの放送日にゆかりのあるゲストをスタジオに迎え、番組のタイトル通り自動車や船舶、航空機の話題などを放送していたようです。この番組の効果もあって、マルサンのプラモデルは放送開始後から数か月経った秋頃から爆発的に売れたと伝えられています。
日本初の国産プラモデルは何か、というのは諸説あるようですが、マルサンのノーチラス号がその一つであり、現在も童友社から再販されていることは多くの方がご存じでしょう。しかし、プラモデルについては当初、問屋筋の評判も芳しくなかったといいます。それでも当時のマルサンの社長は「これはきっと売れる」と信じて希望小売価格の設定など、当時としては強気の商売をしておりました。それでもなかなか売り上げが伸びない中で、テレビと言う当時の新しいメディアでプラモデルを知ってもらう、というある意味「賭け」に出たわけです。フジテレビもまだ開局して日が浅く(開局は昭和34年3月)、新しいメディアに子供たちの新しい娯楽がマッチしたのかもしれません。こうして、マルサンとプラモデルの名前は全国に知れ渡っていくことになりました。
番組は2年で終了し、マルサンというメーカーも消滅しましたが、司会の小金馬は金馬を襲名して以降も模型好きの著名人として知られ、タミヤニュースの「模型ファンを訪ねて」にも登場しています。
私にとってはマルサンという名前は生まれる前の話でしかなく、マルサンのプラモデルについても中古屋さんのガラスケースに収まっているのを見る程度ではありますが、マルサンから他メーカーに金型が渡った製品はあちこちで見かけましたし、私自身が組んだものもあります。それが1/50のF-86Dでした。これは幾度か再販され、私が手にしたのは1980年代前半、中学生の頃「アルカンシエル」のブランドで発売されたものでした。今でいう「情報量の多いキット」といったところで、オール可動でノーズコーンを外せば当然レーダーが顔をのぞかせ、前後に分かれる胴体にはエンジンも入っていて、パイロットに整備士のフィギュアもあります。固定武装のロケット弾とランチャーももちろん入っています。中学生の工作能力ですから、大したことはできませんし、可動部分の多いキットの悪いところであちこちガタガタになってしまうおそれもあり、そこは適宜妥協しながら作った記憶があります。
昭和から令和まで活躍された人気落語家の話から、飛行機のプラモデルの話で着地、いや着陸いたしました。なお、本稿の執筆にあたっては、モデルアート社刊「モデルス プラスチック'60」(平野克己 編著)、「タミヤニュースの世界」(田宮模型編 文春ネスコ発行)を参考にしました。特に前者の「マルサン物語 昔マルサンと云うメーカーがあった」では、平野克己氏がマルサンの石田實・元社長をはじめ関係者への取材を通して、プラモデル誕生から「陸と海と空」、そしてマルサンの最後に至るまでを詳しく書いています。