『表現者』第47号(既発行)に、当ブログの寄稿者・小浜逸郎氏の、座談会での発言と宮里立士氏の文章が、それぞれ載っています。小浜氏は、『座談会・「戦後レジームとしての知識人」を排す』(P106~135)に登場します。座談会のほかのメンバーは、中島岳志氏、西部邁氏、富岡幸一郎氏です。宮里氏は、『いまだ「敗戦国」にして「被占領国」のニッポン』(P16~17)を書いています。今号の『表現者』は、「取り戻すべき日本とは何か」というテーマにちなんだ興味深い文章が(もちろん、お二人の発言・文章をふくめて)目白押しです。ぜひ、ご覧ください。
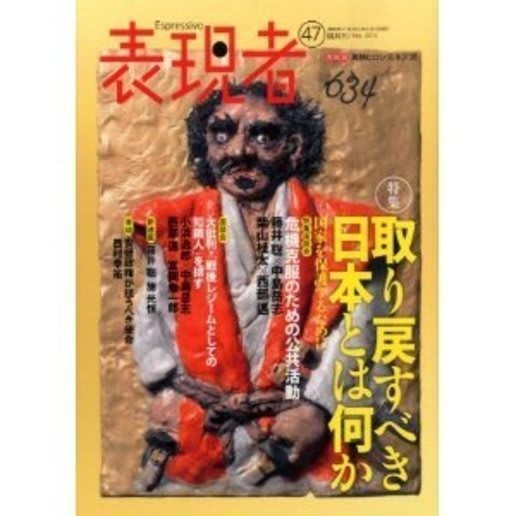
また、月刊誌『正論』四月号(三月一日発行)に、拙文が載ります。本誌の「誌上討論・大阪・桜宮高校入試中止問題 橋下裁定は「英断」か「暴挙」か」(P218~229)という企画のなかで、私は「暴挙」の立場で論陣を張っています。対論の相手は、教育評論家・東京都職員の森口朗(もりぐち・あきら)氏です。ご興味がおありの方は、ぜひご覧ください。

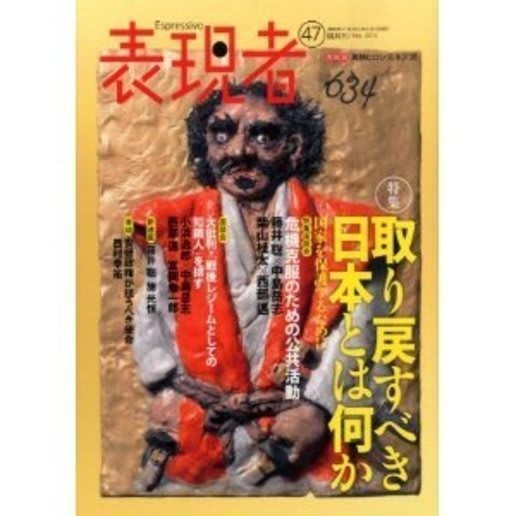
また、月刊誌『正論』四月号(三月一日発行)に、拙文が載ります。本誌の「誌上討論・大阪・桜宮高校入試中止問題 橋下裁定は「英断」か「暴挙」か」(P218~229)という企画のなかで、私は「暴挙」の立場で論陣を張っています。対論の相手は、教育評論家・東京都職員の森口朗(もりぐち・あきら)氏です。ご興味がおありの方は、ぜひご覧ください。




















