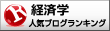小浜逸郎氏「タチの悪い言論とは何か――内田樹批判」についてのコメントと応答
*Commented by soichi2011 さん
以下は拙著『軟弱者の戦争論』で述べたことの要約ですが、今回の記事に関連しそうなので述べます。
対象にしたのは内田樹氏の処女出版『ためらいの倫理学』冒頭に収められた二つの短文「古だぬきは戦争について語らない」と「アメリカという病」です。ここで氏は、コソボ紛争時にナトーによるユーゴ空爆を支持したスーザン・ソンタグを批判しています。
内田氏の大前提は、「泥棒にも三分の理。ましてや戦争だ。ミロシェビッチにだってNATOにだってコソボ解放軍にだってギリシャにだって、それぞれ言い分はあるだろう」から、戦争当事国のうち、どちらかが正義でどちらかが悪だなどと言うことはできない、というものです。そこからして、戦争に対してはシニカルな態度ではなく、決然とした立場をとることを知識人に求めるソンタグを、「とてもアメリカ的」だと言います。自らの正義を疑わず、武力を使ってでも他国にも押しつけようとするところが。自分は腰が引けていて、それは「日本の腰の引け方と同型」なのかも知れないが、悲惨な戦禍を引き起こすのはたいていは「決然」としているほうなのだ、と。
問題はもちろんソンタグの支持とか、それ以前に空爆は正しかったか、などではありません。内田氏はそれについては自分は語らない、語りたくもない、と言っているのですから。彼は態度決定を迫るソンタグの押しつけがましさをいやがっている。それはわからなくはないです。しかし、俺はどんな立場も取らない、なんて「主張」したら、それ自体が「立場」になってしまい、しかも立場をとったことに対する責任は頬かむりすることになる。とてもズルいやり方だ。「古だぬき」を自称するからには気づいている、のかなあ?
コソボ紛争については、たいていの日本人は「知らない」ですましていいでしょう。では、内田氏の前提を、日本が当事国だった大東亜戦争に応用するとどうなるか。「あれだけの大戦争で日本だけが悪いなんてことはあるわけない。そんな主張をするヤツは愚かだ」。これだと立派な「立場」だと、少なくともある国からはみなされるでしょう。だからその部分では、口を噤んでいる。局外者の身軽さがある時しかものが言えない。どうしてもそう見えてしまうのは、内田氏個人でも、「同型」とされる日本でも、やっぱり恥ずかしいんじゃないですかねえ。
*Commented by kohamaitsuo さん
soichi2011さんへ。
スパイシーなコメント、ありがとうございます。
貴兄がすでに『軟弱者の戦争論』で内田氏を批判していたことは覚えていましたが、その文脈を忘れていました。今回改めて貴コメントを読み、その鋭い批判に「わが意を得たり」の思いでした。
局外者なら「決然としない」「立場をとらない」という立場が何やら考え深げでかっこよく見えますが、おひざ元の問題になったら立場を取らざるを得ないことがあるわけですよね。内田氏の好きな「おフランス」でも、サルトルやマルローら知識人は、間違う可能性を承知のうえで最終的にある立場をとっています。それが正しかったのかどうかは、ここでは問いません。
内田氏のような言説が許されるのは、日本の知識人がオキラクな「立場」にいられるからこそです。そのぶん、政治家が時々業を煮やして本音を吐き、そのたびに「失言」として葬られてきました。本当は、知識人こそが内外の批判を恐れず、それらの本音が正しいと思われる場合には、その根拠を情理を尽くして説き、サポートしなくてはならないはずです。もちろんそれをしている人も少数ながらいますけれど。
やれフーコーだ、やれレヴィナスだと、西洋知識人の輸入業で飯を食ってきた多くの戦後日本知識人は、「局外者の身軽さ」が染みついているせいか、わが同朋の問題に触れるときになると、とたんにその幼稚さと無責任ぶりと逃避癖をさらします。内田氏にぜひ大東亜戦争について「日本だけが悪いなんて決めつけられるはずがない」と言わせてみたいものです。そうでないかぎり、彼もまた、あの戦後日本知識人たちの悪弊をそのまま踏襲するひとりとして位置づけられることになるでしょう。「内田樹よ、お前もか!」
*Commented by soichi2011 さん
以下は拙著『軟弱者の戦争論』で述べたことの要約ですが、今回の記事に関連しそうなので述べます。
対象にしたのは内田樹氏の処女出版『ためらいの倫理学』冒頭に収められた二つの短文「古だぬきは戦争について語らない」と「アメリカという病」です。ここで氏は、コソボ紛争時にナトーによるユーゴ空爆を支持したスーザン・ソンタグを批判しています。
内田氏の大前提は、「泥棒にも三分の理。ましてや戦争だ。ミロシェビッチにだってNATOにだってコソボ解放軍にだってギリシャにだって、それぞれ言い分はあるだろう」から、戦争当事国のうち、どちらかが正義でどちらかが悪だなどと言うことはできない、というものです。そこからして、戦争に対してはシニカルな態度ではなく、決然とした立場をとることを知識人に求めるソンタグを、「とてもアメリカ的」だと言います。自らの正義を疑わず、武力を使ってでも他国にも押しつけようとするところが。自分は腰が引けていて、それは「日本の腰の引け方と同型」なのかも知れないが、悲惨な戦禍を引き起こすのはたいていは「決然」としているほうなのだ、と。
問題はもちろんソンタグの支持とか、それ以前に空爆は正しかったか、などではありません。内田氏はそれについては自分は語らない、語りたくもない、と言っているのですから。彼は態度決定を迫るソンタグの押しつけがましさをいやがっている。それはわからなくはないです。しかし、俺はどんな立場も取らない、なんて「主張」したら、それ自体が「立場」になってしまい、しかも立場をとったことに対する責任は頬かむりすることになる。とてもズルいやり方だ。「古だぬき」を自称するからには気づいている、のかなあ?
コソボ紛争については、たいていの日本人は「知らない」ですましていいでしょう。では、内田氏の前提を、日本が当事国だった大東亜戦争に応用するとどうなるか。「あれだけの大戦争で日本だけが悪いなんてことはあるわけない。そんな主張をするヤツは愚かだ」。これだと立派な「立場」だと、少なくともある国からはみなされるでしょう。だからその部分では、口を噤んでいる。局外者の身軽さがある時しかものが言えない。どうしてもそう見えてしまうのは、内田氏個人でも、「同型」とされる日本でも、やっぱり恥ずかしいんじゃないですかねえ。
*Commented by kohamaitsuo さん
soichi2011さんへ。
スパイシーなコメント、ありがとうございます。
貴兄がすでに『軟弱者の戦争論』で内田氏を批判していたことは覚えていましたが、その文脈を忘れていました。今回改めて貴コメントを読み、その鋭い批判に「わが意を得たり」の思いでした。
局外者なら「決然としない」「立場をとらない」という立場が何やら考え深げでかっこよく見えますが、おひざ元の問題になったら立場を取らざるを得ないことがあるわけですよね。内田氏の好きな「おフランス」でも、サルトルやマルローら知識人は、間違う可能性を承知のうえで最終的にある立場をとっています。それが正しかったのかどうかは、ここでは問いません。
内田氏のような言説が許されるのは、日本の知識人がオキラクな「立場」にいられるからこそです。そのぶん、政治家が時々業を煮やして本音を吐き、そのたびに「失言」として葬られてきました。本当は、知識人こそが内外の批判を恐れず、それらの本音が正しいと思われる場合には、その根拠を情理を尽くして説き、サポートしなくてはならないはずです。もちろんそれをしている人も少数ながらいますけれど。
やれフーコーだ、やれレヴィナスだと、西洋知識人の輸入業で飯を食ってきた多くの戦後日本知識人は、「局外者の身軽さ」が染みついているせいか、わが同朋の問題に触れるときになると、とたんにその幼稚さと無責任ぶりと逃避癖をさらします。内田氏にぜひ大東亜戦争について「日本だけが悪いなんて決めつけられるはずがない」と言わせてみたいものです。そうでないかぎり、彼もまた、あの戦後日本知識人たちの悪弊をそのまま踏襲するひとりとして位置づけられることになるでしょう。「内田樹よ、お前もか!」