



 走行は危険をみなされ、レッカー車の手配。いつも車検をお願いしている修理工場に運んでもらいました。
走行は危険をみなされ、レッカー車の手配。いつも車検をお願いしている修理工場に運んでもらいました。 おまけに老眼鏡も忘れ
おまけに老眼鏡も忘れ


 仕方がありません。
仕方がありません。





 走行は危険をみなされ、レッカー車の手配。いつも車検をお願いしている修理工場に運んでもらいました。
走行は危険をみなされ、レッカー車の手配。いつも車検をお願いしている修理工場に運んでもらいました。 おまけに老眼鏡も忘れ
おまけに老眼鏡も忘れ


 仕方がありません。
仕方がありません。

なかなか記事には出来ていませんが・・・
認知症関連のセミナーなど視聴しています。
認知症改善・予防として、まずは水分補給、白い砂糖はとらないなど、予防医学、栄養学、心の問題、環境問題・・・
いろんな角度から改善の可能性を追求していて、どれもこれも興味深いことばかり。
元々、興味ある分野なので、学ぶことが楽しいです。
認知症改善で一番、難しいことは「本人が治そうという気がない」ということだそうです。
私の母もそうでしたが、病院に連れて行こうにも、「私はボケてなんかいない!」と怒ってしまい、連れて行くのは困難でした。
母を病院に連れて行けたのは、どこに向かおうとしているのか、ここは何処なのか認識できなくなってからのことでした。
診察室で、母の症状を説明すると「よく今まで頑張ってこられましたね」と労ってくださり、思わず涙が溢れました。
次に先生の口から語られたことは、「薬はもう時期を逃している。残念ながら、もう手立てがない」ということでした。
先生がもうそれ以上、伝えることがないと知った時、愕然としました。
もう少し早く連れてこれていたら・・・でも、無理だった・・・虚しさに襲われました。
(早く連れていったところで、認知症は治らないとされ、改善策は確率されてはいなかったのですが)
母は、初期段階で、自分が忘れっぽくなってしまったことを悩み、落ち込むことが多かったですが(この時点では、うつ病と診断されることもあるようです)、次第に認知症が進行していくと、もう自分が認知症であるということも認識できなくなりました。
自分が忘れてしまうといういうことも忘れてしまうのですね。
そうなると、自ら受診を希望したり、薬やサプリを飲もうとするようなこともまず期待できないし、家族が何か試したくても、何かさせられることに敏感で怒りっぽくもなるので、拒否されることも多いです。
それこそ、「本人が治そうとする気がない」という状態になります。
自分が認知症であることもわからなくなってしまうので、当然なのですが。
認知症の患者さんは、ほぼ100%、水分不足だそうです。
水分をとるだけで、症状が改善される方もいるようです。
「腸は第二の脳」と言われているように、腸内環境が悪化すると脳にも影響がでることがわかっています。
食品(小麦粉や白砂糖など)、添加物、農薬などは、腸に負担がかかるので、なるべく避けたほうがいいです。
朝、パン食だったのをご飯にしただけで改善した方もいるようです。(グルテンにより腸壁に小さな無数の穴が出て、そこから細菌、毒素など有害物質が体内に入り込んで(リーキーガット症候群)脳にも炎症がおこるとされています)
パンを食べていると認知症になるというわけではなく、認知症になった方は、パン、甘い物が好きな傾向があるということです。
母もそうでした。
もうひとつ改善が難しいケースというのは・・・
「治してもらえますか?」というご家族の患者さんだそうです。
本人に治す気がないのですから、改善を目指すのであれば、ご家族の協力が不可欠です。
「治すためにはどうしたらいいですか?」という姿勢でなければならないと思います。
この話を聞いて「不登校解決」と一緒だなと思いました。
「親が諦めない限りは大丈夫」
言い換えれば「親が諦めたら終わり」
私はずっとこの言葉を支えにしていました。
子どもがどんな状態であっても、どんな環境であっても、
「もう無理」って思ってしまったら、そこで終わり・・・だと。
何か改善策はあると信じたいと思っていました。
それは、ただただ待つことではなく、子どもをなんとかしようとすることではなく、
変われるとしたら、まずは親なので。
子どもとの接し方や、考え方をどう変化させていくのか・・・
地道な作業ですが、少しずつ子どもにも変化が出てくれればと思ってきました。
今、けん太は、毎日、職場に向かっていますが、
今後もずっという保証はどこにもありません。
もしかしたら、また止まってしまうこともあるかもしれません。
でも、その言葉はずっと忘れずにいたいと思います。





 )なんか堂々としていて、
)なんか堂々としていて、









 、頼まれていないけど、モコモコの毛布を追加し、こっそり設定温度を1℃下げておきましたが、まだ、気づいていないようです
、頼まれていないけど、モコモコの毛布を追加し、こっそり設定温度を1℃下げておきましたが、まだ、気づいていないようです


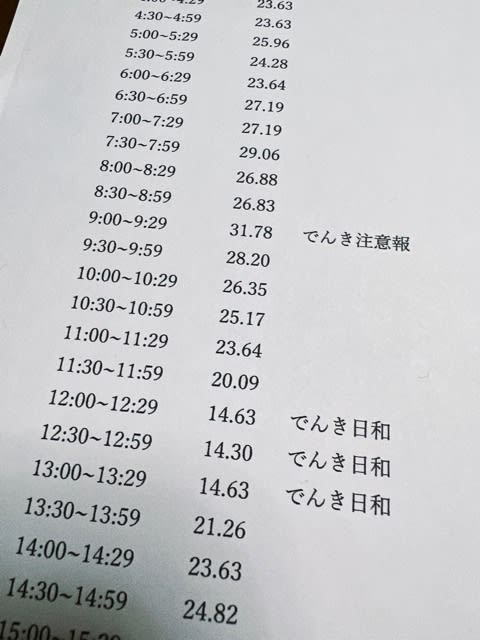

 )
)











 ちっちゃいワンちゃんは人懐こいね。
ちっちゃいワンちゃんは人懐こいね。


 )
)


