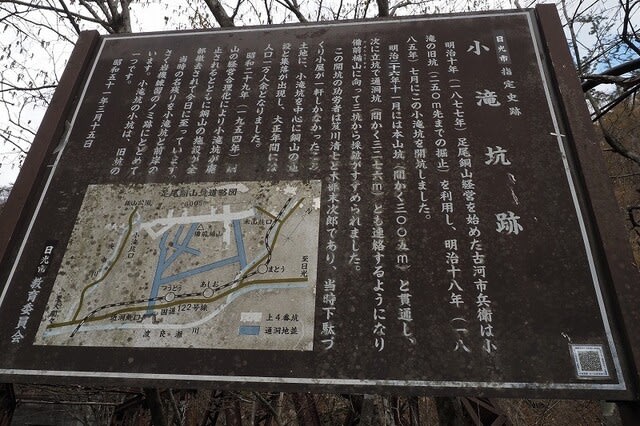春深き足尾の町を徘徊る 笑子
はるふかきあしおのまちをたもとほる
小滝坑 ここへ来たのは何年ぶりだろう
最盛期には1万人が暮らした地
渡良瀬川の支流、庚申(こうしん)川に沿い
かつての小滝坑を中心とした鉱山集落
昭和29年小滝坑閉鎖、社宅撤去となった
下の写真は なんだと思いますか??
坑夫のお風呂跡なんですね
初めてここへ来たときに とても切ない気持ちになったのですよね
過酷な労働を強いられていた人たちが1日のノルマから
解き放たれ 体を洗っていたところ・・・
この大きさでは すし詰め状態だったか
それでも、この入浴のひとときこそ
坑夫らの安らぎのひとときだったにちがいありません
上の写真は火薬庫跡
この場所の隅のほうに・・・↓
これはドリルか何かでここの鉱物の成分を調べたのでしょうか?
私が最初訪れたころは 社宅の名残もあったのですが
今は当時を偲ばせる遺構はほんの少しになっています
私は「足尾」という町に
言葉ではうまく表現できないけど
なぜか惹かれるのですよね
足尾に人が住み始めたのは石器時代とのこと
畑地からやじりや石器縄文式土器などが発見されてるそう
奈良・平安時代にはすでに集落ができ足尾開発が進みます
その後は 室町時代から武士が移住して開発するとともに
農業集落を支配しました
慶長15年 銅の鉱脈が2人の農夫によって発見され
以来町は銅山により繁栄します
銅山は幕府の直轄下におかれ多くの労働者が採掘と製錬を行い
江戸の中期には足尾千軒と呼ばれるほどの繁栄を示しました
その後の衰退と鉱毒事件
時代に翻弄された町なのです
明日は精錬所跡へご案内します(^_-)-☆