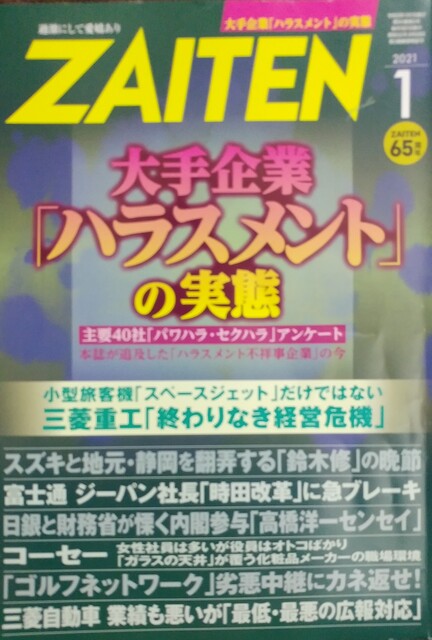「働かない正社員を解雇できる社会にしたい」。そんな刺激的なタイトルのインタビュー記事がこの春、プレジデントオンラインに掲載されて論議を呼んだ。記事の中で、オリックス元会長の宮内義彦氏は、雇用が安定している正規社員と不安定な非正規社員の格差にふれながら、「きちんと働かない人の雇用を打ち切れるように、解雇条件をはっきりさせることが必要でしょう」と述べたのだ。
このような意見に対しては、企業の利益を増やすだけで労働者は幸せにならないという批判が、労働者側に立つ弁護士から出ている。では、企業側の立場で労働法務を扱う弁護士はどう考えているのだろうか。「現在の労働法制には問題がある」という倉重公太朗弁護士に話を聞いた。(取材・構成/関田真也)
●労働法の保護を受けるのは「一部の大企業」の正社員だけ
――現在の労働法は、どのような点に問題があるとお考えですか?
「解雇権濫用法理」によって、解雇が認められる条件が厳しくなりすぎ、労働法のひずみを生み出しているという問題があると思います。普通解雇の場合で考えてみましょう。
与えられた仕事をさぼるといった「勤務態度不良型」であれば、仕事をしていない事実を示せばいいので、比較的立証は容易です。しかし、そういった例は多くありません。
一般的に問題となるのは「能力不足・仕事のミスマッチ型」の場合です。本人としては仕事をしているつもりでも、その成果が伴わないことの立証することは難しいです。なぜなら、「仕事について繰り返しミスをし、何度注意しても改善しない」というプロセスのすべてについて、会社側が立証する必要があるためです。
そして、仕事の出来が悪い人には与えられる仕事がなくなって「社内失業」となる場合もあります。こうした人はそもそも仕事をしないので、ミスをすることもありえない。ですから、絶対に解雇できないという状況が生まれるわけです。仕事を与えればミスをするので重要な仕事をさせられないが、仕事をさせないと解雇理由がなくなってしまうという点で、企業はジレンマに陥ります。
――「解雇権濫用法理」は労働者を保護するためのものですが、これが現実にどのような悪影響を及ぼすのでしょうか?
労働法の保護といっても、実際に恩恵を受けるのは一部の大企業に属する正社員に限られるということになり、極めて公平性を欠く状況が発生するのです。
「解雇権濫用法理」は、2つのダブルスタンダードを発生させます。1つは、正規・非正規の格差、2つ目は、一部の大企業とその他の企業における遵法状況の格差です。
まず、1つ目ですが、賃金原資が限られている以上、企業としては正社員の採用を抑制する行動に出るのは自然な流れです。その結果、非正規・派遣が増加することになります。そして、労働法の保護を受けるのは、基本的に正社員に限られますから、正規と非正規との間で大きな格差が生じることになります。
特に、新卒採用時点で非正規になってしまうと、その後のスキルアップも望めず、生涯賃金に大きな差が出ます。私自身、大学卒業時は就職氷河期だったので、一度「正社員ルート」を外れると復帰困難な現状には違和感を覚えます。
今、厚生労働省が行っている非正期対策が功を奏していないのは、この根本に目を向けていないからです。「全ての労働者を正社員にする」ことができれば理想的なのは間違いありませんが、これができないのであれば、正規・非正規という身分制のような枠組みで考えるのが本当に正しいのか、改めて考えるべきでしょう。
そして2点目ですが、正社員に強い保護が与えられているといっても、これだけ厳しい規制があると、すべての企業が現実に法を守ることは難しくなります。その結果どうなるかというと、一部の大企業は法律を遵守するが、その他の中小零細企業においては法律を遵守している例が少ないというダブルスタンダードが発生することになります。
「働かないオジサン」という言葉も話題になっていましたが、大企業で、かつ、コンプライアンス意識が高いところは、「窓際」と言われて社内で仕事がない従業員でも、正社員という立場だけで給料が支払われ続け、手厚い保護を受けます。極端な例でいえば、仕事がないことに危機感を感じるどころか、給料をもらえるのをいいことに、一日中ネットサーフィンやソリティアをして過ごす人もいるのです。
一方、残業代や解雇などの問題を含めて、中小企業では、労働法が厳密に守られることはほとんどないといえる状況であることは、周知のことだと思います。これは、ブラック企業として昨今批判を浴びている企業に限られる話ではありません。法律の規制が現実にマッチしていないからこそ、法律の保護を受ける労働者が一部に限られてしまっているのです。
●「転職が当たり前」の世の中にしていくべき
――問題点を解決する具体的方策としては、どのような方法が考えられるでしょうか?
解雇の問題について「金銭解決制度」を確立し、解雇規制を緩和するべきだと考えます。
今の解雇紛争は、「復職」することを前提として労働審判や交渉を行います。しかし、そのほとんどは、解決金として「給料の○ヶ月分」といった金銭を手にして和解することで退職しています。
紛争になる時点で関係が壊れてしまっていることもあり、労働者も使用者側も、共に復職は考えていない事が多いです。それにもかかわらず、労働者は戻るつもりもない企業に対して「復職する
一日中ソリティアをして過ごす「働かないオジサン」をクビにできない社会でいいのか?
このような意見に対しては、企業の利益を増やすだけで労働者は幸せにならないという批判が、労働者側に立つ弁護士から出ている。では、企業側の立場で労働法務を扱う弁護士はどう考えているのだろうか。「現在の労働法制には問題がある」という倉重公太朗弁護士に話を聞いた。(取材・構成/関田真也)
●労働法の保護を受けるのは「一部の大企業」の正社員だけ
――現在の労働法は、どのような点に問題があるとお考えですか?
「解雇権濫用法理」によって、解雇が認められる条件が厳しくなりすぎ、労働法のひずみを生み出しているという問題があると思います。普通解雇の場合で考えてみましょう。
与えられた仕事をさぼるといった「勤務態度不良型」であれば、仕事をしていない事実を示せばいいので、比較的立証は容易です。しかし、そういった例は多くありません。
一般的に問題となるのは「能力不足・仕事のミスマッチ型」の場合です。本人としては仕事をしているつもりでも、その成果が伴わないことの立証することは難しいです。なぜなら、「仕事について繰り返しミスをし、何度注意しても改善しない」というプロセスのすべてについて、会社側が立証する必要があるためです。
そして、仕事の出来が悪い人には与えられる仕事がなくなって「社内失業」となる場合もあります。こうした人はそもそも仕事をしないので、ミスをすることもありえない。ですから、絶対に解雇できないという状況が生まれるわけです。仕事を与えればミスをするので重要な仕事をさせられないが、仕事をさせないと解雇理由がなくなってしまうという点で、企業はジレンマに陥ります。
――「解雇権濫用法理」は労働者を保護するためのものですが、これが現実にどのような悪影響を及ぼすのでしょうか?
労働法の保護といっても、実際に恩恵を受けるのは一部の大企業に属する正社員に限られるということになり、極めて公平性を欠く状況が発生するのです。
「解雇権濫用法理」は、2つのダブルスタンダードを発生させます。1つは、正規・非正規の格差、2つ目は、一部の大企業とその他の企業における遵法状況の格差です。
まず、1つ目ですが、賃金原資が限られている以上、企業としては正社員の採用を抑制する行動に出るのは自然な流れです。その結果、非正規・派遣が増加することになります。そして、労働法の保護を受けるのは、基本的に正社員に限られますから、正規と非正規との間で大きな格差が生じることになります。
特に、新卒採用時点で非正規になってしまうと、その後のスキルアップも望めず、生涯賃金に大きな差が出ます。私自身、大学卒業時は就職氷河期だったので、一度「正社員ルート」を外れると復帰困難な現状には違和感を覚えます。
今、厚生労働省が行っている非正期対策が功を奏していないのは、この根本に目を向けていないからです。「全ての労働者を正社員にする」ことができれば理想的なのは間違いありませんが、これができないのであれば、正規・非正規という身分制のような枠組みで考えるのが本当に正しいのか、改めて考えるべきでしょう。
そして2点目ですが、正社員に強い保護が与えられているといっても、これだけ厳しい規制があると、すべての企業が現実に法を守ることは難しくなります。その結果どうなるかというと、一部の大企業は法律を遵守するが、その他の中小零細企業においては法律を遵守している例が少ないというダブルスタンダードが発生することになります。
「働かないオジサン」という言葉も話題になっていましたが、大企業で、かつ、コンプライアンス意識が高いところは、「窓際」と言われて社内で仕事がない従業員でも、正社員という立場だけで給料が支払われ続け、手厚い保護を受けます。極端な例でいえば、仕事がないことに危機感を感じるどころか、給料をもらえるのをいいことに、一日中ネットサーフィンやソリティアをして過ごす人もいるのです。
一方、残業代や解雇などの問題を含めて、中小企業では、労働法が厳密に守られることはほとんどないといえる状況であることは、周知のことだと思います。これは、ブラック企業として昨今批判を浴びている企業に限られる話ではありません。法律の規制が現実にマッチしていないからこそ、法律の保護を受ける労働者が一部に限られてしまっているのです。
●「転職が当たり前」の世の中にしていくべき
――問題点を解決する具体的方策としては、どのような方法が考えられるでしょうか?
解雇の問題について「金銭解決制度」を確立し、解雇規制を緩和するべきだと考えます。
今の解雇紛争は、「復職」することを前提として労働審判や交渉を行います。しかし、そのほとんどは、解決金として「給料の○ヶ月分」といった金銭を手にして和解することで退職しています。
紛争になる時点で関係が壊れてしまっていることもあり、労働者も使用者側も、共に復職は考えていない事が多いです。それにもかかわらず、労働者は戻るつもりもない企業に対して「復職する
一日中ソリティアをして過ごす「働かないオジサン」をクビにできない社会でいいのか?