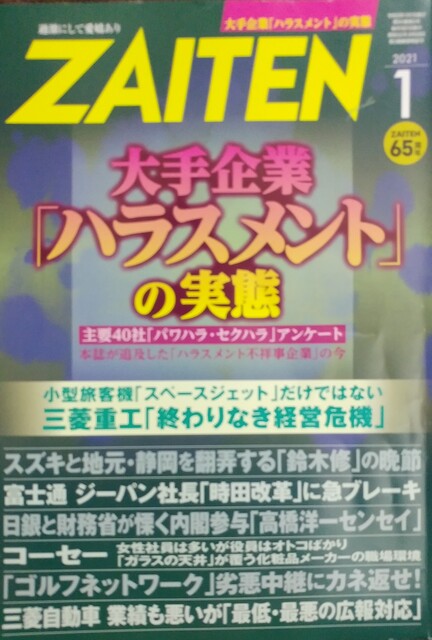先日、海外経済誌主催のコンファレンスにパネリストとして参加する僥倖に恵まれまして、いそいそと馳せ参じて持論を展開して参りました。消費税増税に対して海外の反応がネガティブなのはある程度予想できましたが、今回のセッションでワタクシ自身がかなり意外感を持って受け止めたのは、日本の非正規労働者を含めた賃金格差の問題に海外の分析が非常にニュートラルでなおかつ踏み込んでいることでした。
端的に言えば、低賃金の非正規雇用の増加が、国内消費の低迷を招き、それが国内需要を圧迫している、というもの。この点については単なるワタクシの印象論と受け止められる恐れがありますが、昨今発表されたILO(国際労働機関)の「世界の雇用及び社会の見通し 2015 年版」の指摘とも重なっています。こうしたセッションで日本の雇用問題が取り上げられるのはILOの報告書の内容がかなり海外では浸透している証でもあるでしょう。
失われた日本の数十年は国内の賃金の低迷が主要因の1つであり、ここを解消すれば逆回転が発生して健全なる実体経済の活性化が期待できる。そういう意味では賃金が低迷している状況下でさらに実質的に国民から所得を奪ってしまう消費税の増税などはもっての外。実際に税率を引き下げてきたカナダを模倣して、消費税は増税ではなく引下げ(最終的には廃止へ)、賃金は引き上げへ。それが失われた十数年の処方箋です(勿論、他にも同時進行で手を付けなければならないことはあります)。実体経済が活性化すれば税収も増え財源も賄えます。
日本で消費税とされるこのタイプの税金は海外では付加価値税と呼ばれるのが一般的です。消費税などという奇妙かつ誤解を与えるネーミングは日本だけ。消費税は消費者が負担する税金ではありません。日本の消費税法のどこを見ても消費者に納税義務が発生するなどとした記述はありません。消費税の納税者は内需関連の事業者(ただし、輸出企業の場合、輸出分についての消費税は0%)です。しかも赤字でも黒字でも売り上げがあれば必ず納税しなければならないのが消費税であり、内需事業者にとっては大変過酷な税金です。
5%から8%へ、たかだか3%の増税と侮るなかれ。実際の税負担で考えれば1.6倍の負担増、つまり消費税5%時代に100万円の納税で済んでいたものが、8%では160万円に増えてしまうわけです。売上げが劇的に変わらない中、むしろ増税で売上げが減る中で更なる60万円の捻出は厳しいものです。
というわけで、米財務省などの公文書をみると、付加価値税は実質事業税ではないかとの指摘がされています。法人税もありながら
アベノミクスが目を背ける日本の「賃金格差」 - 岩本沙弓 現場主義の経済学
端的に言えば、低賃金の非正規雇用の増加が、国内消費の低迷を招き、それが国内需要を圧迫している、というもの。この点については単なるワタクシの印象論と受け止められる恐れがありますが、昨今発表されたILO(国際労働機関)の「世界の雇用及び社会の見通し 2015 年版」の指摘とも重なっています。こうしたセッションで日本の雇用問題が取り上げられるのはILOの報告書の内容がかなり海外では浸透している証でもあるでしょう。
失われた日本の数十年は国内の賃金の低迷が主要因の1つであり、ここを解消すれば逆回転が発生して健全なる実体経済の活性化が期待できる。そういう意味では賃金が低迷している状況下でさらに実質的に国民から所得を奪ってしまう消費税の増税などはもっての外。実際に税率を引き下げてきたカナダを模倣して、消費税は増税ではなく引下げ(最終的には廃止へ)、賃金は引き上げへ。それが失われた十数年の処方箋です(勿論、他にも同時進行で手を付けなければならないことはあります)。実体経済が活性化すれば税収も増え財源も賄えます。
日本で消費税とされるこのタイプの税金は海外では付加価値税と呼ばれるのが一般的です。消費税などという奇妙かつ誤解を与えるネーミングは日本だけ。消費税は消費者が負担する税金ではありません。日本の消費税法のどこを見ても消費者に納税義務が発生するなどとした記述はありません。消費税の納税者は内需関連の事業者(ただし、輸出企業の場合、輸出分についての消費税は0%)です。しかも赤字でも黒字でも売り上げがあれば必ず納税しなければならないのが消費税であり、内需事業者にとっては大変過酷な税金です。
5%から8%へ、たかだか3%の増税と侮るなかれ。実際の税負担で考えれば1.6倍の負担増、つまり消費税5%時代に100万円の納税で済んでいたものが、8%では160万円に増えてしまうわけです。売上げが劇的に変わらない中、むしろ増税で売上げが減る中で更なる60万円の捻出は厳しいものです。
というわけで、米財務省などの公文書をみると、付加価値税は実質事業税ではないかとの指摘がされています。法人税もありながら
アベノミクスが目を背ける日本の「賃金格差」 - 岩本沙弓 現場主義の経済学