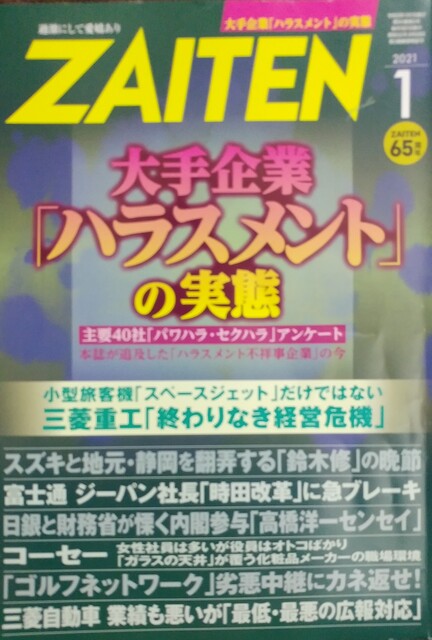伊藤忠 働き方を朝型に 残業削減で早朝手当増額 軽食も無償提供
仕事は深夜よりも早朝に―。伊藤忠商事は2日、残業削減に向け社員の働き方を夜型から朝型に変えるため、深夜の残業を禁止し、早朝の時間外手当を増やす新たな制度を10月から試験的に始めると発表した。
夜の残業は疲れる上、区切りがつきにくく効率が悪い。同社は「業務の効率化や健康管理だけでなく、家庭や子どもを持つ女性も働きやすくなる」と新制度の狙いを話している。
新しい勤務制度の狙いは、勤務時間の午前9時から午後5時15分の間に仕事をできるだけ終わらせ、残業しないようにすること。やむを得ない場合も、翌朝に「残業」するようにする。
早朝に働くメリットを感じられるよう、午前5時から同9時までの時間外手当の割増率を従来の25%から50%に引き上げる。同8時前に仕事を始めた社員には、バナナやヨーグルトなどの軽食を無償で提供する。
一方、午後8時以降の勤務は原則禁止する。午後10時から午前5時の勤務は禁止し、午後10時には完全に消灯する。
対象は管理職を含めた国内の正社員約2600人。来年3月末までの時限的な措置で、残業時間の変化などを検証し、正式に導入するか決める。
仕事は深夜よりも早朝に―。伊藤忠商事は2日、残業削減に向け社員の働き方を夜型から朝型に変えるため、深夜の残業を禁止し、早朝の時間外手当を増やす新たな制度を10月から試験的に始めると発表した。
夜の残業は疲れる上、区切りがつきにくく効率が悪い。同社は「業務の効率化や健康管理だけでなく、家庭や子どもを持つ女性も働きやすくなる」と新制度の狙いを話している。
新しい勤務制度の狙いは、勤務時間の午前9時から午後5時15分の間に仕事をできるだけ終わらせ、残業しないようにすること。やむを得ない場合も、翌朝に「残業」するようにする。
早朝に働くメリットを感じられるよう、午前5時から同9時までの時間外手当の割増率を従来の25%から50%に引き上げる。同8時前に仕事を始めた社員には、バナナやヨーグルトなどの軽食を無償で提供する。
一方、午後8時以降の勤務は原則禁止する。午後10時から午前5時の勤務は禁止し、午後10時には完全に消灯する。
対象は管理職を含めた国内の正社員約2600人。来年3月末までの時限的な措置で、残業時間の変化などを検証し、正式に導入するか決める。