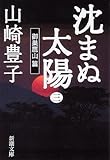昨日、調布の自宅を車で出て、関越道、上越道?、を通り、一般道をひたすら走って、迷いながら、午前8時に出発してから4時間30分かけて、午後12時30分、御巣鷹の尾根への登山口に到着する。明日、月曜日から登山口は冬季閉鎖に入ると看板が出ていた。今回、御巣鷹山に登ろうと思ったのは、自分が50歳になり、今から25年前、起きた日航機JAL123便墜落事故で貴い520人の命が失われ、川上慶子さん始め、4人が救出された御巣鷹山の尾根。「命」「生きている事とは?」「これからの人生」を内観する為。御巣鷹山の事故に関する、遺稿集、御遺族の書かれた本、数々のノンフィクション、そして小説を片っ端から読んだ。その場所に身を起きたかった。
内容(「BOOK」データベースより)
今から二〇年前の一九八五年八月一二日、日航ジャンボ機が群馬県上野村の「御巣鷹の尾根」に激突、炎上し、五二〇名が亡くなる航空史上空前の事故が起こりました。文集『茜雲』は毎年発刊され、今年は、二〇冊目となりました。今回発刊の二〇年目の文集『茜雲』には、高齢化する遺族たちが事故の記憶を次世代に伝えたい、事故を風化させないという遺族の強い思いを詰めました。そして、亡き愛する人への変わることのない想いと遺族一人ひとり違う二〇年間の心の軌跡が記されています。
内容(「MARC」データベースより)
日航ジャンボ機墜落事故から20年。残された家族によるゆるやかな連帯の輪「8・12連絡会」。遺族の思いのたけを綴った文集。亡くした人への変わることのない想いと一人ひとりの20年間の心の軌跡。
出版社/著者からの内容紹介
遺体は何かを語りかけてきた……
520人、全遺体の身元確認までの127日を最前線で捜査にあたった責任者が切々と語る!人間の極限の悲しみの記録。
私は、愛する肉親を失った数千人の遺族の究極の悲しみの場に立ち会った。
どれもが、私の記憶の奥底に永遠に封じこめておきたい凄惨(せいさん)な情景である。できることならあの夏の出来事だけは私の記憶からすべて消し去りたいと思う。でも夏が近づくとあの情景が、もぞもぞと這(は)いだしてくる。忘れようにも、忘れられるものではないのである。それならば、今年はあの遺体確認捜査の責任者として1つの節目をつける年でもあると思った。
それは、夏から冬に至る127日間にわたる身元確認作業の中で、とくに藤岡市内の3つの体育館の中で行われた、47日間の実録を記すことであった。(中略)
遺族の極限の悲しみが集約された体育館の中で、各々の職業意識を越えて、同じ思いで同化していった1つの集団の記録を決して風化させてはならないと考えて本書を執筆した。――「はじめに」より抜粋
--このテキストは、絶版本またはこのタイトルには設定されていない版型に関連付けられています。
内容(「BOOK」データベースより)
1985年8月12日、群馬県・御巣鷹山に日航機123便が墜落。なんの覚悟も準備もできないまま、一瞬にして520人の生命が奪われた。本書は、当時、遺体の身元確認の責任者として、最前線で捜査にあたった著者が、全遺体の身元が確認されるまでの127日間を、渾身の力で書きつくした、悲しみ、怒り、そして汗と涙にあふれた記録である。
内容(「BOOK」データベースより)
1985年8月12日、日航123便は群馬県御巣鷹山中に墜落し、520名の犠牲者を出した。発表された事故原因は圧力隔壁破壊。だが、その結論には多くの専門家が首をかしげた。何が隠されたのか。元日航機長の著者は、各種の資料を収集し、事故原因を追究する。そして、ついに内部告発者があらわれ、隠されていた証言が事故の真相と隠蔽の構図を浮き彫りにした。迫真のノンフィクション。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
藤田 日出男
1934(昭和9)年生れ。’56年3月大阪府立大学農学部獣医学科卒業。’58年、運輸省航空大学校卒業。同年、日本航空入社。パイロットとして、コンベア880、ダグラスDC‐8などに乗務。’94(平成6)年、同社を退社。航空安全活動歴は長く、’66年、「航空安全推進連絡会議」設立に参加。’87年、英国クランフィールド工科大学で航空事故調査のマスタークラスに学ぶ。現在、「日本乗員組合連絡会議」事故対策委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
内容(「BOOK」データベースより)
1985年8月12日、日航123便ジャンボ機が32分間の迷走の果てに墜落し、急峻な山中に520名の生命が失われた。いったい何が、なぜ、と問う暇もなく、遺族をはじめとする人々は空前のできごとに否応無く翻弄されていく…。国内最大の航空機事故を細密に追い、ジャンボに象徴される現代の巨大システムの本質にまで迫る、渾身のノンフィクション。講談社ノンフィクション賞受賞。
Amazon.co.jp
硬派の警察小説や社会派ミステリーの分野で当代一の横山秀夫が、上毛新聞記者時代に遭遇した御巣鷹山日航機墜落事故取材の体験を、本格長編小説にまとめ上げた。常に新しい手法を模索し手抜きを知らない著者の、会心の力作だ。
組織と個人の軋轢、追う者と追われる者の駆け引きなどを緻密な筆でつづり、水際立った展開で読み手を引きこむのが横山の持ち味である。しかし本作では、あえてその筆の巧みさに自ら縛りをかけ、実体験をベースに抑制の効いた渋い群像小説となった。トリッキーな仕掛けや、えっ、と声が出そうなスリリングな結末、といったものはない。練りに練ってこれ以上は足し引き不可能な研ぎ澄まされた文章で、未曾有(みぞう)の大事故に決然と立ち向かい、あるいは奔流を前に立ちすくむ人間を描いている。
地方新聞の一筋縄ではゆかない、面妖と言っても過言でない人間関係、ひりひりした緊張感。おそらく横山自身が体験したのであろう新聞社の内幕はリアルで、読み止めを許さない。過去に部下の新人がなかば自殺の事故死を遂げた負い目をもつ主人公は40歳の遊軍記者だ。大惨事の現場にいち早く到着し、人間性のどこかが壊れてしまった26歳の若手記者や、現場雑感の署名記事をつまらぬ社内の覇権争いでつぶされる33歳の中堅記者、「下りるために登るんさ」と謎の言葉を残して植物状態になった登山家の同僚――どの登場人物も、著者の一部であり、また思い通りにゆかない人生を懸命に生きる、すべての人間の一部でもある。
本作は、普通に捉えれば著者の新境地だろう。しかし、これはむしろ横山が元々、奥深くに抱いていたものではないか。著者は本書を上梓することで、自身も過去に決着をつけようとしている印象を強く受ける。やや明る過ぎて物足りない感のある結末も、聖と俗を併せ持つ人間にもっと光を当てたい、救いたいという願いであり、そしてなにより著者自身が本作を支えに新たな一歩を踏み出すためのものだろう。また、そうであってほしい(坂本成子) --このテキストは、 単行本 版に関連付けられています。
出版社/著者からの内容紹介
85年、御巣鷹山の日航機事故で運命を翻弄された地元新聞記者たちの悲喜こもごも。上司と部下、親子など人間関係を鋭く描く。
北関東新聞の記者・悠木は、同僚の安西と谷川岳衝立岩に登る予定だったが、御巣鷹山の日航機墜落事故発生で約束を果たせなくなる。一方、1人で山に向かったはずの安西は、なぜか歓楽街でクモ膜下出血で倒れ、病院でも意識は戻らぬままであった。地方新聞を直撃した未曾有の大事故の中、全権デスクとなった悠木は上司と後輩記者の間で翻弄されながら、安西が何をしていたのかを知る――。 実際に事故を取材した記者時代の体験を生かし、濃密な数日間を描き切った、著者の新境地とも言うべき力作。
若き日、著者は上毛新聞の記者として御巣鷹山の日航機事故の 現場を取材しました。18年という長い時を経て初めて、その壮絶な体験は、 感動にあふれた壮大な長編小説として結実しました。それが本作品です。
――記録でも記憶でもないものを書くために、18年の歳月が必要だった。