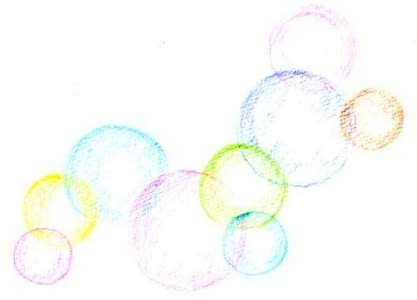金曜日の夕方から夜にかけて、東京オペラシティコンサートホールにて、ケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジ聖歌隊の演奏を聴きに行ってきました。
曲目は以下の通り。ルネサンスから現代まで幅広い時代にわたっており、アカペラ、オルガンによる伴奏つきの演奏、オルガンソロの演奏とがありました。
R・パーソンズ(1535~1572)「アヴェ・マリア」
A・ベルト(1935) 「晩祷」
S・ラフマニノフ(1873~1943) 晩祷Op.37 より 「生神童貞女や慶べよ」
J・S・バッハ(1685~1750) オルガン・ソロ
J・シェパード(1515~1558) 「西風のミサ」よりグローリア、アニュス・ディ
H・パーセル(1659~1695) 「主に仕える諸々の僕よ、主をほめまつれ」
休憩
E・エルガー(1857~1934)「アヴェ・ヴェルム・コルプス」
B・ブリテン(1913~1976)「キリストによりて喜べ」Op.30
ヴィリアム・ウォルトン(1902~1983)「戴冠式行進曲『王冠』」
C・H・H・パリ―(1848~1918)「私は歓喜した」Op.51(詩編第122編)
R・V・ウィリアムズ(1872~1958)「味わい、知れ、主の恵み深さを」
J・タヴァナー(1944) 「アテネのための歌」
W・マシアス(1934~1992)「神よ、諸国の民があなたをたたえ」Op.87
アンコール
夕焼け小焼け
With a little hepl from my friends(the Beatles)
パーソンズのアヴェ・マリアはルネサンスの曲。独立した旋律がずれながら重なり合うポリフォニーそのもので、ここで盛り上がるんだ、というような箇所も明確に思えず曲が流れながら盛り上がっていく感じで、終止の形もはっきりしていないように思えたのですが、澄み切ったアカペラの歌声によって、曲とともに盛り上がっていけそうなそんな感じでした。
バッハのフーガト長調。オペラシティの重厚なオルガンとバッハの心打つ音楽に心打たれずにはいられませんでした。オルガンが聴きたくて申し込んだのもあり、まさにその思いを満たしてくれるような演奏でした。
前半の他の曲の演奏も、すべて未知の曲ながら素晴らしく、感動をさそわずにはいられませんでした。永遠の雰囲気をもったアカペラに吸い込まれていきそうな感じでした。
E・エルガーは前半の曲とは打って変わってめりはりや終止もくっきりとしておりしかも美しい曲でした。さすがエルガー、メロディーメーカーだと感じ入った次第。
ブリテンの「キリストによりて喜べ」は劇音楽みたいな感じで、途中で各声部のソロが登場。苦悩に満ちた詩人がキリストと比較する部分とが重要だと解説にあったものの分からず。音の並びは聴きなれない響きで斬新な感じがしました。演出はうまいと思ったのですが。
ウォルトンのオルガンによる「戴冠式行進曲」は昨年のウィリアム王子とキャサリン王妃との結婚式の退堂曲として演奏されたため、なんとなく耳になじんでいました。バッハの神聖でちょっと硬そうな雰囲気とは異なり、のびやかな気持ちになれそうでした。
J・タヴァナーの「アテネのための歌」には腰を抜かしました。最低音部が続けて声を出しっぱなしでいつブレスをしているのか分からない状態。循環呼吸なのではないかと思ったぐらい。ダイアナ王妃の葬儀にて使われた曲で非常に重く悲しい曲だったのですが。
アンコール、夕焼け小焼けが出てきました。合唱への彼らのアレンジが美しくてびっくり。こんなにダイナミックな曲になるのだと。ビートルズのWith a little hepl from my friendsは指揮なしで自然発生的な感じで始まりました。普段から歌っていて生活のひとつになっているのだろうと思いました。合唱へのアレンジもみごとなものでした。
ちょっとひとことでは言えないのですが、聴いていていつの間にか巻き込まれてしまう、そんな魅力を持った演奏ばかりで、最後はなんともいえず温かい気持ちになって帰ることができました。
今まで触れていなかったような音楽を聴くのも大切だ、と思った次第。しかも、この解説も勉強不足で舌足らずなのですが、とても素敵な聖歌隊でした。たちまちファンになってしまいました。
まとまったら書くか、まとまってなくても書くか、文章で書けるかどうかも分かりませんが、更新しようとは思っています。
函館への旅行に出て本番後の初レッスンがあって、時が矢のように過ぎているような気がします。慌ただしい日々でも自分を見失わないようにしたいと思うこのごろです。
先日のピエール・アンタイ氏のチェンバロによるスカルラッティのK175の演奏の記事を多くの方たちが閲覧してくださいました。ありがとうございます!
出だしのところ、溜めがあるように聴こえます。記譜上では均等に書かれている2音の長さの一方を長く、一方を短く演奏するという、イネガル奏法のようです。しばらくすると非常に激しく反り返ったような不協和音が聴こえてきます。あまりクラシック音楽では聴かないような斬新な響きの和音。その和音が体当たりで叩きつけられたかと思ったら、また急速なパッセージとともに舞い上がっていき、何かを訴えかけるような熱く美しいメロディーが歌い上げられ、情熱が再び不協和音の塊となって繰り返し繰り返し注がれます。なんと激しく情熱的で血潮したたる演奏なのでしょう。ピエール・アンタイ氏はどんな様子でこの曲を演奏しているのでしょうか。写真の落ち着いたような風貌からは、髪を振り乱しているようには思えないのですが、あの演奏では思いっきり髪を振り乱していそうな感じがします。
チェンバロの場合、1つの鍵盤で複数の弦を鳴らすことができるのですね。8フィートの弦2本とか、8フィートの弦2本+4フィートの弦1本とか。そうすることによって演奏を豪華にしたりすることができるようです。この曲も、2本以上の弦が使われている気がします。スカルラッティのこのK175はチェンバロの特性を生かした名曲であり、アンタイ氏の演奏はまさに名演奏だと思います。この曲が街中などでかかっていたりしたらかっこいいと思う人が多いような気がしています。
ちなみにスカルラッティの不協和音と、近代以降の不協和音の働きには関連性があるのだろうか、という疑問も湧いています。
古い音楽もいろいろ探ってみたら、さらに面白い発見がありそうな気がします。そういいながら、ヒルデガルド・フォン・ビンゲンのオルド・ヴィルトゥトゥムに感銘を受けていたのでした。当時はバロック以前の音楽は苦手と書いていたようなのですが、だんだん抵抗がなくなってきています。このオルド・ヴィルトゥトゥムも改めて聴いてみたらさらに魅力的に感じました。ミステリアスな面、怪奇的な面もあるように思うのですが、そこも含め興味が尽きません。
最後に、先日アップしたフランクのプレリュードとフーガ、変奏Op.18の演奏も聴いてくださりありがとうございました。早いものでその日から二週間がたったのですね。この記事をもって削除します。そして今後も研鑽を積んでいきたいと思います。
スカルラッティといえばどのような曲を作った方という印象をお持ちでしょうか?
快適で涼やかで胸のすく気持ちの良い曲を作った方。きらりとしたセンスが素敵な方。ときどきぴりっと心引き締まりそうになったりする曲もあるけれど、恐ろしそうな感じとは無縁。不協和音なんかなおさら無縁。濃い方の多い作曲家たちの中ではほっとさせられる癒し的な存在の方、だと思っていらっしゃる方も多いかもしれません。実は私も、そうでした。それでも好きだったんですけどね。
ところがこんな演奏をある方に紹介していただき、のけぞりそうになりました。ピエール・アンタイ氏というチェンバリストによる、K.175の演奏です。
出だしからすっ飛ばすような勢いです。こんな激しい演奏があっていいのでしょうか。そして注目すべきは中間部!なんだこれは、と思えそうなところがいくつか登場します。
今書いてしまうと聴く楽しみが半減してしまうので、今回はここまでにしておきますね