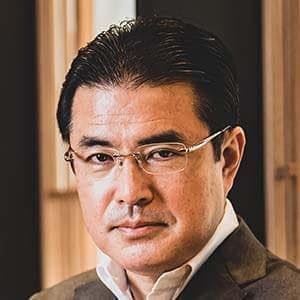日産の内田社長(左)とホンダの三部社長
日産自動車は5日、ホンダとの経営統合に向けた基本合意書(MOU)を破棄する方針を固めた。持ち株会社方式で協議したが、統合比率などの条件が折り合わなかった。
ホンダは日産の子会社化案も打診したものの、日産は社内で反発が起き協議の打ち切りを決めた。世界3位グループの誕生を目指した統合計画は、約1カ月で振り出しに戻る。
日産はホンダに対し4日に経営統合に向けた協議を打ち切る意向を伝えた。日産は5日に取締役会を開催し、2024年12月に締結した経営統合に向けたMOUを破棄することを議論した。
ホンダと日産は日本経済新聞の報道を受けて、「様々な議論を進めている段階であり、2月中旬をメドに方向性を定め、発表する」とのコメントを出した。
両社は24年12月23日に経営統合に向けた協議に入ると発表した。当初は持ち株会社を設立し、新会社の傘下にホンダと日産が入る方向で検討を進め、25年6月の最終合意を目指していた。

ホンダ、日産にさらなるリストラ策を要求
日産がホンダとの統合協議の打ち切りを決めた背景には、経営統合を巡り、大きな隔たりがあったためだ。
ホンダは経営統合の協議の条件として、業績不振の日産に対し再生プランの策定を求めていた。日産は24年11月に全従業員の7%にあたる9000人を削減し、世界生産能力も2割減らす方針を打ち出していた。
日産はタイや北米などで人員削減をするなどの再生プランの大枠を固め、ホンダに水面下で提示した。ただ、ホンダは踏み込み不足と判断し、日産にさらなるリストラ策を強く求めた。
持ち株会社の統合比率でも調整難航
持ち株会社の統合比率でも調整が難航した。基本合意書では公表前より一定期間の平均株価などで算出することを定めた。
日経新聞での試算ではホンダと日産の比率は時価総額でおよそ5対1が協議の出発点となる。統合会社で日産の存在感は低下するため、株価の算出の時期を巡り対立があった。
ホンダは日産の立て直しや統合比率の協議に時間がかかると判断し、日産を子会社化してホンダ主導で再生させる案も打診した。だが、これに日産が強く反発した。
基本合意書では持ち株会社方式を前提としていた。想定と異なる子会社化を唐突に提案したホンダへ日産社内の不満が強まった。日産は基本合意書に基づいて協議を進めることは難しくなったと判断した。
ホンダと日産は統合協議をいったん打ち切るが、持ち株会社方式を前提として再協議するか、このまま破談にするかの選択肢があるとみられる。車載ソフトウエアや部品の共通化などの業務提携に向けた協議は継続する可能性がある。
日産が筆頭株主の三菱自動車は統合への参画を検討してきたが、日産傘下のままホンダも交えた3社の協業を進めるとみられる。
ホンダと日産が歴史的な大型再編に向けた決断をした背景に、台湾電機大手、鴻海(ホンハイ)精密工業の影があった。
鴻海は経営不振の日産に狙いを定め、経営に参画しようと動いていた。統合協議が打ち切りとなり、今後は鴻海の出方も焦点の一つとなる。
※掲載される投稿は投稿者個人の見解であり、日本経済新聞社の見解ではありません。
破談となったわけですが、どういった別れ方をするかは今後も注視が必要です。
様々な選択肢が残っています。
しかし、誰の目にも日産の再建策は不十分に映り、その甘さと遅さにホンダが統合を不安視し、自らが経営に直接参画できる買収提案を出しましたが、日産の選択は「自主独立再建」の道となりました。
国内にビッグ2を構築し、様々な構造改革を推進し世界における産業競争力を確立するというシナリオは泡沫夢幻となったわけです。
日産取締役がいかなるロジックで自主独立再建を可能と判断したか、その説明責任は重いと考えます。個人の意見として自主再建の確度は低く、新たな再編・アライアンス劇場の幕開けでもあります。
ホンダの将来性も危うい。
昨年12月の会見でホンダ三部社長は「はっきり申し上げるのは(日産の)救済ではない」と言っていたにも関わらず、ここにきて、「日産を子会社化してホンダ主導で立て直しを進める案も打診した」という辻褄の合わない動きをしたホンダの将来性にも危うさを感じる。
ホンダの社員及び株主に対して、経営統合がホンダにとってどのようなメリットがあるのかの明確な説明がない中で、日産のリストラに時間と労力を割こうと考えたことに、とりわけホンダの利益の大宗を稼いでいる二輪事業関係者はウンザリしただろう。
日産には鴻海に加えて、日米首脳会談を目前にテスラも興味を示すかもしれない。
協議が破談となれば、外資を含む異業種が日産の経営権取得に向けて触手を伸ばす可能性もあり、その交渉には流動的な面もある。
足元では、世界で保護主義政策が始まり、日本勢はHVで稼ぐ方向を示した一方、電動化に対する危機感が少し薄れている。
ただ、日産の先行きには危さが漂うが、ホンダも決して安泰ではない。
そのまま行くと、300万台割れは時間の問題であろう。
今回の協議を引き金に、日本の自動車産業は再編の時代に突入する可能性が高い。
単なる弱者連合では次世代市場に太刀打ちできない。
クルマの価値が変化する中、再編による「規模拡大」と同時にいかに構造転換を図り、これまでにない新価値を創出できるかどうかが問われる。
破談とはいえ、両社ともに、このままで良いわけではありません。
電動化と知能化で、初期投資が嵩むのは目に見えているため、ホンダによる日産の子会社化のシナリオが破談となっても、両社ともに、なんらかの策を打つ必要はあります。
日産は独自で建て直すには体力に乏しく、今後、資本面での支援を得る必要がありそうです。
ホンダも全社的に見れば、健全に見えますが、四輪事業だけ抜き出すと、年産400万台程度と、コネクテッドカーの時代に突入するには微妙な立ち位置です。
売上高で見れば、二輪事業に対して、四輪事業の方が大きいのですが、営業利益では、二輪事業と四輪事業は拮抗しています。
ホンダと日産の電動システムの目線からしても、共有化が相容れない状況でした。
ホンダはHonda 0 Tech Meeting 2024、CES2025と、次世代戦略BEVであるHonda 0を提案しましたが、そこにはホンダ系列の日立アステモのサポートが必須となる駆動システムが提案されていました。
フロントとリアの一体化インバータによる小型化と室内スペース拡大の提案です。
日産がリーフやアリアで培ってきた電動システムの方向性と全く異なる方向性であり、電動化技術の肝である駆動系をどう共有化していくのか、全く先が見えない状況でした。
今後は独立してそれぞれの電動化技術の強みを磨き上げていくことになります。
EV、ソフト、自動運転、AI化という激動の自動車業界において、元々2社の日本連合で本当に生き残ることができるのかもテーマとしてはあった。
日産が単独で生き残るのは困難であり、社内で自律的に危機感が高まらないと、ルノーによる救済の時のような展開になるのではないかと危惧される。
同救済の際に外資系金融機関で日産を担当していたが、その時の危機感は今の日産には感じられない。
最後にようやくルノーの救済を受けることができた事実は忘れ去られている。
ホンダも今回の迷走を挽回するには外資を含む新たなアライアンスが必要になるのではないかと思う。
今回の破談を危機感を高めて一気に企業変革する機会とできるかが注目される。
残念ながらM&Aにおける「対等の壁」の厚さを示す事例として産業史に刻まれそうです。
時価総額や業績などの面からみて「対等」はあり得ない選択。
それでも日産がこだわったのは色あせたプライドの故。
昭和の企業ドラマをみているようです。
もっとも、対等にこだわって統合に突き進むよりも、破談になったほうが良いのかもしれません。
かつて対等にこだわるあまり、統合後の融和に四苦八苦した(している)メガバンクグループの「対等のワナ」の教訓もあります。
ホンダと日産自動車が2024年12月23日、経営統合へ向けた協議入りを発表。持ち株会社を2026年8月に設立し、傘下に両社が入る予定でしたが、日産が基本合意書(MOU)を撤回する方針を固めました。
日産が筆頭株主の三菱自動車の合流も取りやめに。最新ニュースと解説をお伝えします。
<ニュースの理解を深める関連記事>
続きを読む
日経記事2025.2.5より引用