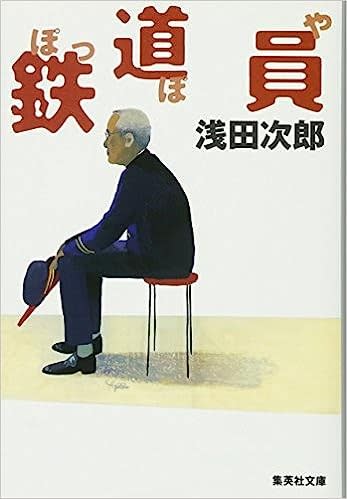第145回の直木賞を受賞した、池井田潤の『下町ロケット』を読む。
読んでいる間ずっと「半沢直樹」に似てるなあなんて読んでいたら、まさしく同じ作家さんの作品だった。ああ、恥ずかしい・・・。
ロケットに搭載する大型水素エンジンの開発に心血を注いできた佃だったが、願いもむなしくロケット打ち上げは失敗に終わる。
それから7年が経過した今、宇宙科学開発機構の研究員をロケット打ち上げ失敗の責を負い辞職した佃は、亡くなった父親の佃製作所の後を継いでた。
代が変わり会社は飛躍的な成長を遂げたが、ある日大口の取引先である京浜マシナリーから、突然取引を一方的に解消される・・・。
題名からロケット打ち上げの話かと勝手に思っていたが(結局はそこへいくんだが)、むしろ読みどころは技術だけは世界トップクラスの中小企業の会社が、大企業の圧力により倒産の危機に追いやられるという話で、読む前の予想とはまったく違った内容だった。
いわゆる会社内のドロドロした上下関係とか、企業間の弱肉強食の駆け引きの話なのだ。
突然会社存続の危機に見舞われた佃が社長を務める佃製作所が、どうやってこのピンチに立ち向かっていくのかというところが、とにかく読みごたえがあり、読みだしたらもはやノンストップで読み続けるしかないという面白さだ。
最初は足並みがそろわなかった社員が次第に協力し、一丸となって夢と情熱で難関を紙一重で次々と乗り切っていくスリルは圧巻である。
こんなに面白い本があったんだなあ。
一見中小企業のプライドと大企業のプライドが激しくぶつかり合うという構図に見えるんだけど、大企業側が振りかざす力はプライドでもなんでもなくただの驕りであり、法にに触れなければ何をやってもいいという卑劣な力に、読者も何度も煮え湯を飲まされた気分にさせられるんだが、飲まされれば飲まされるほど、最後に訪れるだろカタルシスに、気分はフィナーレにむけて否が応にも盛り上がる。
もうワクワクが止まらないのだ。
そしてついにやってくるその瞬間に、佃製作所の社員と一体となって歓喜し、涙するのだ。
まあ窮地に陥るたびに、都合よくどこかから救いの手が差し伸べられという展開が都合よすぎるというところはあるが、そんなものを軽くこえる感動に比べればどうってことはない。
読後は最高に面白い本を読めたという満足感を得られるが、同時に純粋に働くということの意味をも考えさせられる。
お金のためだけに働くことの虚しさが心に鋭く突きつけられる。
そして自らの仕事に取り組む姿勢を深く考えさせられ、そこから次第に湧き上がってくる熱に自ら驚いてしまうだろう。
今はこの小説が文庫化されるのをただ待っていたことが悔しい・・・(^^;)