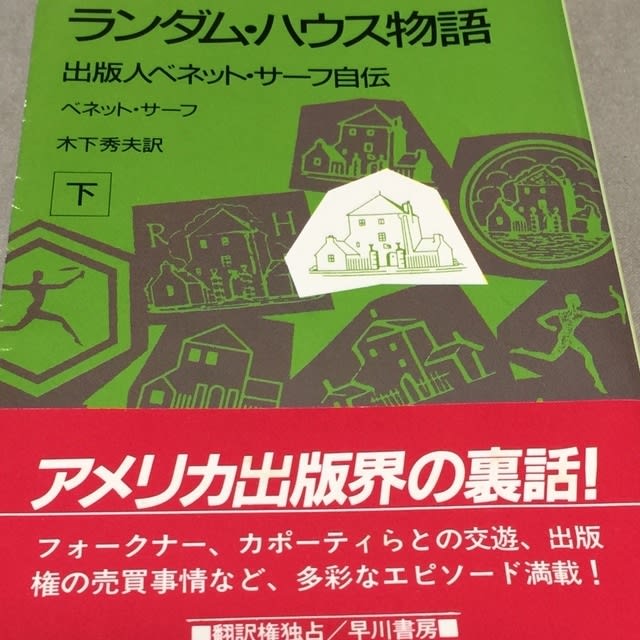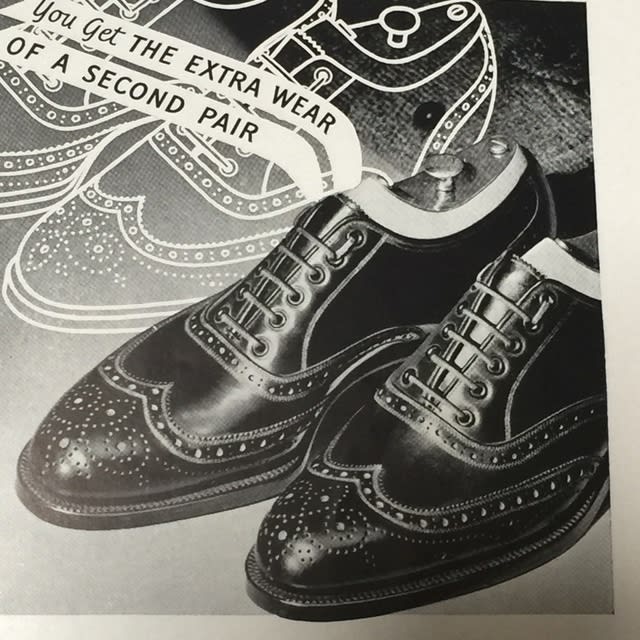今さらですが、今年の冬は寒かったですね。
上空に寒波がきていた2月初めに関西に行ってしまい、連日下がマイナス2~3度で久々に寒いおもいをしました。

(比叡山の東側の麓でみた、寒そうな画)
寒い季節は乾燥とのたたかいですが、心なしか昨年よりましな気もします。
乾燥といえば、外国製の保湿クリームを使っていた友達が、ポンプの先が容器の底までとどいてないので、最後まで使い切るのに毎回面倒な思いをすると言ってたことがありました。
「言ってあげた方がいいかな?」
「そうだね、何万人か分かんないけど、改善されたらきっと世界中の利用者がスッキリするね」
なんて言ってたのも懐かしい。
数年前に買った、一枚仕立ての薄いコートがあります。
買うときに分かっていましたが、裾にあおりどめがありません。
後で付ければいいかと思いましたが無精して未だそのままで、風雨の強い時には「イギリス製なのにダメだなぁ、何で付けないかなぁ」と、パンツの膝下を濡らしながら毎回思います。
私の話はスッキリしていませんが、何だかそういうことを忘れない教訓として、そのままにしておこうなんて気持ちもないではない今日このごろ。

旅に出るたび思い出す、あのシューマイは.....
でなくて、こちらは一枚仕立てでもいわゆるダブル・フェイスのボリュームある素材。
生地を接ぐ部分の張りで、特徴ある雰囲気が生まれます。
少ないながら、ここ数年いくらか見ます。
上空に寒波がきていた2月初めに関西に行ってしまい、連日下がマイナス2~3度で久々に寒いおもいをしました。

(比叡山の東側の麓でみた、寒そうな画)
寒い季節は乾燥とのたたかいですが、心なしか昨年よりましな気もします。
乾燥といえば、外国製の保湿クリームを使っていた友達が、ポンプの先が容器の底までとどいてないので、最後まで使い切るのに毎回面倒な思いをすると言ってたことがありました。
「言ってあげた方がいいかな?」
「そうだね、何万人か分かんないけど、改善されたらきっと世界中の利用者がスッキリするね」
なんて言ってたのも懐かしい。
数年前に買った、一枚仕立ての薄いコートがあります。
買うときに分かっていましたが、裾にあおりどめがありません。
後で付ければいいかと思いましたが無精して未だそのままで、風雨の強い時には「イギリス製なのにダメだなぁ、何で付けないかなぁ」と、パンツの膝下を濡らしながら毎回思います。
私の話はスッキリしていませんが、何だかそういうことを忘れない教訓として、そのままにしておこうなんて気持ちもないではない今日このごろ。

旅に出るたび思い出す、あのシューマイは.....
でなくて、こちらは一枚仕立てでもいわゆるダブル・フェイスのボリュームある素材。
生地を接ぐ部分の張りで、特徴ある雰囲気が生まれます。
少ないながら、ここ数年いくらか見ます。