明治初期の関東では、1円の通称を「円助」といい50銭は「半助」と呼んだとある。当時うなぎ一匹のお値段が1円で、財力的に半分しか買えない庶民は、うなぎの半身をも捩って「半助」と呼んだとあるが、これは頭を含む半匹のことを指すようだ。一方、関西では作家 花登 筺(はなと こばこ)の原作「道頓堀」のお話で、うなぎの「いづもや(現存)」の繁盛記で、女将役 小山明子・半助役 大村昆で、うな丼の「まぶし(現在は訛ってまむし)」を考案したのが道頓堀の「いづもや」ならば、丼のタレをうなぎの頭からとった出汁で作る作業があった。半助が「まかない食」に鰻ダレで豆腐を炊いたものを白ご飯にぶっかけて、毎日食べていたのをヒントに、女将さんが「半助丼」として売り出したとあった。このふたつの説があるが、ワシは後者を支持する。


上記のご紹介をした当時は、Googleで「半助丼」を調べると、僅かワシのブログだけヒットしたものが、今では「辻調理師学園」の豪華な半助鍋までヒットするようなメジャーになっている。運悪く本家のワシのブログが、5年前にBIGLOBEウェブリブログの不手際で消えてしまったので、今ではワシのレシピで再現してくださった、クッキーさんのブログ「半助丼」←※つつくとリンクで残っている程度。従って再びアップして起源の本筋を正し、半助の間違った情報を訂正したい。

関西で「半助」と耳にするのは、関東では焼く前に頭を落として蒸すが、関西では1匹丸ごと焼き上がってから頭を落とす。関西のうなぎ専門店や料理店では、この頭から出汁をとるので、業界用語として「半助」は残ったのだ。さてお役御免となった半助を利用する正当な「半助丼」は、あくまでも・・・まかない食なので、うなぎの出汁で煮込んだ豆腐を白ご飯にぶっ掛けるだけで、運が良ければうなぎの頭が紛れ込む程度なのだ。しかし現在は飽食の時代で、味が沁み込んだ豆腐だけでは物足らず、豆腐を始め、うなぎの頭・身・三つ葉・卵・刻み海苔で調理するレシピを紹介するが、これもうなぎの切り身が少なくてすむので節約と言えるだろう。

■半助丼の材料
・うなぎの蒲焼:一匹(約3人分)
・絹こし豆腐:1丁
・三つ葉:ひと袋
・卵:3個(1人分)
・刻み海苔:適量
☆市販の蒲焼のタレ:一個
☆味醂:大匙3
☆お湯に溶いた鰹出汁の素:2/3カップ
・山椒:お好みに応じて

■半助丼の作り方
・うなぎ蒲焼を幅約7ミリの厚さに断面が大きく見えるように削ぎ切りにする。
・絹ごし豆腐は厚みを7ミリ程度で、大きさは2×3センチくらいに切る。
・☆市販の蒲焼のタレを味醂・鰹出汁でのばし、一人前ずつ3回に分けて使用。
・鍋に上記のタレとうなぎの頭をいれ煮込んだあと、豆腐も並べいれる。
・豆腐を放射線状に並べなおし合間にうなぎも交互に並べて煮込む。
・食材に味が沁み込んだら、刻んだ三つ葉をふぁっさとかける。
・溶き卵(一個全卵・一個黄身のみ)を中心部、そして外側にもまわし入れる。
・卵が半熟状になったら火を消す。
・すばやく丼にアツアツ白ご飯をいれ、その上へ滑らすように乗せ蓋をして2分蒸らす。
・更に卵黄を一個センターに乗せ、周囲に刻み海苔を散らせば出来上がり。

余談だが、出雲の宍道湖から生きた「うなぎ」を大阪へ運ぶには、途中で息絶えるうなぎが続出したため、弱りきったうなぎを復活させるべく、中継の池が何箇所も必要だったようで、それぞれが「いづもや」を屋号にしていたから、うなぎ屋さんには「いづもや」の屋号が多いそうだ。


上記のご紹介をした当時は、Googleで「半助丼」を調べると、僅かワシのブログだけヒットしたものが、今では「辻調理師学園」の豪華な半助鍋までヒットするようなメジャーになっている。運悪く本家のワシのブログが、5年前にBIGLOBEウェブリブログの不手際で消えてしまったので、今ではワシのレシピで再現してくださった、クッキーさんのブログ「半助丼」←※つつくとリンクで残っている程度。従って再びアップして起源の本筋を正し、半助の間違った情報を訂正したい。

関西で「半助」と耳にするのは、関東では焼く前に頭を落として蒸すが、関西では1匹丸ごと焼き上がってから頭を落とす。関西のうなぎ専門店や料理店では、この頭から出汁をとるので、業界用語として「半助」は残ったのだ。さてお役御免となった半助を利用する正当な「半助丼」は、あくまでも・・・まかない食なので、うなぎの出汁で煮込んだ豆腐を白ご飯にぶっ掛けるだけで、運が良ければうなぎの頭が紛れ込む程度なのだ。しかし現在は飽食の時代で、味が沁み込んだ豆腐だけでは物足らず、豆腐を始め、うなぎの頭・身・三つ葉・卵・刻み海苔で調理するレシピを紹介するが、これもうなぎの切り身が少なくてすむので節約と言えるだろう。

■半助丼の材料
・うなぎの蒲焼:一匹(約3人分)
・絹こし豆腐:1丁
・三つ葉:ひと袋
・卵:3個(1人分)
・刻み海苔:適量
☆市販の蒲焼のタレ:一個
☆味醂:大匙3
☆お湯に溶いた鰹出汁の素:2/3カップ
・山椒:お好みに応じて

■半助丼の作り方
・うなぎ蒲焼を幅約7ミリの厚さに断面が大きく見えるように削ぎ切りにする。
・絹ごし豆腐は厚みを7ミリ程度で、大きさは2×3センチくらいに切る。
・☆市販の蒲焼のタレを味醂・鰹出汁でのばし、一人前ずつ3回に分けて使用。
・鍋に上記のタレとうなぎの頭をいれ煮込んだあと、豆腐も並べいれる。
・豆腐を放射線状に並べなおし合間にうなぎも交互に並べて煮込む。
・食材に味が沁み込んだら、刻んだ三つ葉をふぁっさとかける。
・溶き卵(一個全卵・一個黄身のみ)を中心部、そして外側にもまわし入れる。
・卵が半熟状になったら火を消す。
・すばやく丼にアツアツ白ご飯をいれ、その上へ滑らすように乗せ蓋をして2分蒸らす。
・更に卵黄を一個センターに乗せ、周囲に刻み海苔を散らせば出来上がり。

余談だが、出雲の宍道湖から生きた「うなぎ」を大阪へ運ぶには、途中で息絶えるうなぎが続出したため、弱りきったうなぎを復活させるべく、中継の池が何箇所も必要だったようで、それぞれが「いづもや」を屋号にしていたから、うなぎ屋さんには「いづもや」の屋号が多いそうだ。
・・・・・・・・・<切り取り線>・・・・・・・・・
ここを訪問してくださってありがとうです。
どなたさまでも、お気軽にコメント戴けると嬉しいです。
何とか自力で修理した「CANON IXY」と、「iPad-Air2」での撮影です。
日本ブログ村 こだわり料理部門、写真ブログ部門に参戦しております。
下部をポチ(クリック)して頂くと励みになります。

イイネ
どなたさまでも、お気軽にコメント戴けると嬉しいです。
何とか自力で修理した「CANON IXY」と、「iPad-Air2」での撮影です。
日本ブログ村 こだわり料理部門、写真ブログ部門に参戦しております。
下部をポチ(クリック)して頂くと励みになります。
イイネ






















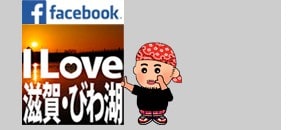









半助丼、思い出した。
うなぎの頭からとった出汁で煮た豆腐だけでも、充分に美味しそうですねー
とても素敵なまかないですよね(^^)
食べたくなってきました~~
ポチポチ
こんちは。(*⌒ー⌒*)ゞ
以前のウェブリブログの時にご紹介させてもらってから早5年ですよ。
早いものですね~~って言うか、変わらぬお付き合いありがとうです。
今回も久しぶりにクッキーさんのブログにお邪魔してリンクのお願いを、
快く了解頂いて、あの頃の想い出も蘇って懐かしかったです。
いつもありがとうです。(^_-)-☆応援感謝!
めちゃくちゃ、色もきれいで
美味しそうだすね
香りまで、こっちに届きそうだすよ~
安くて美味しいのが一番だすよね
ごはん、いっぱい食べちゃいそうだす
ぷっちんだす
こんばんは。(*⌒ー⌒*)ゞ
鰻のタレをのばして煮詰めるパターンをとりますので、
豆腐に味はキッチリとついていて、そこへの卵とじになるんですよ。
うな丼をつくるだけは量を使いませんし、逆に卵とじが美味しいんですよ。
今ではクッキーさんの画像が、後を引き継いでくれているのが幸いで、
あと少しでワシの画像も出ると思います。
応援ぷっちん(^_-)-☆ありがとうです!
「半助」
奥の深い言葉なのですね。
これは凄い!
きざみ海苔が躍っているいるようで素晴らしい。
ぬる燗の本醸造に、多分合いますね。
大応援団派遣\(^o^)/
おはようです。(*⌒ー⌒*)ゞ
丼でお酒いっちゃいますか・・・英さん。ならではでしょうね?(笑)
半助の名称はどこから来たのか、探るのにも一苦労ですよ。
半助さんが丼を考案したとき、既に頭のことを「半助」と呼んでいた説も。
応援団派遣(^_-)-☆ありがとうです。
半助丼も半助鍋も当地では見ないように思います。
最近、外食もあまりしていないので定かではありませんが・・・
大阪のテレビ局の製作した番組で何度か目にした程度です。
うな丼よりも個人的にはスキですね。
豆腐も入ってるというの良いですね。
いつも云ってますが、食べてみたいですね。
でも、
こんばんは。(*⌒ー⌒*)ゞ
外食ではないでしょうね。本文にもありますように「まかない食」で、
あまり対外的には日の目を見ていないのが「半助丼」なんです。
本来ならば濃い味付けの鰻出汁で煮込んだ豆腐を飯にぶっ掛けなんで、
見た目も質素なんですが、ここでは卵が良い仕事していますよね。
いつも(^_-)-☆ありがとうです!