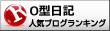年々厳しくなる排ガス規制に49ccでは対応できなくなるので
排気量を世界的に需要のある125ccへ引き上げて馬力を規制する案が有力です。
第一種原動機付自転車という区分を廃止して第二種原付と統合すればいいだけですね。
あの忌まわしい最高速度30km/h規制と二段階右折も廃止の方向で検討されているようだ。
従弟と姪っ子で行く原付ツーリングもそれが大きなネックで
昨年は姪っ子用に中古の3輪バイクをミニカー登録してスピードアップを図りました。
自動車免許で乗れる新基準の原付が発売されたら姪っ子用に購入する予定です。
車の流れに乗るなら制限速度は50km/hに引き上げるべきなんです。
125ccなのに50ccと同じ原付扱いに?! 『5.4馬力以下』案が浮上!【令和5年度 バイクの課題はどうなるPART②】……〈多事走論〉from Nom
配信
道路交通法/道路運送車両法/税金を全て改正できるかが課題
 </picture>
</picture>125ccなのに50ccと同じ原付扱いに?! 『5.4馬力以下』案が浮上!【令和5年度 バイクの課題はどうなるPART②】……〈多事走論〉from Nom
2022年11月26日にはヤングマシン松田編集長が記事を執筆しているように、長年にわたって維持され、親しまれてきた「原付一種は50cc以下」という枠組みが見直されるかもしれません。高速道路料金とともにライダーの関心事となっている「原付」問題を取材しました。 【画像ギャラリー】神カラー早よ! ホンダ「モンキー125」の2023年モデルがタイで登場
保有台数500万台のユーザーが今もいる!
4月4日に投稿した「令和5年度の課題①高速道路料金」に続く課題②としてお届けするのは、「原付」問題です。 手軽な乗り物として1980年代には年間200万台に迫る販売台数を誇った原付一種(=原動機付自転車、以下原付)ですが、高校生への3ナイ運動や、ヘルメットの着用義務、2段階右折、30㎞/hの最高速度規制などによりその存在意義が年々低下してしまい、2021年は約13万台と年間販売台数は約6分の1にまで減少しています。 また、原付の50㏄以下という排気量カテゴリーは現在では日本だけのガラパゴス的な存在となっていて(海外はご存じのように125㏄クラスが主流です)、国内4メーカーもラインナップを絞らざるを得ない状況になっています。 とはいえ、通学や通勤の手軽な足としての需要はまだまだあって、特に公共交通機関が未整備な地方では原付がなければ日常生活が円滑に行えないところも少なくありません。また、年間販売台数が13万台レベルに減少しているとはいえ、まだまだ13万台の需要があり、原付の平均価格を25万円とすると年間325億円の大きなマーケットが存在していて、多くのバイクショップにとっても重要な商材となっています。 さらに、保有台数は500万台近いといいますから、現状でも相当数のユーザーが原付を使用しているのです。 ──原付一種の販売台数の推移を示すグラフ。1980年には200万台近い台数を販売していたが、ここ2年は13万台レベルにまで激減。しかし今でも年間10万台以上の需要がある…とも言えるのだ。
まさに絶滅の危機を迎えている原付を救う手段は?
その原付がいま、絶滅の危機を迎えています。 年々厳しくなる排ガス規制は、当然、原付も規制対象となっていて、2025年10月に新規制が適用されることになっていますが、現在の原付各車がこの規制をクリアするには莫大な費用がかかり、それが販売価格にも反映されて非常に高額なものにならざるを得ないことなどから、メーカーも事実上、現在の50㏄以下という原付の存続を断念せざるを得ない状況になっているのです。 そんな状況を受けて、全国約1600社のバイクショップが加盟する全国オートバイ協同組合連合会(以下AJ)など業界各方面から、原付免許あるいは普通自動車免許で運転できて、価格も手ごろで税金も安い原付を何とか存続させてほしいという声が上がり、約3年後に迫った新規制適用を前に、昨年11月に原付を存続するための具体的な動きが始まりました。 この動きを報じた記事を、昨年11月末に編集長の松田が投稿したところ、思いがけないほどの反響があり、原付がどうなってしまうのかは非常に多くの人の関心事だということが分かりました。 そこで、この課題②では、国内4メーカーが所属する日本自動車工業会(以下 自工会)の関係者にヒアリングした、原付をめぐる現状を整理することにしました。