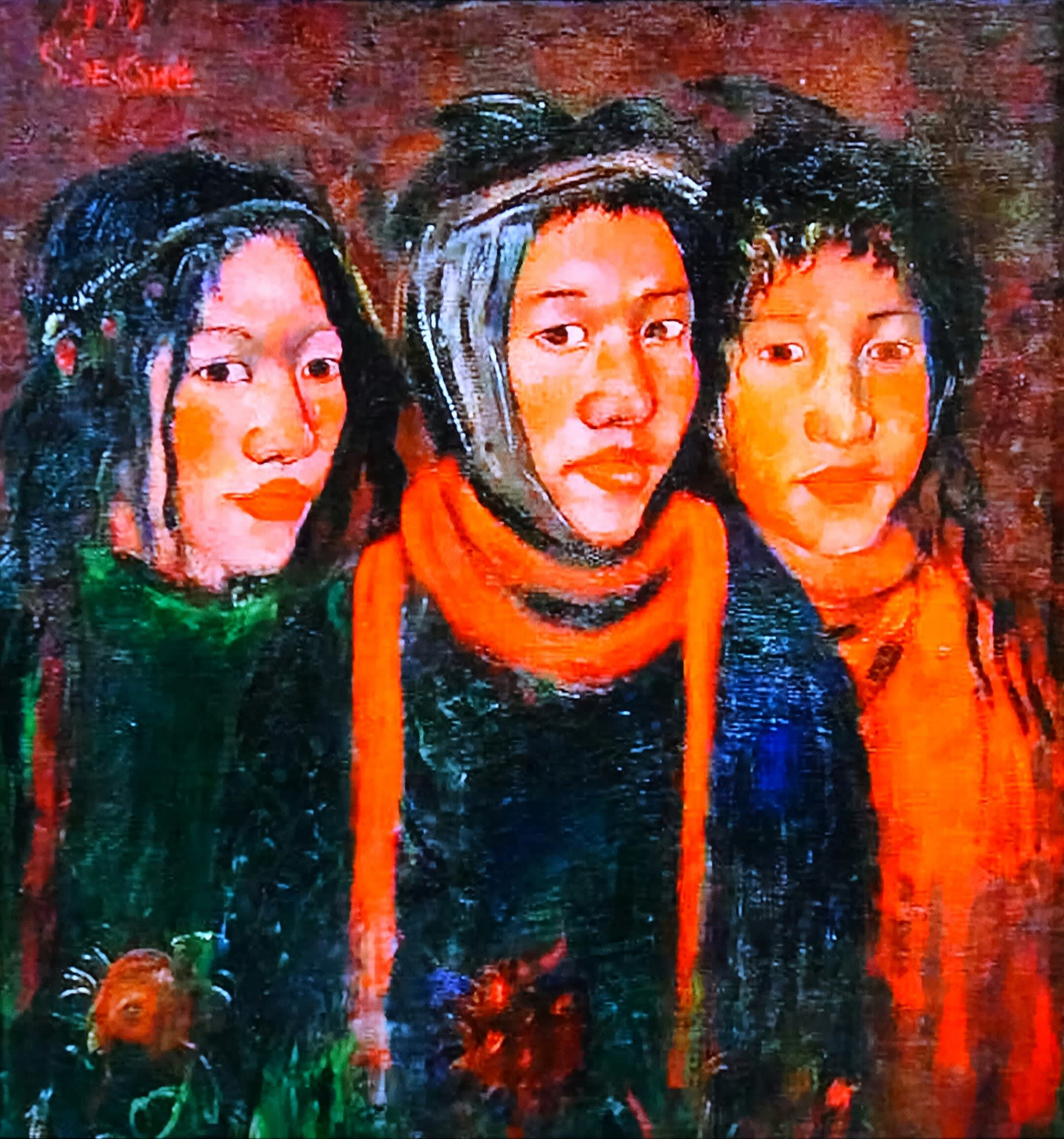本日2度目の投稿です。
祇園祭の山鉾巡行の日、私は巡行前の景色を撮影し、10時過ぎ一旦家に帰りました。
暑さで火照った身体をエアコンで冷やし、身体を休めました。
昼食をとり、夕方までまだ時間があります。
晩御飯は○○にしよう、食材があるので買い物はいらないね、などと考えているうちに、
もう一度、山鉾巡行の終わりを撮影したくなりました。
それで午後1時過ぎにもう一度でかけました。
自宅が山鉾まで比較的近いというのは、良いのか悪いのかわかりません。
四条烏丸東を出発した、山鉾巡行は烏丸御池付近で終了です。
それぞれの山鉾は、それぞれの会所に向かいます。
そして新町通りを帰る山鉾が多くなります。
会所に着いた山鉾は、休む間もなく、解体に入ります。
まるで、祭の余韻を打ち消すかのようです。
実は山鉾は、厄を集める神事なので、集めた厄を留めないためなのです。
会所に帰ってきた山鉾が並ぶ四条通り

郭巨山では、松の木の山を取り外しています。

新町通りを南下する月鉾

向きを変えるために、辻まわしが行われてます。

月鉾の会所に到着した鉾に、拍手と三本締めが行われ、片付けに入りました。

新町通りを南下する岩戸山

同じく南下する船鉾

鶏鉾も片付けに入っています。

菊水鉾も同様です。

函谷鉾でも片付けです。
あっという間に、懸装品がはずされました。

例年はこれで、祇園祭のハイライトが終わり、京都は本格的な夏に突入となります。
でも、今年は古式に戻り、後祭がこれから始まります。
後祭は、前祭の23基より、山鉾数は少ない10基です。
前祭の巡行が終わるとすぐに鉾建てに入り、21日から23日まで宵山、24日に巡行となります。
蛤御門の変で消失した、大船鉾が再興するという記念すべき年です。
朝8時から交通規制されていた四条通りは、午後2時には解除されました。
いつもの景色にあっという間にもどりました。