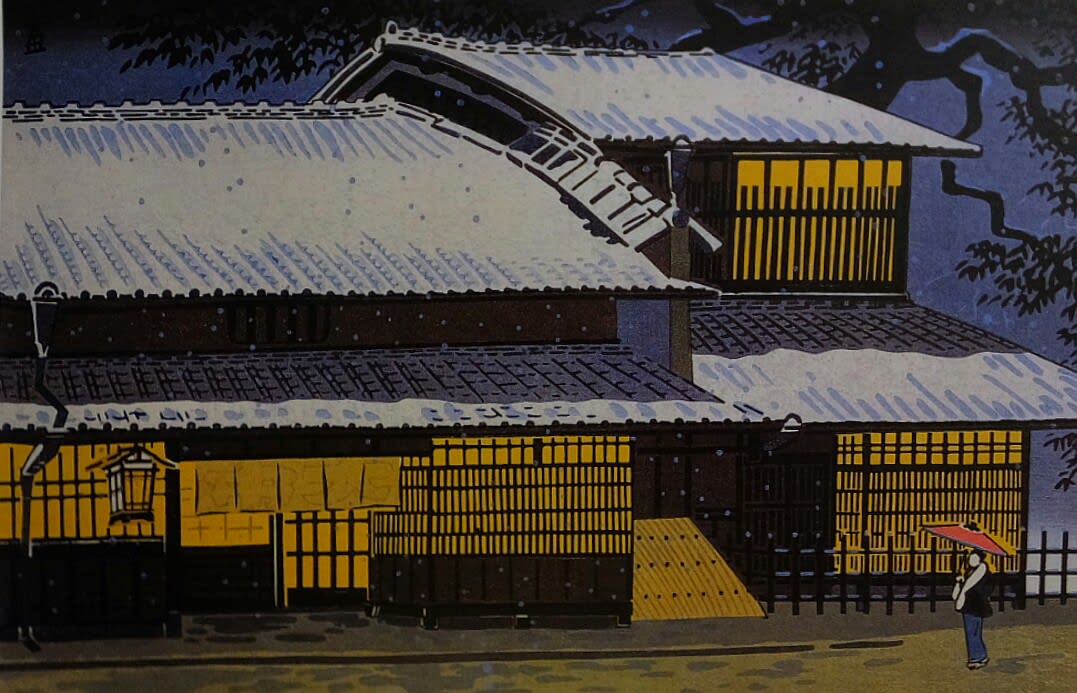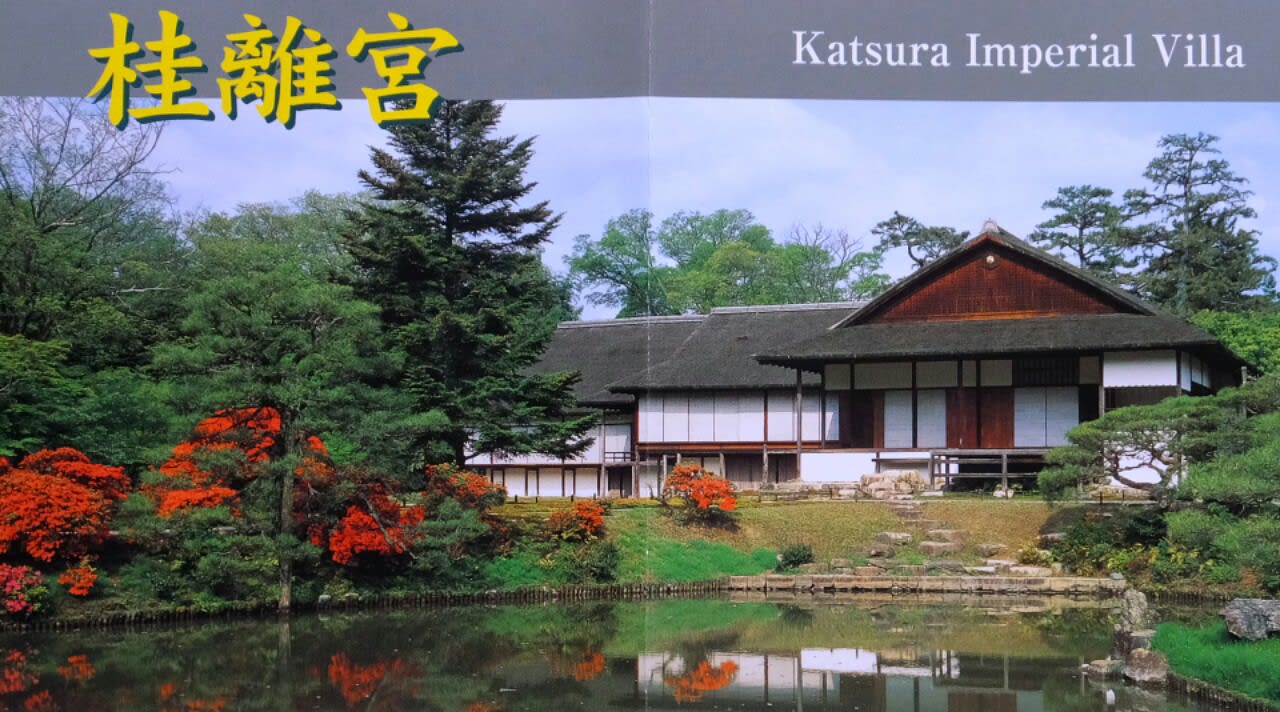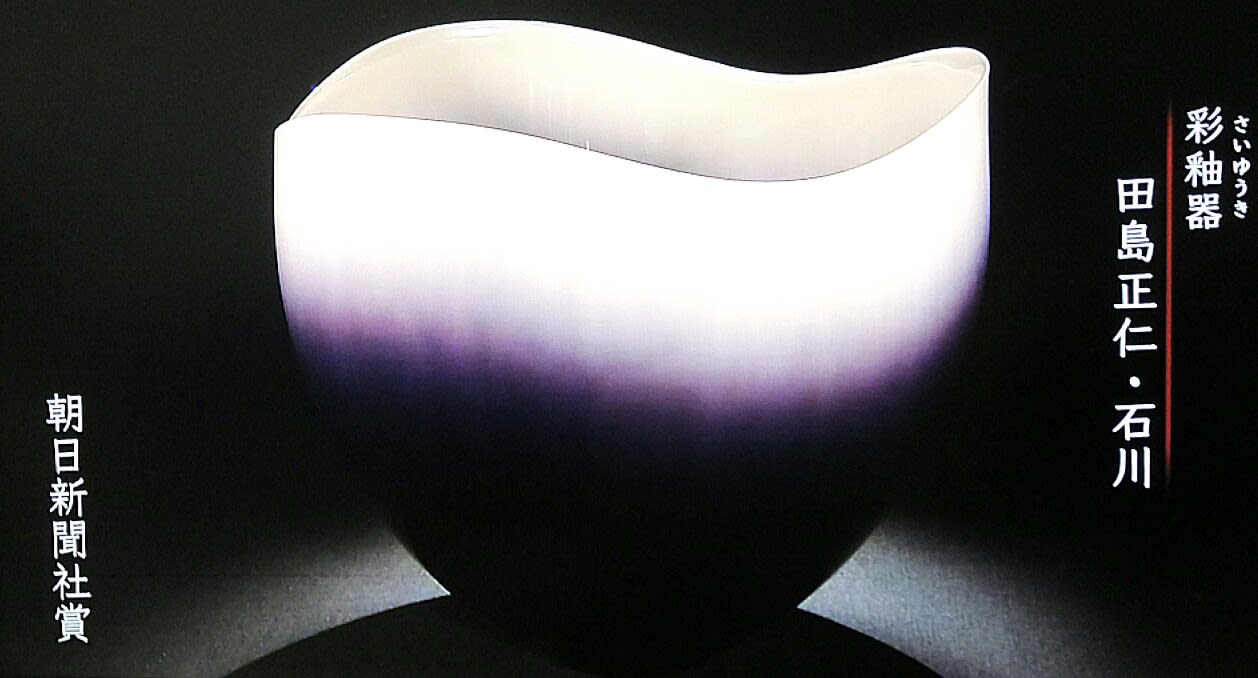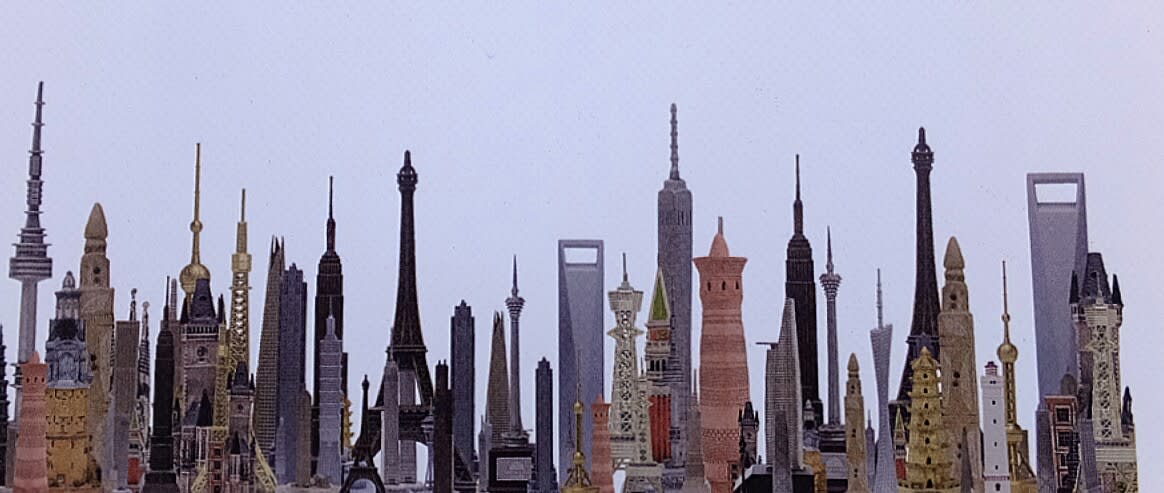朝早く紅葉チェックもかねて向かったのは真如堂です。
通称赤門

本堂前
まだまだ紅葉には早いです。
今年は昨年よりも色づきが遅れています。

本堂前から三重塔
色づいているのは「花の木」とカエデも一部色づいています。


ツワブキが開花しています。

貴船菊(シュウメイギク)


ホトトギスが見頃です。



赤門前のヤマザクラまだ花をつけています。

宗忠神社


本殿

次に向かったのは法然院
茅葺き山門

白砂壇
右側の砂壇が先日来たときにはなかった紅葉が描かれています。


新しく追加された水の流れに落ちたもみじ
一足早く紅葉気分になります。


茶の花

苔むした石垣

安楽寺の紅葉も全く色づいていません。

次に向かったのは永観堂です。
総門

中門前
少し色づいています。







紅葉拝観の案内看板
11月8日から寺宝展と夜のライトアップが始まりますが、紅葉の見頃は中旬以降のようです

最後は南禅寺です。
三門
九時になり三門に観光客が上っています。
私も一度上りましたが、急勾配の階段で足がすくんでしまいました。
紅葉はまだまだです。

法堂

大方丈前

これで朝の散策は終わりです。