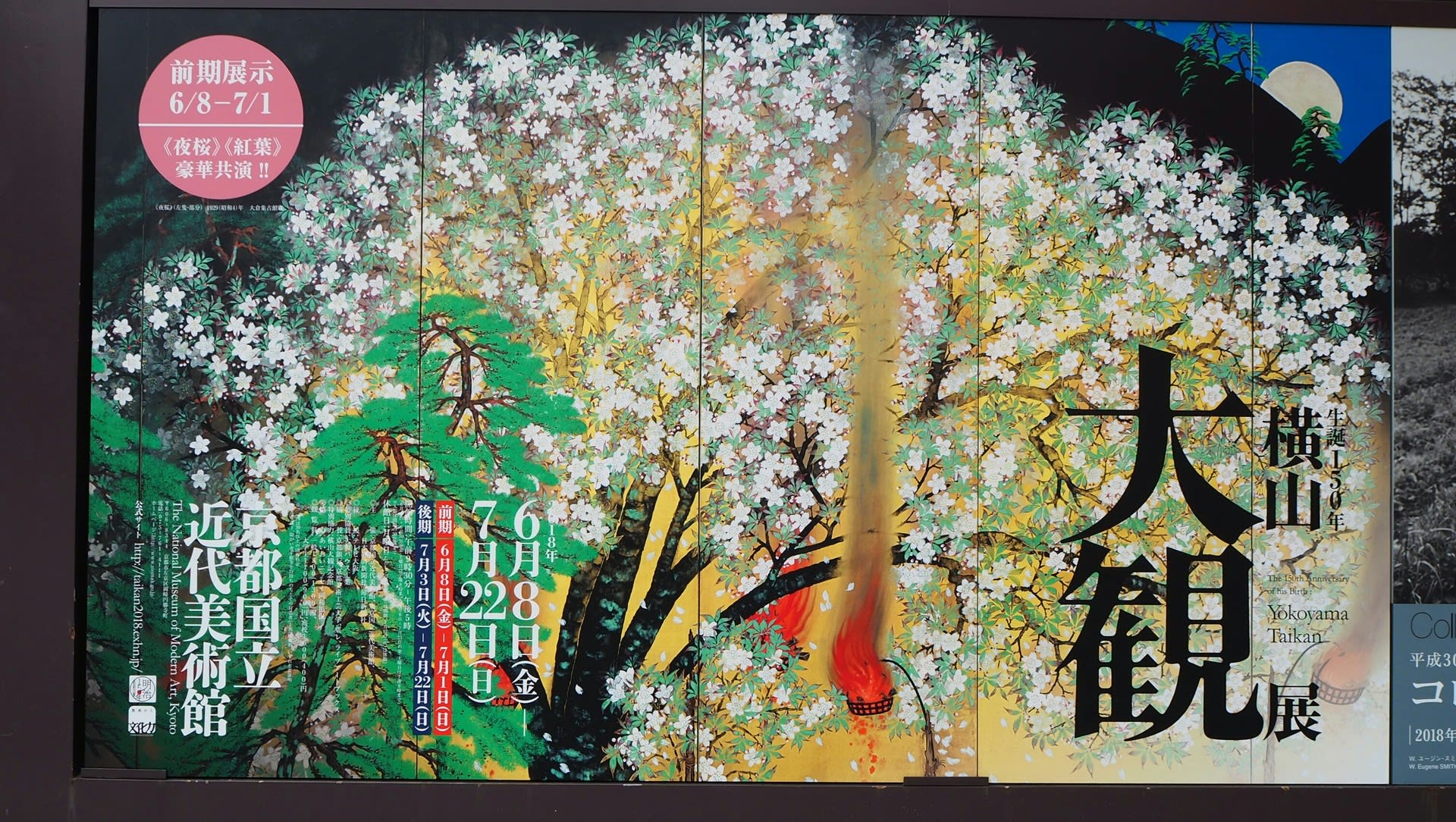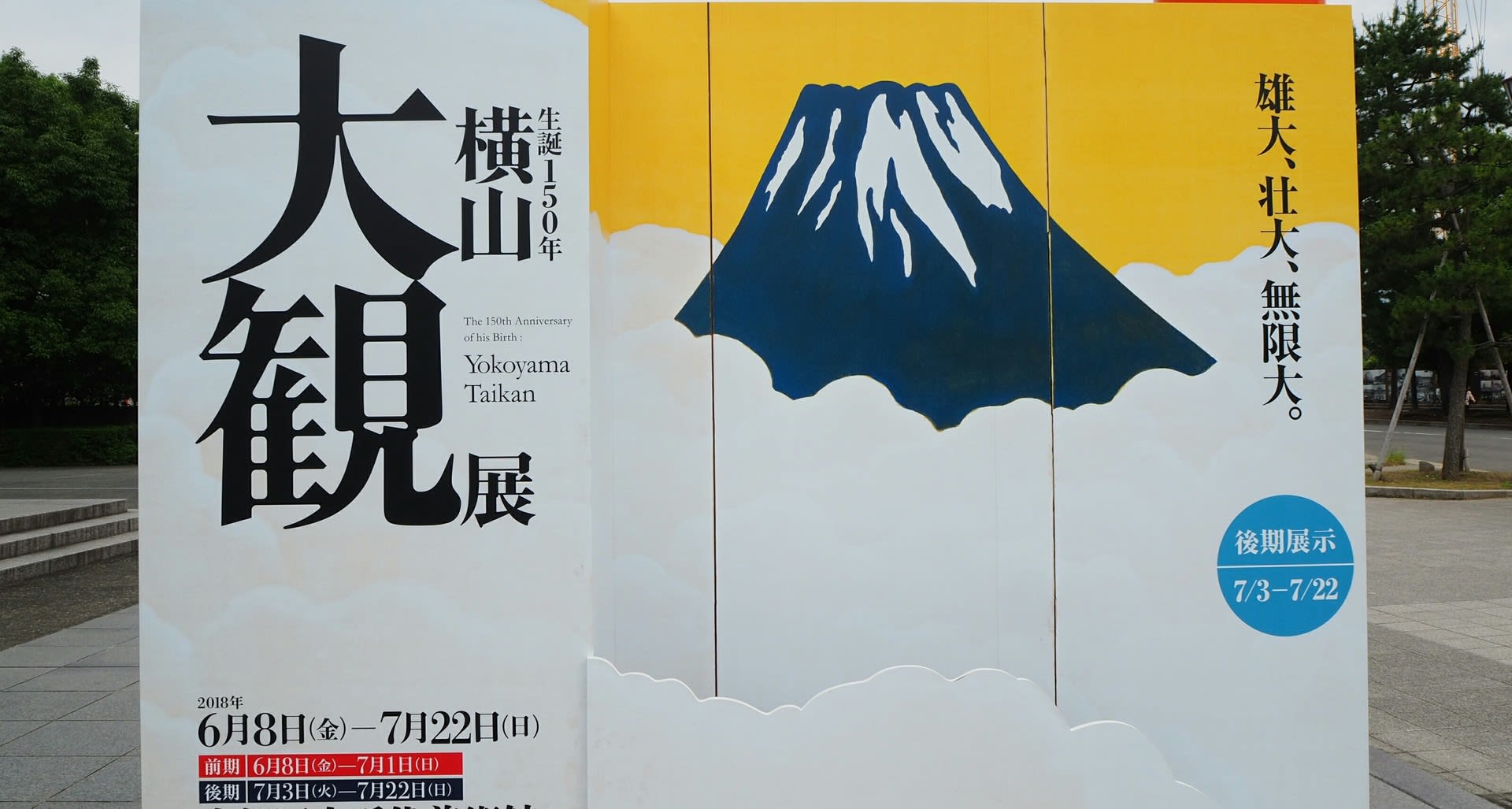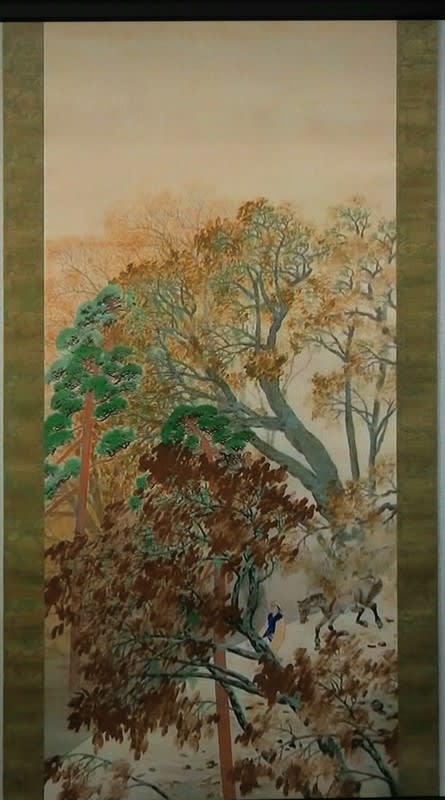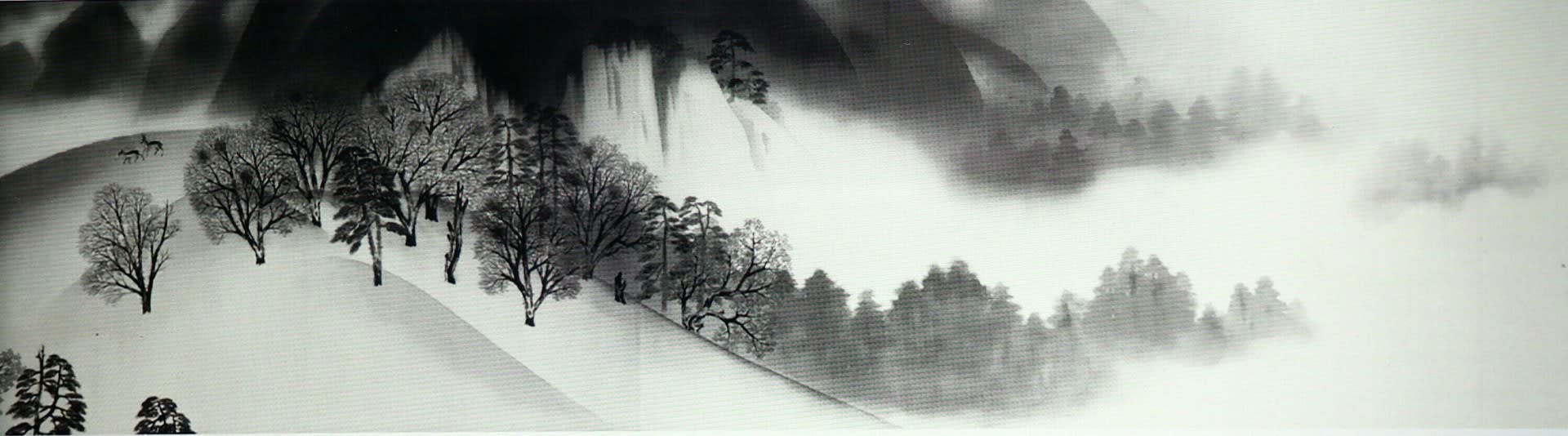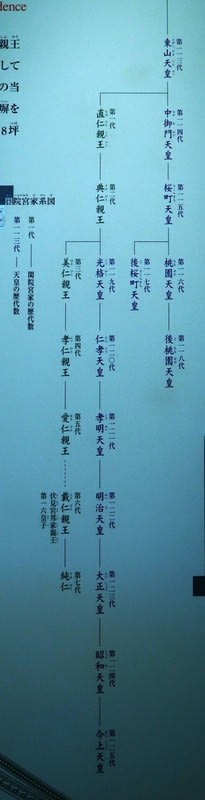東山散策の続きで、安井金比羅宮です。
あらゆる悪い縁を切り、良縁を結ぶ神社として有名ですが、私は京都に住んで長いですが初めての訪問です。
東大路通りの鳥居



縁切り縁結び碑には様々な願いが書かれた「形代」(身代わりのおふだ)が貼られ、碑が見えないほどになっています。
祈願は本殿に参拝し、次に「形代」に切りたい縁・結びたい縁などの願い事を書きます。
「形代」を持って願い事を念じながら碑の表から裏へ穴をくぐります。
これでまず悪縁を切り、次に裏から表へくぐって良縁を結びます。そして最後に「形代」を碑に貼るのだそうです。
本殿

人気とあって縁切り縁結び碑の前に列ができています。






悪縁を切り良縁を結びたいという切ないほどの願いが形代や絵馬に書かれています。
なかには細かな字でびっしり書かれ、願いの重さが伝わってきます。
少し複雑な気持ちで神社を後にしました。
次に向かったのは八坂神社
南楼門

舞殿

西楼門


暑かったのでエアコンの効いた漢字ミュージアムで休憩です。
無料休憩所の祇園祭コーナーで一休みします。

映像ビデオもあります。



見送りも展示されていました。

東山散策はこれでおしまい。