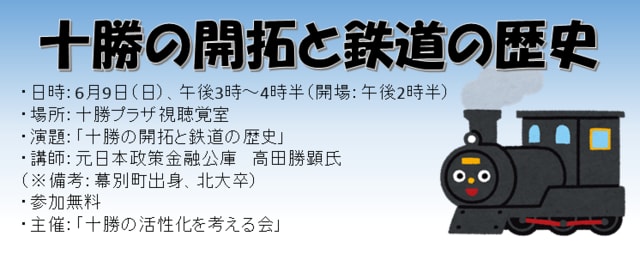遺作《馬(絶筆・未完)》は、むき出しのベニヤに克明に描かれた馬の半身が、 全身全霊でキャンバスに対峙した画家の儚くも力強い生き様を物語っているかのようである。私が初めて絵に対して強烈なイメージを持ったのは、この絵が最初である。

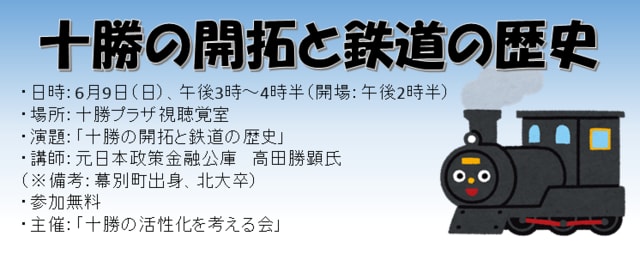

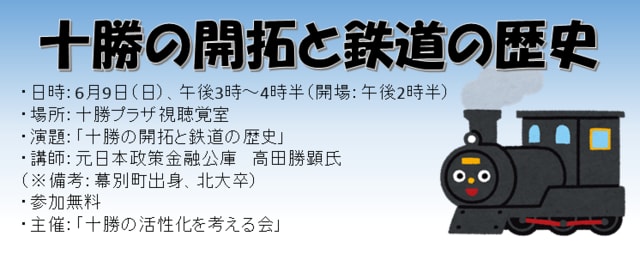
先日、「北海道新聞」令和元年6月4日付け『卓上四季』欄に、以下の記事が載っていた。
『禁煙に挑戦するポイントは、「3」だと聞いたことがある。3日目、3週間目、3カ月目、3年目が難所で、ここを乗り越えるのが肝心なのだそうだ。新入社員にとっても「3」は大切である。様々な理由で退職する人が増えるのが、入社から3日、3週、3カ月、3年の節目だと言われる。この6月が、ちょうど3カ月目にあたる。
だから、というわけではあるまいが、「退職代行」への依頼が目立つそうだ。会社を辞めたいが、自分からは言い出しにくい。そういう人たちに代わり、専門業者が退職手続きをする。「会社を辞める時ぐらい、自分で言えないのか」と思う人もいよう。
ただ、昨今の人手不足もあり、退職の意思を会社に伝えると会社側に強く慰留され、辞めたくても辞められないケースも少なくないらしい。
国の調査では、大卒で就職後3年以内に辞めた割合は3割を超える。
「売り手市場」が続き、転職しやすいという背景もあろう。ただ、せっかく入った企業との縁が、3年足らずで切れてしまうのは残念な気もする。
「若者は、企業が社員を大切にしているかに敏感で、辞める一番の理由は、職場の人間関係です」。学生の就職支援に当たる教授がそう言っていた。』 (後略)
十勝の活性化を考える時、転職は企業の損失に繋がり企業にとってあまり好ましいことでは無い。日本の非正規社員が4割と言われており、愛社精神が醸成されることはまずない。GDPとは関係ないが、このGDPが中国に抜かれ、将来的にはインドにも抜かれるようであり、企業における非正規社員の比率を心配している。
「十勝の活性化を考える会」会員

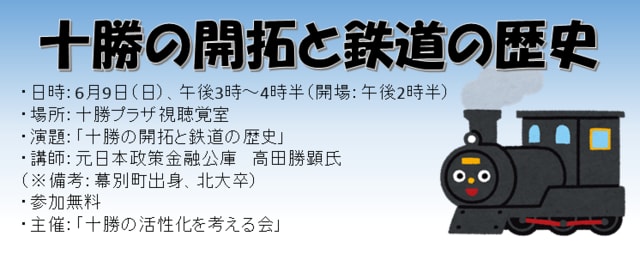
本「北涯の悲劇」(松好貞夫著)には、以下のように書かれていた。
『アイヌの世界は自然と共にあり、且つ、自然なるがゆえに美しく、文明や歴史の爪痕をとどめるがゆえに真実であって、旅する和人がそぞろに郷愁の世界を発見し、あるいは羨望の情けをいだいたのも、あながち無理ではない。
「日本も上古は蝦夷(北海道)の地にかわりし事は少しもなく、無為にして太平なりしものなり。今の蝦夷地には領主・地頭と言うものもなく無為にしておさまり、直なる風俗はうらやましき事なり」とは、古河古松軒のもらした感慨である。 (中略)
考えさせられるのは、徳川時代の人々、それもすべて武士の肩書を持った人々が、領主や地頭がいない蝦夷地をうらやみ、あるいはそこに神代の清純さを発見して歓喜したのと対照的に、原住民たちは和風化する北海道に背を向け、山の奥ふかく「踏晦」して行った。この深刻な事態の時である。けだし民族の文化的な発展段階がどうであろうと、およそ自然と自由への回帰は、人間に共通する永遠の願望であり、理想と言わねばなるまい。
日本の近代文明がアイヌ民族の上にもたらすところは、決してかれらの幸福ではなく、逆にかれらをこの永遠の理想から絶縁する結果だった。』と。
また、知里幸恵のアイヌ神謡集には、以下のようにも書かれている。
『その昔この広い北海道は、私たちの先祖の自由の天地でありました。天真爛漫な稚児の様に、美しい大自然に抱擁されてのんびりと楽しく生活していた彼等は、真に自然の寵児、なんという幸福な人たちであったでしょう。 (中略)
その昔、幸福な私たちの先祖は,自分のこの郷土が末にこうした惨めなありさまに変ろうなどとは,露ほども想像し得なかったのでありましょう。
時は絶えず流れる。世は限りなく進展してゆく。激しい競争場裡に敗残の醜をさらしている今の私たちの中からも、いつかは、二人三人でも強いものが出て来たら,進みゆく世と歩をならべる日も、やがては来ましょう。それはほんとうに私たちの切なる望み、明暮あけくれ祈っている事で御座います。
けれど……愛する私たちの先祖が起伏す日頃互いに意を通ずる為に用いた多くの言語、言い古し、残し伝えた多くの美しい言葉、それらのものもみんな果敢なく、亡びゆく弱きものと共に消失せてしまうのでしょうか。おおそれはあまりにいたましい名残惜しい事で御座います。
アイヌに生れアイヌ語の中に生いたった私は、雨の宵、雪の夜、暇ある毎に打集って私たちの先祖が語り興じたいろいろな物語の中極く小さな話の一つ二つを拙ない筆に書連ねました。
私たちを知って下さる多くの方に読んでいただく事が出来ますならば、私は、私たちの同族祖先と共にほんとうに無限の喜び,無上の幸福に存じます。』
「十勝の活性化を考える会」会員 T

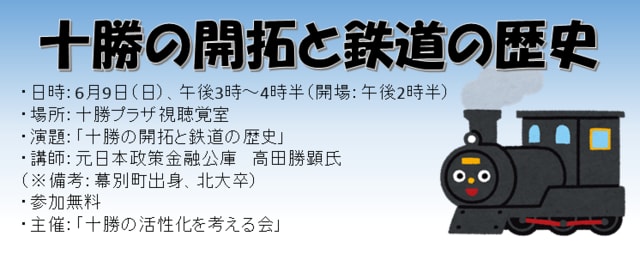
先日、「北海道新聞」令和元年5月30日付け夕刊『今日の話題』欄に、以下の記事が載っていた。
江差追分や歴史的町並みで知られる桧山管内江差町は、「働く障害者の町」でもある。社会福祉法人・江差福祉法人は、江差と周辺に13施設・事業所を持ち、知的障害者を中心に423人が利用。約300人は江差町のグループホームなどから通勤する。同町の人口は7500人。その割合は道内屈指だ。授産事業として行うのは、災害備蓄用の缶入りパンの製造、食堂、給食サービス、撤退した民間施設の運営と多種多様だ。
昨年度の売上は、13憶円と全国トップ級。月平均賃金は、雇用契約を結んで最低賃金を保証する「就労継続支援A型」で9万8千円、雇用契約までは困難な「同B型」で4万5千円。それぞれ全国平均を2万~3万円も上回る。
「転機だった」と理事長の樋口英俊さんは言うのが、20年前のパン工場建設だ。地元業者が「民業圧迫だ」と反発。樋口さんは、「それでは地元と競合しない商品を」
と決意し、今や年間300万個を出荷する缶入りパンにつながった。これを主力に経営センスを活かして業務を拡大していった。 (中略)
樋口さんは言う。「普通に稼ぎ、普通に遊び、普通に暮らしたい。利用者の思いは健常者と変わらないんです。われわれが目指すのは、そこです」。
私は障害者(介護1)ですが、障害を持ってはじめて分かったのですが、健常者は障害者を見て、「障害者だからできない」と思うことがほとんどだと思います。確かに、出来ないこともありますが全てではありません。
「十勝の活性化を考える会」会長


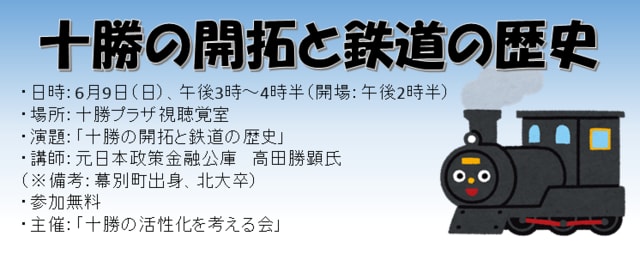
本:「巧みな質問ができる人できない人」
(中島孝志著より)
「つい口を出したくなる」のをこらえてじっと聞け。
「賢者は聞き、愚者は語る」というイスラエル王ソロモンの言葉を持ち出すまでもないが、まさに聞き上手の人ほど賢い。
ところが、頭のいいようで愚かな人間は、会議をまるで自分のワンマンショーと錯覚しているのか、周囲の意見を吸い上げない。そして最初から終わりまでしゃべり続けるのである。
逆に愚かなようでいて賢い人間は、周囲のいい分をじっくり聞き、そして判断する。
それが上手な人間関係の築き方なのである。上に立てば立つほど聞き上手でなければならないと思う。 (中略)
~松下幸之助のこと~
「ああしろ、こうしろと自分から結論を出さず、何回も根気よく質問を繰り返し、
担当者たちに徹底的に考えさせる。そして、ひとつ結論が出ると、それまでの労をねぎらう。あれほどまわりの人に感謝をした人はいない。けれども何事にも満足しなかった人もいない。
最初の頃は自分ですべてを決めて、部下に命令するというのが普通だったようです。創業オーナーなのですから、当たり前といえば当たり前です。
相談役になられてからは、責任の発生するような命令は一切せず、すべて部下に考えさせるようにされていたようです。かなりの努力が必要だったのではないでしょうか。つい、口を出したくなるものだからです」 そのときのシーンが目に浮かぶようだ。
※教育上、何かの参考になれば幸いです。
「十勝の活性化を考える会」会員