↓↓ 二つのサイトの陶芸ランキングに参加してます。バナーをポチッと応援クリックしてね! 人差し指や中指でトントン。
 人気ブログランキング
人気ブログランキング 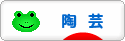 にほんブログ村
にほんブログ村


(真紀ちゃんが手びねりの復習をしている時の写真)

ー 「陶芸」 が教えてくれる 15 のしあわせ ー
第九章 : 教えるということ / その1
陶芸教室を開いて5ヶ月ほど経ってから、20代の真紀ちゃんが入会してくれた。その後も若い女の人たちが入会してくれた。その内に、中高年の女性の生徒さんも徐々に増えてきた。
足立のおばさんもその一人でした。
「私でも出来るでしょうか」 と不安そうに聞いていた。
「若い頃に絵を描くのが好きだったので、絵画か陶芸をしてみたいと思ってるのですが ・・・ 」 と、そして、
「お世話になったお客さんに、自分で作った器をあげたいのです」 と言っていた。
30数年間、釣具店に勤めて、店長をやっていたそうである。
「今も店長と言われるので困るんです」 と話していた。
(足立さんが手びねりの基礎コースの課程で作った絵付け皿)

種本の森下典子さんの著書 『日日是好日』 では、
冒頭に “武田のおばさん” という茶道の先生が登場する。
序章の 「茶人といういきもの」 の第一項は “武田のおばさん” である。
「あの人は、タダモノじゃないわよ」 という森下さんの母親の語りから始まる。
私が連載する 「日日是好日」 では、足立のおばさんに登場願った。
オーバーな表現だが、2軒先にも聞こえそうな大声でしゃべり、そして大声で笑う。
「道端の雑草のようにタクマシイのです」
生命力のある踏まれ強い雑草は、足立のおばさんの絵付けのモチーフなのです。
教室は、一段と明るく、賑やかになった。
教室では、手びねりの最初の課程で湯呑みをつくる。
手びねりの基本となる玉づくりという手法で湯呑みを2個つくるのです。
上にアップした椿の絵皿も、玉づくりで倒して広げて作った手びねりのお皿です。
400gの重さの陶土を二つ準備してもらった。粒子の目が細かい京土と言う信楽の白土です。
「土がひんやりして、気持ちがいい!」 と声をあげた。
「この土の柔らかな感触を覚えておいて下さいね」 と私は言った。さらに、
「これからは土と仲良くして下さいね。これが大事なんですよ」 と付け加えた。
陶土を野球ボールのようにまん丸くして、手ろくろの真ん中に置いてもらった。
手ろくろとは、直径が22㎝の鉄でできた円盤状の回転台です。22㎝は小型サイズの手ろくろです。
真ん中に置いたボール状の陶土を、手の平で叩いて円柱状の形にします。
そして、円柱状にした陶土の真ん中に、両手の親指を押し込んで、外側に土を寄せてドーナツ状にして行きます。電動ろくろで行う時は、これを 「土取りをする」 と言います。同じことです。
半筒型のドーナツ状に土取りをしてから、胴体の厚みを薄くしながら、高さを出して行くます。最初は、内底の際の最下段の位置で、両手の指で土を摘まんで寄せて行きます。
「両手を半筒型の陶土の向かい側に置いて下さい。両手の親指を内側に入れて下さい。人差し指、中指を外側にあてます。左右の指の間隔を10㎜くらい離して置いて下さい。そして、両手の指先でドーナツ状になった胴を摘まんでから、両手の指先で土を寄せて下さい」
「そうです、そうです。両手の指で胴を摘まんで、寄せて行くと、胴体が薄くなります。1回寄せたら少し半筒を動かしてから、また摘まんで合わせて下さい」
足立のおばさんは、言われた通りにやっていたが、次に摘まむ時に間隔があいている。飛び飛びに摘まんでいた。最初はそうなるのです。
「間隔をあけて飛び飛びにやっていると、摘ままなかったところに厚みが残りますよ。ミスタードーナツの “ポンデリング” のようになりますよ」 と注意した。
ここで笑ってくれた。緊張も少しほぐれたようだ。
私は、「ポンデリングが大好きなんですよ」 と付け加えた。本当にドーナツの中では、ポンデリングが一番好きなのである。
「手びねりは、小まめにやることが大事なんです。小まめにやっていると、均一な厚みになりますからね」 「同じ位置で3、4周して下さいね」
「最下段の一段目が薄くなってきたので、両手の位置を少し上げて、二段目に行きましょう」
「両手の位置を少し上にあげて下さい」 「二段目も同じ要領で繰り返して下さい」
「二段目は薄くなってるので、摘まんで寄せるのを2周くらいにして下さい」
「両手を一段上げる時も、間隔をあけて上げると、ドーナツを積み重ねたようになりますよ」 と私は注意した。
少し手の位置を上げてから、ピッチを狭めて摘まんで寄せる作業を繰り返してくれた。
「いいですよ」 「その調子で3段目、4段目と進んで下さい。縁まで行って下さい」
手びねりは、小まめにこまめにやっていると均一の厚みの器ができる。左右対称の器になる。手びねりは小まめにやることで、厚みが均一な正円形に近い器が出来るのです。
手びねりは、慎重に丁寧にやる人が上手です。逆に、電動ろくろでは、大胆にやる人が早く上達します。手でつくる場合と、電動ろくろという機械でつくる場合の違いがこんなところに出るのです。
陶芸のよい所は、慎重な人にも、大胆な人にも向いているということです。どんな性格の人をも迎え入れてくれるのです。陶芸の懐の広さです。
足立のおばさんは言われた通りにやっていた。言われた通りにやることが大事なことなのです。習い事を教わる時は教えられ上手になることです。それが上達への早道です。
- 次回へ続きます ー
※ 9月30日 (月) からの
NHK の朝ドラ 「スカーレット」 は
信楽焼の女性陶芸家の物語です。
愉しそう。楽しみましょう !!!
 にほんブログ村
にほんブログ村  陶芸ランキング
陶芸ランキング
↑↑ 励ましのクリックをしてあげてね!! にほんブログ村 陶芸ランキングでは1位、もう一つの陶芸ランキングでは4位です。健闘しておられます。
☆ 教室案内 : https://blog.goo.ne.jp/asuka1
☆ 自費出版 : 『生活にうるおいを与える食器づくり』
こういう本があるといい。こういう本が欲しかった。残りは数部。
 人気ブログランキング
人気ブログランキング 

(真紀ちゃんが手びねりの復習をしている時の写真)

ー 「陶芸」 が教えてくれる 15 のしあわせ ー
第九章 : 教えるということ / その1
陶芸教室を開いて5ヶ月ほど経ってから、20代の真紀ちゃんが入会してくれた。その後も若い女の人たちが入会してくれた。その内に、中高年の女性の生徒さんも徐々に増えてきた。
足立のおばさんもその一人でした。
「私でも出来るでしょうか」 と不安そうに聞いていた。
「若い頃に絵を描くのが好きだったので、絵画か陶芸をしてみたいと思ってるのですが ・・・ 」 と、そして、
「お世話になったお客さんに、自分で作った器をあげたいのです」 と言っていた。
30数年間、釣具店に勤めて、店長をやっていたそうである。
「今も店長と言われるので困るんです」 と話していた。
(足立さんが手びねりの基礎コースの課程で作った絵付け皿)

種本の森下典子さんの著書 『日日是好日』 では、
冒頭に “武田のおばさん” という茶道の先生が登場する。
序章の 「茶人といういきもの」 の第一項は “武田のおばさん” である。
「あの人は、タダモノじゃないわよ」 という森下さんの母親の語りから始まる。
私が連載する 「日日是好日」 では、足立のおばさんに登場願った。
オーバーな表現だが、2軒先にも聞こえそうな大声でしゃべり、そして大声で笑う。
「道端の雑草のようにタクマシイのです」
生命力のある踏まれ強い雑草は、足立のおばさんの絵付けのモチーフなのです。
教室は、一段と明るく、賑やかになった。
教室では、手びねりの最初の課程で湯呑みをつくる。
手びねりの基本となる玉づくりという手法で湯呑みを2個つくるのです。
上にアップした椿の絵皿も、玉づくりで倒して広げて作った手びねりのお皿です。
400gの重さの陶土を二つ準備してもらった。粒子の目が細かい京土と言う信楽の白土です。
「土がひんやりして、気持ちがいい!」 と声をあげた。
「この土の柔らかな感触を覚えておいて下さいね」 と私は言った。さらに、
「これからは土と仲良くして下さいね。これが大事なんですよ」 と付け加えた。
陶土を野球ボールのようにまん丸くして、手ろくろの真ん中に置いてもらった。
手ろくろとは、直径が22㎝の鉄でできた円盤状の回転台です。22㎝は小型サイズの手ろくろです。
真ん中に置いたボール状の陶土を、手の平で叩いて円柱状の形にします。
そして、円柱状にした陶土の真ん中に、両手の親指を押し込んで、外側に土を寄せてドーナツ状にして行きます。電動ろくろで行う時は、これを 「土取りをする」 と言います。同じことです。
半筒型のドーナツ状に土取りをしてから、胴体の厚みを薄くしながら、高さを出して行くます。最初は、内底の際の最下段の位置で、両手の指で土を摘まんで寄せて行きます。
「両手を半筒型の陶土の向かい側に置いて下さい。両手の親指を内側に入れて下さい。人差し指、中指を外側にあてます。左右の指の間隔を10㎜くらい離して置いて下さい。そして、両手の指先でドーナツ状になった胴を摘まんでから、両手の指先で土を寄せて下さい」
「そうです、そうです。両手の指で胴を摘まんで、寄せて行くと、胴体が薄くなります。1回寄せたら少し半筒を動かしてから、また摘まんで合わせて下さい」
足立のおばさんは、言われた通りにやっていたが、次に摘まむ時に間隔があいている。飛び飛びに摘まんでいた。最初はそうなるのです。
「間隔をあけて飛び飛びにやっていると、摘ままなかったところに厚みが残りますよ。ミスタードーナツの “ポンデリング” のようになりますよ」 と注意した。
ここで笑ってくれた。緊張も少しほぐれたようだ。
私は、「ポンデリングが大好きなんですよ」 と付け加えた。本当にドーナツの中では、ポンデリングが一番好きなのである。
「手びねりは、小まめにやることが大事なんです。小まめにやっていると、均一な厚みになりますからね」 「同じ位置で3、4周して下さいね」
「最下段の一段目が薄くなってきたので、両手の位置を少し上げて、二段目に行きましょう」
「両手の位置を少し上にあげて下さい」 「二段目も同じ要領で繰り返して下さい」
「二段目は薄くなってるので、摘まんで寄せるのを2周くらいにして下さい」
「両手を一段上げる時も、間隔をあけて上げると、ドーナツを積み重ねたようになりますよ」 と私は注意した。
少し手の位置を上げてから、ピッチを狭めて摘まんで寄せる作業を繰り返してくれた。
「いいですよ」 「その調子で3段目、4段目と進んで下さい。縁まで行って下さい」
手びねりは、小まめにこまめにやっていると均一の厚みの器ができる。左右対称の器になる。手びねりは小まめにやることで、厚みが均一な正円形に近い器が出来るのです。
手びねりは、慎重に丁寧にやる人が上手です。逆に、電動ろくろでは、大胆にやる人が早く上達します。手でつくる場合と、電動ろくろという機械でつくる場合の違いがこんなところに出るのです。
陶芸のよい所は、慎重な人にも、大胆な人にも向いているということです。どんな性格の人をも迎え入れてくれるのです。陶芸の懐の広さです。
足立のおばさんは言われた通りにやっていた。言われた通りにやることが大事なことなのです。習い事を教わる時は教えられ上手になることです。それが上達への早道です。
- 次回へ続きます ー
※ 9月30日 (月) からの
NHK の朝ドラ 「スカーレット」 は
信楽焼の女性陶芸家の物語です。
愉しそう。楽しみましょう !!!
 陶芸ランキング
陶芸ランキング↑↑ 励ましのクリックをしてあげてね!! にほんブログ村 陶芸ランキングでは1位、もう一つの陶芸ランキングでは4位です。健闘しておられます。
大分市内にある数少ない 陶芸教室 「夢工房あすか」 です。
意外にも近くにあるのに気付かない人たちが多いですが、
下記の教室案内をご覧下さい。陶芸を基礎からコツコツと学ぼ~う。
電動ろくろもスムーズに習得できます。
意外にも近くにあるのに気付かない人たちが多いですが、
下記の教室案内をご覧下さい。陶芸を基礎からコツコツと学ぼ~う。
電動ろくろもスムーズに習得できます。
☆ 教室案内 : https://blog.goo.ne.jp/asuka1
☆ 自費出版 : 『生活にうるおいを与える食器づくり』
こういう本があるといい。こういう本が欲しかった。残りは数部。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます