ブログを始めるにあたりメインコンテンツにしようと思っていたCDレビューですが、
ようやく第一弾です。(もちろんこの間もCDは買ってますが)
しかも、なぜかニール・セダカになってしまった…
なぜこのCDを買ったかというと、だいぶ話はさかのぼります。
高校生になってステレオコンポを買ってもらい、
レコード、CDが聴けるようにはなったものの、ソフトを大量に買えるわけでもないので
FM放送というのは相変わらず重要な音楽ソースだったわけです。
それでよく聴いていたのが、NHK-FMで平日午後4時くらいからやっていた「軽音楽をあなたに」という番組です。
パーソナリティが日替わりで、洋楽を新旧取り混ぜてオンエアーしていました。
時は1980年台半ば。MTV全盛の時代です。
中学生のときから洋楽を聴くようにはなっていましたが、
どうもその頃流行の80年代の音楽は今ひとつ好きになれなくて、
70年代のものの方が好みだったので、それを中心に聴いていました。
とある日その番組で70年代のポップスの特集があり、
エアチェック(死語)したわけですが、その中で特に印象に残ったのが
カーペンターズの「ソリティア」でした。
カーペンターズ自体はすでに知っていましたし、
その日放送された曲の多くは有名な曲が中心だったので大体知っている曲でしたが、
初めて聴いたこの曲。聴き終わったあとの深い余韻は今でも忘れません。
今でもカーペンターズの数ある曲の中で一番好きかもしれません。
それでその日の放送の最後にパーソナリティが
「カーペンターズにも曲を提供し、素晴らしいメロディを作る人」として触れていたのが
そうニール・セダカだったのです。
実は、カーペンターズの曲がかかる前にニール・セダカの「Laughter In The Rain」と
「Breaking Up Is Hard To Do」がかかっていたのですが、
歌手名を聞き逃していたのです。
エアチェックはしていたので、この後にかかったカーペンターズの曲とともに愛聴していました。
とてもキレイなメロディなんだけれど、うきうきするようなポップ感がしっかりある。
まさか「Breaking Up Is Hard To Do」が日本でもよく知られた「悲しき慕情」の
セルフカバーだなんて気づくわけがない(アレンジが全く違う)。
さらに大好きが「ソリティア」の作曲がニール・セダカだというのを知ったのは
ほんとにだいぶ後のことでした。
それで今頃になってニール・セダカのCDを買おうと思ったのは、
やはりカーペンターズの40周年記念のベスト盤を買ったのがキッカケでした。
ニール・セダカは1950年代から活躍しているのですが、
50年代のオールディーズには興味がなかったので、
彼の70年代の曲を集めたベスト盤を今回購入したわけです。
で、そのCDのジャケット写真です。

なんといっていいものやら。
しかし、収録されている曲はいいですね。
これこそアメリカンポップの王道といった感じです。
からっと明るく乾いた感じ。
アレンジは70年代ということを考えてもちょっと古臭いところがあるかな。
しかし曲、メロディは素晴らしいものがあります。
メロディーメーカーとしてのニール・セダカの才能は疑う余地がないですね。
20曲が収められていますが、やはり前述の「Laughter In The Rain」と
「Breaking Up Is Hard To Do」は珠玉のメロディといって差し支えないでしょう。
エバーグリーン、永遠の緑、そういった言葉がピッタリと当てはまります。
20年以上前FMから流れてきた曲をカセットテープに録音して繰り返し聴いていた曲を
今CDからパソコンにリッピングしてUSB-DACを介して聴いている。
なんとも不思議な感覚になりますが、曲を聴いたときの感情はあの日のまま。
音楽の素晴らしいところです。
そしてカーペンターズのカバーで有名になった「Solitaire」のオリジナルを始めて聴きました。
やはりいい曲ですが、この曲についてはカーペンターズの方がよいと思います。
リチャードのアレンジセンス、そしてなんといってもカレンのボーカリストとしての才能を
改めて思い知らされる感じです。
そしてキャプテン&テニールの「Love Will Keep Us Together」もニール・セダカの曲だったのをこのCD初めて知りました。
ライナーノーツにはニール・セダカのコメントとこのCDが1994年に発売されたときにビルボード誌に掲載された解説が載っていましたが、
1950年代の終わりから1960年代の初めにかけて成功を収めたニール・セダカが
ビートルズを初めとする「ブリティッシュ・インベーション」によってすっかり忘れ去られた存在であったのですが、彼の1970年代の復活の立役者がイギリス人であるエルトン・ジョンであったというのは皮肉なものを感じます。
実際1970年代にアメリカで出されたニール・セダカのレコードのほとんどは、エルトン・ジョンが興したロケット・レコードから発売されています。
そしてもうひとつ思うことは、メロディの時代は1970年代で終わってしまったのかなということです。
天衣無縫に書いた曲が名曲として誉めそやされた時代は、もう終わってしまったというようなことを言っていたのは、来生たかおだったでしょうか。
よいメロディが出来たと思っても、それは数十年前に誰かがとっくに発表した曲であることがでてきて、そうならないようにするためには、あえてコードやテンポを変えたりする必要がある。
現在は、ほとんどパソコン上で曲を作るようなので、こういったことはとてもやりやすくなっているのかもしれませんが、むしろパソコンがないと職業としての作曲家というのは成り立たなくなっているのでしょう。
メロディ限界論といわれて久しいですが、ニール・セダカの曲が、無理にこねくり回した感じが微塵もなく、純粋に美しいメロディと屈託のない明るさを持っているので、
そんなことを思ってしまい、少々寂しい気分になってしまいました。
そういえばグラミー賞直前特集ということで、WowWowで洋楽のライブを特集していたのですが、その中にエルトン・ジョンとレオン・ラッセルのジョイントコンサートが放送されていました。
エルトン・ジョンのアメリカでのコンサートでレオン・ラッセルと競演するという形式でしたが、レオン・ラッセルを紹介するエルトン・ジョンのMCの中で、エルビス・コステロの番組で忘れ去られた作曲家を聞かれたエルトンがA・アックルズ、ローラ・ニーロとともに名前を挙げたのがレオン・ラッセルでした。
エルトンはレオン・ラッセルと「The Union」というアルバムを作っていたのですね。

レオン・ラッセルといえば、カーペンターズつながりで、これまた名曲の「Superstar」を作曲した人です。
ニール・セダカのときといい、「達人は達人を知る」ということなのでしょうか。
ようやく第一弾です。(もちろんこの間もCDは買ってますが)
しかも、なぜかニール・セダカになってしまった…
なぜこのCDを買ったかというと、だいぶ話はさかのぼります。
高校生になってステレオコンポを買ってもらい、
レコード、CDが聴けるようにはなったものの、ソフトを大量に買えるわけでもないので
FM放送というのは相変わらず重要な音楽ソースだったわけです。
それでよく聴いていたのが、NHK-FMで平日午後4時くらいからやっていた「軽音楽をあなたに」という番組です。
パーソナリティが日替わりで、洋楽を新旧取り混ぜてオンエアーしていました。
時は1980年台半ば。MTV全盛の時代です。
中学生のときから洋楽を聴くようにはなっていましたが、
どうもその頃流行の80年代の音楽は今ひとつ好きになれなくて、
70年代のものの方が好みだったので、それを中心に聴いていました。
とある日その番組で70年代のポップスの特集があり、
エアチェック(死語)したわけですが、その中で特に印象に残ったのが
カーペンターズの「ソリティア」でした。
カーペンターズ自体はすでに知っていましたし、
その日放送された曲の多くは有名な曲が中心だったので大体知っている曲でしたが、
初めて聴いたこの曲。聴き終わったあとの深い余韻は今でも忘れません。
今でもカーペンターズの数ある曲の中で一番好きかもしれません。
それでその日の放送の最後にパーソナリティが
「カーペンターズにも曲を提供し、素晴らしいメロディを作る人」として触れていたのが
そうニール・セダカだったのです。
実は、カーペンターズの曲がかかる前にニール・セダカの「Laughter In The Rain」と
「Breaking Up Is Hard To Do」がかかっていたのですが、
歌手名を聞き逃していたのです。
エアチェックはしていたので、この後にかかったカーペンターズの曲とともに愛聴していました。
とてもキレイなメロディなんだけれど、うきうきするようなポップ感がしっかりある。
まさか「Breaking Up Is Hard To Do」が日本でもよく知られた「悲しき慕情」の
セルフカバーだなんて気づくわけがない(アレンジが全く違う)。
さらに大好きが「ソリティア」の作曲がニール・セダカだというのを知ったのは
ほんとにだいぶ後のことでした。
それで今頃になってニール・セダカのCDを買おうと思ったのは、
やはりカーペンターズの40周年記念のベスト盤を買ったのがキッカケでした。
ニール・セダカは1950年代から活躍しているのですが、
50年代のオールディーズには興味がなかったので、
彼の70年代の曲を集めたベスト盤を今回購入したわけです。
で、そのCDのジャケット写真です。

なんといっていいものやら。
しかし、収録されている曲はいいですね。
これこそアメリカンポップの王道といった感じです。
からっと明るく乾いた感じ。
アレンジは70年代ということを考えてもちょっと古臭いところがあるかな。
しかし曲、メロディは素晴らしいものがあります。
メロディーメーカーとしてのニール・セダカの才能は疑う余地がないですね。
20曲が収められていますが、やはり前述の「Laughter In The Rain」と
「Breaking Up Is Hard To Do」は珠玉のメロディといって差し支えないでしょう。
エバーグリーン、永遠の緑、そういった言葉がピッタリと当てはまります。
20年以上前FMから流れてきた曲をカセットテープに録音して繰り返し聴いていた曲を
今CDからパソコンにリッピングしてUSB-DACを介して聴いている。
なんとも不思議な感覚になりますが、曲を聴いたときの感情はあの日のまま。
音楽の素晴らしいところです。
そしてカーペンターズのカバーで有名になった「Solitaire」のオリジナルを始めて聴きました。
やはりいい曲ですが、この曲についてはカーペンターズの方がよいと思います。
リチャードのアレンジセンス、そしてなんといってもカレンのボーカリストとしての才能を
改めて思い知らされる感じです。
そしてキャプテン&テニールの「Love Will Keep Us Together」もニール・セダカの曲だったのをこのCD初めて知りました。
ライナーノーツにはニール・セダカのコメントとこのCDが1994年に発売されたときにビルボード誌に掲載された解説が載っていましたが、
1950年代の終わりから1960年代の初めにかけて成功を収めたニール・セダカが
ビートルズを初めとする「ブリティッシュ・インベーション」によってすっかり忘れ去られた存在であったのですが、彼の1970年代の復活の立役者がイギリス人であるエルトン・ジョンであったというのは皮肉なものを感じます。
実際1970年代にアメリカで出されたニール・セダカのレコードのほとんどは、エルトン・ジョンが興したロケット・レコードから発売されています。
そしてもうひとつ思うことは、メロディの時代は1970年代で終わってしまったのかなということです。
天衣無縫に書いた曲が名曲として誉めそやされた時代は、もう終わってしまったというようなことを言っていたのは、来生たかおだったでしょうか。
よいメロディが出来たと思っても、それは数十年前に誰かがとっくに発表した曲であることがでてきて、そうならないようにするためには、あえてコードやテンポを変えたりする必要がある。
現在は、ほとんどパソコン上で曲を作るようなので、こういったことはとてもやりやすくなっているのかもしれませんが、むしろパソコンがないと職業としての作曲家というのは成り立たなくなっているのでしょう。
メロディ限界論といわれて久しいですが、ニール・セダカの曲が、無理にこねくり回した感じが微塵もなく、純粋に美しいメロディと屈託のない明るさを持っているので、
そんなことを思ってしまい、少々寂しい気分になってしまいました。
そういえばグラミー賞直前特集ということで、WowWowで洋楽のライブを特集していたのですが、その中にエルトン・ジョンとレオン・ラッセルのジョイントコンサートが放送されていました。
エルトン・ジョンのアメリカでのコンサートでレオン・ラッセルと競演するという形式でしたが、レオン・ラッセルを紹介するエルトン・ジョンのMCの中で、エルビス・コステロの番組で忘れ去られた作曲家を聞かれたエルトンがA・アックルズ、ローラ・ニーロとともに名前を挙げたのがレオン・ラッセルでした。
エルトンはレオン・ラッセルと「The Union」というアルバムを作っていたのですね。

レオン・ラッセルといえば、カーペンターズつながりで、これまた名曲の「Superstar」を作曲した人です。
ニール・セダカのときといい、「達人は達人を知る」ということなのでしょうか。












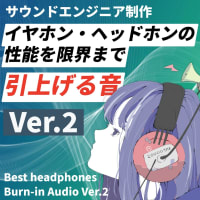







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます