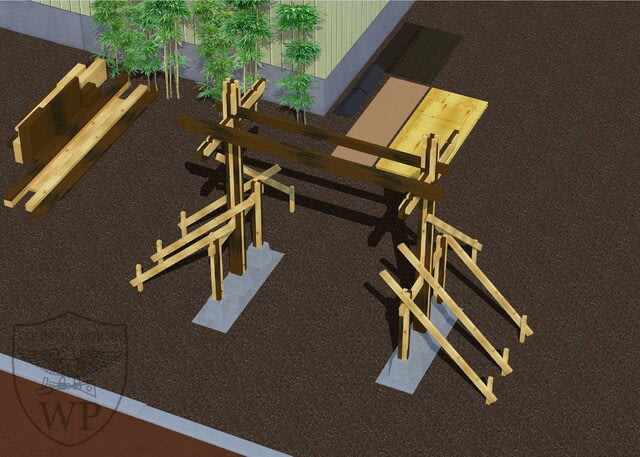今日(3/12)は、昨日(3/11)以上に暖かです
気温は昨日と変わりませんが・・・?
建物自体が一気に温まったのか
午前中だけのストーブもなしで過ごせています
(六十年物の土壁はカラッカラで良く冷え、良く温まります⁈)
さて、今週も建込を続けて行きます

先週土曜日に軒桁Lを取付けたので
今日はその軒桁Lに沿わせて取付ける
軒桁Sを取付けます
軒桁Lの長さが2350mmで、軒桁Sが2240mmですから
長さの差の半分の55mm(なぜこんな中途半端な数字⁈)を
軒桁Lの木口から取って墨を付けておき
軒桁Sの木口をこの墨に合わせながら、梁の上え置き
まずは、軒桁Sの正面側から、梁の上向きの木刃へ向かって
65mmのコーススレッドを斜め打ちに打ち込んで
取敢えず位置が動かない様に止めたら
裏側へ廻って、軒桁Lの横面から≒300ピッチ程度で
(センターで150づつ割り振って、そこから300の追い出しで、端が70?下は大丈夫?)
軒桁Lの上側の木刃からは20mm下がり程度
軒桁Lの下側の木刃からは70mm程度の位置へ
65mmのコーススレッドを打込んで止めてやります
この時、以前にも書きましたが
コーススレッドに押されて、軒桁LとSの間に
隙間が出来てしまう事が有るので
バイス等で二材をシッカリと挟んで置いてから
コーススレッドを打込んで行くのが良いかと思います
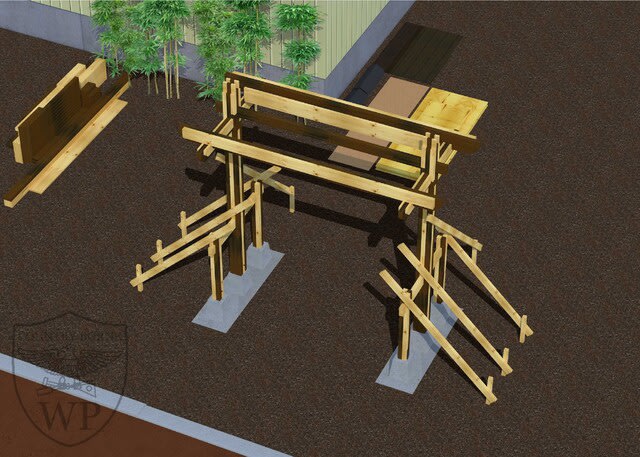
で、軒桁Sが取付けられたら
続いて、添桁としたおかしな名前の部材を取付けてやります
材料は1x6で、長さは一様1686mmとして有りますが
念のため取付前に現物を測って確認して
柱間が多少狭い場合は、叩き込むか、切り直して
広い場合は目を瞑るか・・・材料を追加で買いに走って下さい

で、これも軒桁と同様に
≒300ピッチで、今度は上下とも添桁の木刃から
45mm当たりの位置へ45mmのコーススレッドを打込んで
(センターから300づつ割り振って両端が93mm残りかな?)
止めてやります
と言う事で、片側だけで何やら中途半端ですが
今日はここまでですm(__)m
(諸事情が有るのでね?)
週明け、ウクライナ問題はどうなっているのでしょう
大国間で生物兵器だの化学兵器だの言ってますが?
とあるNEWSでは、この事態の落としどころは何処なんだろう
等と言う事が書いて有りましたが
ホント!後始末をどうするつもりなのか?
自分で抜いた刃物は、自分で仕舞えよ!
(by 北方謙三?的な感じ?)
・・・では又明日ですm(__)m