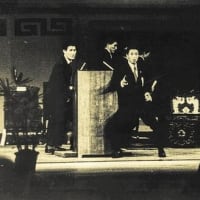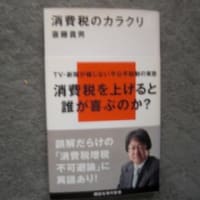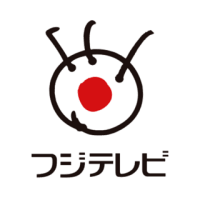『冬の夜』は1912年(明治45年)の文部省唱歌で、もう1世紀以上も昔になる。ほのぼのとした一家団らんの様子が伝わってくるようだ。
なお、末尾に少し長くなるが、2008年10月4日に「二木紘三のうた物語」に寄せた一文を載せておきたい。
https://www.youtube.com/watch?v=wf0n0_oo9AI
☆ この歌を聴いていると、亡き母を思い出します。母が生まれたのは明治37年末の日露戦争の真っ最中でしたが、子供のころ「父(私の祖父)からずいぶん日露戦争の話を聞いた」と語っていました。
また、子供の間で流行った尻取りの“手まり唄”をよく歌っていたので、私もほとんどそれを覚えてしまいました。『冬の夜』が出来たころの女の子の歌ですが、これも「文化」の一つだと思うので、紹介させてください。
『にっぽんの 乃木さんが 凱旋す スズメ メジロ ロシヤ 野蛮国 クロパトキン 金の玉 負けて逃げるはチャンチャンボウ 棒で叩くは犬殺し 死んでも命があるように・・・・・』
最後の方は少し卑猥な表現になるので、省略します。乃木さんはもちろん乃木大将のこと、クロパトキンはロシア軍のクロポトキン総司令官のことで、チャンチャンボウはたしか、当時の中国人を蔑視した言葉です。
母たちは『冬の夜』を歌いながらも、こうした時代背景がすぐに分かる手まり唄も歌っていたのです。
昭和も遠くなりにけりですが、明治はさらに忘却の彼方へ去っていきますね。長い駄文、大変失礼しました。
投稿: 矢嶋武弘 | 2008年10月 4日 (土) 15時15分