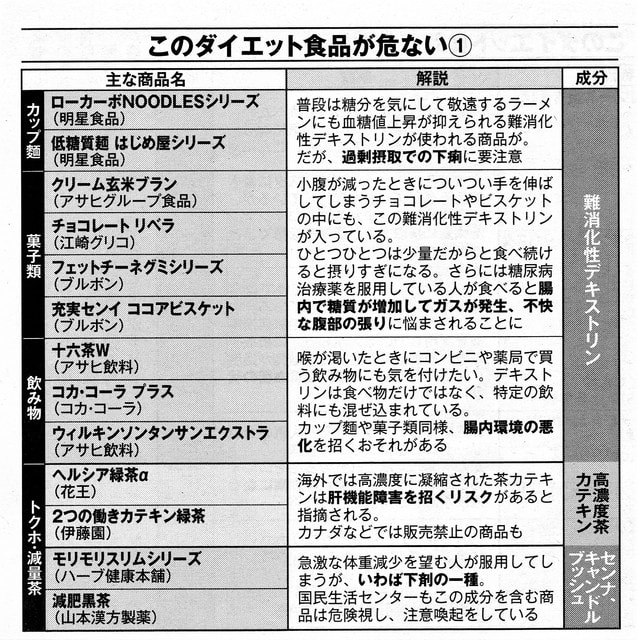恐らく生まれて初めて本格的なダイエットをした。
コロナ禍の巣ごもり生活の影響もあり、自分史上最高体重を更新し続け、心臓に負担が増えたため、医者から痩せるようにと言われた。それが6月のこと。
栄養士さんの助言を受け、早速減量を試みる。
減量するためには基礎代謝を上げる必要がある。基礎代謝を上げるには筋肉を鍛えなければいけない。
ずっと、週に一度水泳をしていたが、コロナの影響でしばらくお休みしていた。週に一度2000メートル泳いでいたが、運動は短時間でも毎日した方が効果的だそうだ。
基礎代謝を上げるには人間の体の中で一番大きな太腿の筋肉を鍛えるのが最も効率的。よくお腹を凹ませるために腹筋をする人がいるが、腹筋の筋肉はそれほど大きくなく、基礎代謝を上げるには不十分だそうだ。水泳も腕の筋肉は鍛えることができるが太腿の筋肉はそれほど鍛えられない。
お勧めを訊くとスクワットやエアロバイクがいいと言う。
ジョギングやウォーキングも効果的だが、ジョギングは膝を痛めるリスクがある。
長く続けるために、スクワットはきついのでエアロバイクをすることにした。
ホームセンターでエアロバイクを購入して寝室に何とか設置する。これならテレビを観たり、音楽を聴きながらでもできるので長続きしそうである。
天気のいい休日は1~2時間のウォーキング、平日はエアロバイクを15分ほど。エアロバイクはスピードメーターを見ながら時速20~25キロを維持するようにした。
栄養士さんに食べ物のことも訊いた。
糖質を控えるようにと言われる。但し、あまりに糖質を制限すると認知症になるリスクが高まるそうである、糖質は脳の主な栄養なので、あまり制限すると脳の活動に影響するらしい。朝はパンなので、昼と夜、一食のご飯の量を150グラムにするといいと指導を受ける。炊きあがったご飯一合が330グラムなので、その半分くらい。それほど無理な量ではない。カロリーは1日に1600キロカロリー以下にすることが望ましいそうだ。朝昼晩、1食のだいたいのカロリーを計算する。夜は妻に協力してもらい、昼はチェーン店など、ホームページなどでなるべくカロリーがわかる店を使うようにした。
すでに減塩、低コレステロールの食事にはしていたが、さらにカロリーも制限することに。
でも、やってみるとそれほど無理な生活ではない。
注意点もある。
食事だけで減量すると筋肉量も減る。筋肉量が低下すると免疫力も低下してしまう。運動と並行することはとても大切なことなのだ。
あと、減量すると骨も痩せてしまう。そうすると骨粗鬆症のリスクが高まるので、ヨーグルトなどのカルシウムを毎日摂るようにとアドバイスされる。
それから5か月。10キロ以上の減量に成功。
前の健康診断では色んな数値が悪化していた。次の健康診断では少しはよくなっているかな。