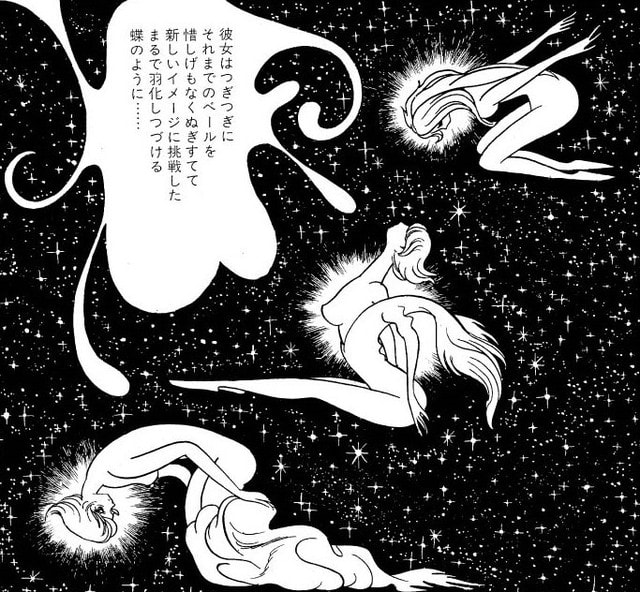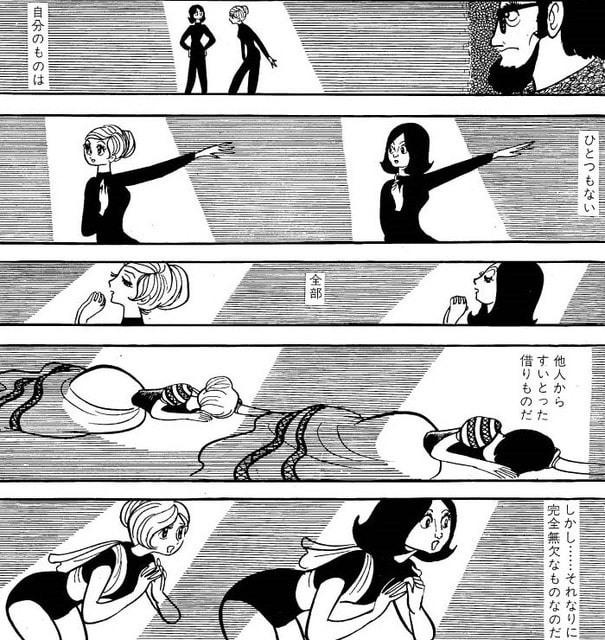花粉症について医師の森田豊氏が医学的見地に基づいた情報をTBSラジオ『ジェーン・スー生活は踊る』で紹介していた。今年は例年に比べ、ややスギ花粉が多いそうである。
・子供の頃プールでよく遊んでいた人は花粉症になりやすい。
プールに使用されている塩素化合物の刺激を慢性的に受けると様々なアレルギー疾患の原因となる。ドイツでの研究によると学童時代に頻繁にプールに通っていた人はそうでない人より74パーセントも多いそうだ。但し、現在のプールはそれほど塩素濃度は高くないのでそれほど心配は要らない。
・人差し指が薬指より長い人は花粉症になりやすい。
お母さんのおなかの中にいるときは女性ホルモン、男性ホルモン、両方にさらされているが、女性ホルモンの影響が強い人ほど人差し指が薬指より長くなるとされている。女性ホルモンの影響が強い人ほどアレルギーになりやすいそうだ。
・バナナは花粉症の症状を軽くすると考えられている。
筑波大学の研究チームによると、スギ花粉症の人に3週間くらい継続的にバナナを食べてもらったところ、くしゃみなどの症状がよくなったと報告されている。バナナに含まれるビタミンB6やセロトニンなどが関与していると考えられている。
・生トマトにはヒスタミンが含まれていて炎症を助長してしまうので花粉症には良くないが、加工用のトマト、例えばトマトジュースやケチャップなどのトマトにはポリフェノールが多く含まれるので花粉症の症状を緩和してくれるそうだ。
・花粉症の人は癌になりにくい。
花粉症の人は癌で死亡するリスクが52パーセントも少なくなるという統計結果がある。花粉症の人は免疫が活発に働いているからだろうと考えられている。
・歳をとると、花粉症が治ることが多い。
歳とともに免疫力が落ち着くせいか、年齢とともに花粉症の割合は減っていくそうだ。花粉症の人は50代で33パーセント、70代で11パーセントという報告がある。
・花粉症は遺伝しない。
アレルギー体質そのものは遺伝すると考えられているが、花粉症に関してはなりやすい遺伝子は解っていない。統計的にも親が花粉症なので子供も花粉症になりやすいという結果は出ていないそうだ。