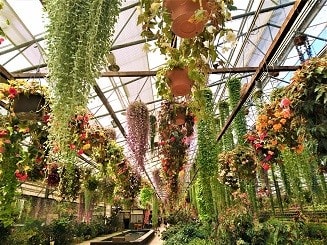ファン・ルルフォ著『燃える平原』は、「おれたちのもらった土地」「コマドレス坂」「おれたちは貧しいんだ」「追われる男」「明け方に」「タルパ」「マカリオ」「燃える平原」「殺さねえでくれ」「ルビーナ」「置いてきぼりにされた夜」「北の渡し」「覚えてねえか」「犬の声は聞こえんか」「大震災の日」「マティルデ・アルカンヘルの息子」「アナクレト・モローネス」の17篇からなる短編集。
革命前後のメキシコを舞台に騒乱と暴力の世界に生きる農夫たちを感傷と修辞を排した乾いた文体で描く。
ルルフォは生涯に『燃える平原』と『ペドロ・パラモ』のたった二つの著作しか残さなかったが、ラテンアメリカ文学の最も重要な作家の一人であるという評価を得ている。
メキシコ文学を読むのは、カルロス・フエンテス著『アウラ・純な魂』『遠い家族』に次いで3作目だが、フエンテスの作風が幽玄で幻想的であるのに対し、ルルフォの作風はメキシコの大地そのもののように熱く荒涼として暴力的だ。
ルルフォは実体験から離れられない作家で、それ故に多くの作品を残すことが出来なかった。生涯でたった二作の彼の作品は、一行一句すべてが彼の血と肉で出来ていると言えよう。ルルフォ自身がメキシコ革命の激戦地アプルコで生まれ育っているので、メキシコ革命やその後の混乱の描写が距離感ゼロで生々しい。モラトリウムとは無縁の魂の強さを感じた。
「農地に火を放たれ、父親や祖父、父親の兄弟、みんな殺された」ルルフォは、十歳になる前に母親も亡くし、その後は祖母に引き取られ、やがて孤児院に入れられた。ルルフォの作品に共通する暴力の嵐や突発的な死、それに伴う孤独や怨念は、ルルフォ自身の生い立ちを原風景としている。
不幸でない人間、悲惨でない人間は一人もいない。だから、それは非道の言い訳にはならない。そもそも言い訳をしようという発想すらない。
この地では子供が一人前になるのが早い。
おっぱいを飲んでいるかと思ったら、次の日にはもう鍬を握っている。そしてあっという間にどこかへ行ってしまう。そんな感じで、一生の流れが酷く速い。
役人から痩せた土地をあてがわれ強制的に移住させられる農夫たち。復讐のために旅を続け、復讐を果たした後は自らが復讐者に追われる立場になる男。父親の死体を馬に乗せハーモニカを吹きながら帰路に就く息子。全身から黄色い粘液を垂らしながら聖地を目指す巡礼者。乳房の重みで堕落の底へと沈んでいく商売女たち……焼けつくような日差しが照り付ける荒野を人々は行き交う。
積み上げられた死体の山から燃え上がる炎。赤く染まった歯を唇の間から覗かせて、まだ生きている仲間たちをあざ笑っているかのような死体。道端の棒杭に吊るされたまま干からび、しわしわに縮れた死体。殺され棄てられてすぐに無数の禿鷹が舞い降りる死体……17篇の殆どに死体の描写が出てくる。理不尽な死が日常のこの地では、生きている人間よりも死人の方がよっぽど重たい。そんな悲惨の極みのような世界で、それでも人々は死ぬまでの人生をもがきながら生きるのだ。
「タルパ」は、疫病に侵された兄を兄の妻と共に巡礼地タルパに葬った男の話。
物語はタルパから故郷センソントラに戻ったおれと兄嫁のナターリアの場面から始まる。
おれたちは兄のタニーロの亡骸をタルパに埋めてきたのだ。
嫌な死臭をまき散らし、思わず目をそむけたくなるような遺体だった。体中の爛れから黄色い液が滲み出していた。遺体に群がる青蠅の唸りはまるでタニーロの口から漏れ出る鼾のようだった。息がしたくてもがいているみたいに見えた。まだ苦痛に苛まされているように手足を引きつらせ、目を大きく見開いて、自分の死を睨んでいるようだった。
タルパの聖母様の前に立てば病気などすっかり治る。痛みはあとかたもなく消える。タニーロはそう信じていた。おれたちはそこに付け込んで、タニーロをタルパに連れて行った。道中でタニーロの手足の爛れが裂け、血と腐った液が滴った。タニーロはセンソントラに引き返したがったが、おれたちは強引に前に進ませた。
おれたちはタニーロの死をのぞんでいた。
おれたちはタニーロの目の届かないところで体をまさぐり合っていた。タニーロを聖母のもとに連れて行くと言いながら、おれたちはタルバに向かう道々でそんなことをしていたのだ。
タルパに続く砂塵に包まれた街道を、おれたちは群衆にもまれながら、太陽に焼かれながら、蛆虫のように蠢きながら、少しずつ進んでいった。
タニーロの足の肉は裂け血が流れ出し、ふいに腐ったようなにおいをドッと吹き出していたが、おれたちはこれっぽちの憐みも感じられなくなっていた。この分だとまだまだ死にそうになかった。何としてでもタニーロをタルパまで引っ張っていかねばと思うのだった。
タニーロは跪き膝の骨で地面を擦りながら進んでいった。見るからに異様な肉塊となり、体中湿布だらけで、あちこちに黒ずんだ血がこびりいており、彼が通った後には腐乱した動物の死骸を思わせる饐えた臭いが漂った。
そんなタニーロを引きずって、おれたちは聖歌を謳いながらタルパに入っていったのだ。
タニーロはタルパで死んだ。
目論見通りになったというのに、おれたちは永遠に心の安らぎを失ってしまった。
ナターリアは酷く悔やみ、死んだ亭主の為に頻りに涙を流す。後悔の念に駆られる自分の姿をあの世の亭主に見てもらいたいのかもしれない。おれを見る時のあの目の輝きはどこかに消えてしまった。ナターリアにとってタニーロがすべてになった。
おれもそうだ。ここにはタニーロの思い出がいっぱい詰まっていて、四六時中後悔の念に苛まされるのだ。
この分だとおれたちは互いに相手を恐れるようになるのかもしれない。
何だか目的地にまだ辿り着いていないような気がする。ここはまだ通りすがりの場所で、じきにまた歩き続けねばならないような感じだ。何処に行くべきなのか見当もつかないけれど、とにかく先へ行かねばならないのだ。
死体の上にしっかりと土を盛り、石をいっぱい乗せる描写は、「アナクレト・モローネス」にも出てくる。
しかし、「アナクレト・モローネス」の主人公は、良心の呵責や自責の念に駆られるところがいっさいない。彼が埋めたのはただの肉塊で、それに付随する思いは何もない。
人々に聖人のように信仰されていたアナクレト・モローネスは、実はとんでもないペテン師だった。
物語は突然失踪した新興宗教の教祖アナクレト・モローネスを探し求める信者の女たちが、弟子で娘婿のルカス・ルカテロのもとを訪ねてくるところから始まる。
ルカス・ルカテロは師匠がろくでなしなことを知っている。そして、彼が今どこにいるかも。
女たちへのルカスの対応が酷過ぎる。あんまり酷過ぎるので読みながら何度も笑ってしまった。
ルカスはアナクレト・モローネス以上のクズ男で、女をたぶらかすことにも人を殺すことにも罪の意識は一切ない。その冷めた感覚から放たれる毒舌は清々しくさえあった。
「犬の声は聞こえんか」では、老いた父親が瀕死の息子を背負って町を目指し荒野を歩く。
イグナシオは、何一つ思い通りにならなかった息子だった。
だがこの体がガタガタになっても、どうしても息子をトヤナに連れて行きたいのだ。医者に手当てをしてもらったって、傷が治ったらすぐにまた悪の道に戻るのだろうけれど。
どこか遠くに行けばいい。二度と顔を見なくて済むようなところに消えればいい。こんなろくでなしに自分の血が流れていることが情けなくて悔しい。息子は山賊に身を落として、何の罪もない人たちを殺した。その中には名付け親さえいた。
父親は息子を背負いながら、息子が赤ん坊だっだ時のことを思い出す。
こんな気性の荒い、乱暴な人間になるとは、夢にも思っていなかった。夫婦で一人息子を大切に育てて来たつもりだったけど、何か恨みがあるみたいな仕打ちしか受けなかった。妻はもう死んだが、たとえ生きていたとしても結局は息子に殺されただろう。
膝が曲がって、息子の重みに押しつぶされそうだが、気力を振り絞って歩き続ける。
町が近づいたことを知らせる犬の吠える声が聞こえてくる。だけど、背中の息子は既に息絶えていた。父親は首に絡みついた息子の指をひとつひとつ外しながら呟く。
“「これが聞こえなかったのか、イグナシオ」と老人は言った。「おまえってやつはこんなちっぽけな希望さえわしに与えちゃくれなかったな」”
革命前後のメキシコを舞台に騒乱と暴力の世界に生きる農夫たちを感傷と修辞を排した乾いた文体で描く。
ルルフォは生涯に『燃える平原』と『ペドロ・パラモ』のたった二つの著作しか残さなかったが、ラテンアメリカ文学の最も重要な作家の一人であるという評価を得ている。
メキシコ文学を読むのは、カルロス・フエンテス著『アウラ・純な魂』『遠い家族』に次いで3作目だが、フエンテスの作風が幽玄で幻想的であるのに対し、ルルフォの作風はメキシコの大地そのもののように熱く荒涼として暴力的だ。
ルルフォは実体験から離れられない作家で、それ故に多くの作品を残すことが出来なかった。生涯でたった二作の彼の作品は、一行一句すべてが彼の血と肉で出来ていると言えよう。ルルフォ自身がメキシコ革命の激戦地アプルコで生まれ育っているので、メキシコ革命やその後の混乱の描写が距離感ゼロで生々しい。モラトリウムとは無縁の魂の強さを感じた。
「農地に火を放たれ、父親や祖父、父親の兄弟、みんな殺された」ルルフォは、十歳になる前に母親も亡くし、その後は祖母に引き取られ、やがて孤児院に入れられた。ルルフォの作品に共通する暴力の嵐や突発的な死、それに伴う孤独や怨念は、ルルフォ自身の生い立ちを原風景としている。
不幸でない人間、悲惨でない人間は一人もいない。だから、それは非道の言い訳にはならない。そもそも言い訳をしようという発想すらない。
この地では子供が一人前になるのが早い。
おっぱいを飲んでいるかと思ったら、次の日にはもう鍬を握っている。そしてあっという間にどこかへ行ってしまう。そんな感じで、一生の流れが酷く速い。
役人から痩せた土地をあてがわれ強制的に移住させられる農夫たち。復讐のために旅を続け、復讐を果たした後は自らが復讐者に追われる立場になる男。父親の死体を馬に乗せハーモニカを吹きながら帰路に就く息子。全身から黄色い粘液を垂らしながら聖地を目指す巡礼者。乳房の重みで堕落の底へと沈んでいく商売女たち……焼けつくような日差しが照り付ける荒野を人々は行き交う。
積み上げられた死体の山から燃え上がる炎。赤く染まった歯を唇の間から覗かせて、まだ生きている仲間たちをあざ笑っているかのような死体。道端の棒杭に吊るされたまま干からび、しわしわに縮れた死体。殺され棄てられてすぐに無数の禿鷹が舞い降りる死体……17篇の殆どに死体の描写が出てくる。理不尽な死が日常のこの地では、生きている人間よりも死人の方がよっぽど重たい。そんな悲惨の極みのような世界で、それでも人々は死ぬまでの人生をもがきながら生きるのだ。
「タルパ」は、疫病に侵された兄を兄の妻と共に巡礼地タルパに葬った男の話。
物語はタルパから故郷センソントラに戻ったおれと兄嫁のナターリアの場面から始まる。
おれたちは兄のタニーロの亡骸をタルパに埋めてきたのだ。
嫌な死臭をまき散らし、思わず目をそむけたくなるような遺体だった。体中の爛れから黄色い液が滲み出していた。遺体に群がる青蠅の唸りはまるでタニーロの口から漏れ出る鼾のようだった。息がしたくてもがいているみたいに見えた。まだ苦痛に苛まされているように手足を引きつらせ、目を大きく見開いて、自分の死を睨んでいるようだった。
タルパの聖母様の前に立てば病気などすっかり治る。痛みはあとかたもなく消える。タニーロはそう信じていた。おれたちはそこに付け込んで、タニーロをタルパに連れて行った。道中でタニーロの手足の爛れが裂け、血と腐った液が滴った。タニーロはセンソントラに引き返したがったが、おれたちは強引に前に進ませた。
おれたちはタニーロの死をのぞんでいた。
おれたちはタニーロの目の届かないところで体をまさぐり合っていた。タニーロを聖母のもとに連れて行くと言いながら、おれたちはタルバに向かう道々でそんなことをしていたのだ。
タルパに続く砂塵に包まれた街道を、おれたちは群衆にもまれながら、太陽に焼かれながら、蛆虫のように蠢きながら、少しずつ進んでいった。
タニーロの足の肉は裂け血が流れ出し、ふいに腐ったようなにおいをドッと吹き出していたが、おれたちはこれっぽちの憐みも感じられなくなっていた。この分だとまだまだ死にそうになかった。何としてでもタニーロをタルパまで引っ張っていかねばと思うのだった。
タニーロは跪き膝の骨で地面を擦りながら進んでいった。見るからに異様な肉塊となり、体中湿布だらけで、あちこちに黒ずんだ血がこびりいており、彼が通った後には腐乱した動物の死骸を思わせる饐えた臭いが漂った。
そんなタニーロを引きずって、おれたちは聖歌を謳いながらタルパに入っていったのだ。
タニーロはタルパで死んだ。
目論見通りになったというのに、おれたちは永遠に心の安らぎを失ってしまった。
ナターリアは酷く悔やみ、死んだ亭主の為に頻りに涙を流す。後悔の念に駆られる自分の姿をあの世の亭主に見てもらいたいのかもしれない。おれを見る時のあの目の輝きはどこかに消えてしまった。ナターリアにとってタニーロがすべてになった。
おれもそうだ。ここにはタニーロの思い出がいっぱい詰まっていて、四六時中後悔の念に苛まされるのだ。
この分だとおれたちは互いに相手を恐れるようになるのかもしれない。
何だか目的地にまだ辿り着いていないような気がする。ここはまだ通りすがりの場所で、じきにまた歩き続けねばならないような感じだ。何処に行くべきなのか見当もつかないけれど、とにかく先へ行かねばならないのだ。
死体の上にしっかりと土を盛り、石をいっぱい乗せる描写は、「アナクレト・モローネス」にも出てくる。
しかし、「アナクレト・モローネス」の主人公は、良心の呵責や自責の念に駆られるところがいっさいない。彼が埋めたのはただの肉塊で、それに付随する思いは何もない。
人々に聖人のように信仰されていたアナクレト・モローネスは、実はとんでもないペテン師だった。
物語は突然失踪した新興宗教の教祖アナクレト・モローネスを探し求める信者の女たちが、弟子で娘婿のルカス・ルカテロのもとを訪ねてくるところから始まる。
ルカス・ルカテロは師匠がろくでなしなことを知っている。そして、彼が今どこにいるかも。
女たちへのルカスの対応が酷過ぎる。あんまり酷過ぎるので読みながら何度も笑ってしまった。
ルカスはアナクレト・モローネス以上のクズ男で、女をたぶらかすことにも人を殺すことにも罪の意識は一切ない。その冷めた感覚から放たれる毒舌は清々しくさえあった。
「犬の声は聞こえんか」では、老いた父親が瀕死の息子を背負って町を目指し荒野を歩く。
イグナシオは、何一つ思い通りにならなかった息子だった。
だがこの体がガタガタになっても、どうしても息子をトヤナに連れて行きたいのだ。医者に手当てをしてもらったって、傷が治ったらすぐにまた悪の道に戻るのだろうけれど。
どこか遠くに行けばいい。二度と顔を見なくて済むようなところに消えればいい。こんなろくでなしに自分の血が流れていることが情けなくて悔しい。息子は山賊に身を落として、何の罪もない人たちを殺した。その中には名付け親さえいた。
父親は息子を背負いながら、息子が赤ん坊だっだ時のことを思い出す。
こんな気性の荒い、乱暴な人間になるとは、夢にも思っていなかった。夫婦で一人息子を大切に育てて来たつもりだったけど、何か恨みがあるみたいな仕打ちしか受けなかった。妻はもう死んだが、たとえ生きていたとしても結局は息子に殺されただろう。
膝が曲がって、息子の重みに押しつぶされそうだが、気力を振り絞って歩き続ける。
町が近づいたことを知らせる犬の吠える声が聞こえてくる。だけど、背中の息子は既に息絶えていた。父親は首に絡みついた息子の指をひとつひとつ外しながら呟く。
“「これが聞こえなかったのか、イグナシオ」と老人は言った。「おまえってやつはこんなちっぽけな希望さえわしに与えちゃくれなかったな」”

















 <
<