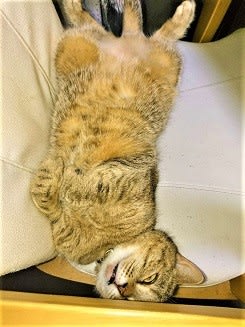木曜日は、コメガネの小学校の冬の社会科見学でした。
行き先は、国会議事堂と科学技術館の二本立て。良い組み合わせですね。

今回のお弁当。
メインは、鶏ひき肉とお豆腐の和風ハンバーグ。ひじきと枝豆入り。醬油ベースのあんかけです。
それから、南瓜とクリームチーズのサラダ、カラーピーマンとツナの炒め物、おにぎり。デザートは苺。
因みに春の社会科見学は鎌倉でした。
6年生は遠足がない代わりに、社会科見学が2回あるのですね。5ヶ月も前のことなので忘れていましたよ。
それにしても、社会科見学で国会議事堂とはコメガネが羨ましい。
私は小学5年生まで都内住みだったのですが、春休みに親の転勤のため転校になってしまい、国会議事堂見学には行けなかったのですよね。確か、「6年の社会科見学は国会議事堂だ」って先生から言われて、楽しみにしていた記憶があるのですが。
大人になってから、国会議事堂は当日に現地で申し込みをすれば、誰でも見学できると知ったのですが、やはり学校の行事で行っておきたかったです。その年頃でしか味わえないワクワク感があると思うので。
コメガネも国会議事堂は相当楽しみだったようで、当日の朝もテレビニュースに国会議事堂が映っていたのを、「今日、ここ行くから」と見入っていました。
帰って来てから、色々話してくれましたよ。
国会議員に会えたことと、総理大臣の席を見ることが出来たのが、嬉しかったみたいです。他は、「シャンデリアやステンドグラスが宮殿みたいだった」とか「大理石と化石が綺麗だった」など、内装のことばかりなのが女の子らしい感想。「お母さんも今度一緒に行こう」とも言っていました。
科学技術館は、乗り物に乗ったり実験に参加できたりするコーナーがたくさんあって飽きなかったそうです。
コメガネは、視覚の錯覚を体験するコーナーとドライビングシミュレーターが気に入ったそうで、こちらもまた訪れたいと言っていました。
私は科学技術館も行ったことないのですが、HPを閲覧してみたら大人が見学しても面白そうなところでした。機会があったら行ってみたいですね。
HPには、おすすめ見学コースがいくつか紹介されていますが、科学の原理発見コース、生活の科学発見コース、最先端科学発見コースが特に面白そう。時間をかけてじっくり見学したいです。