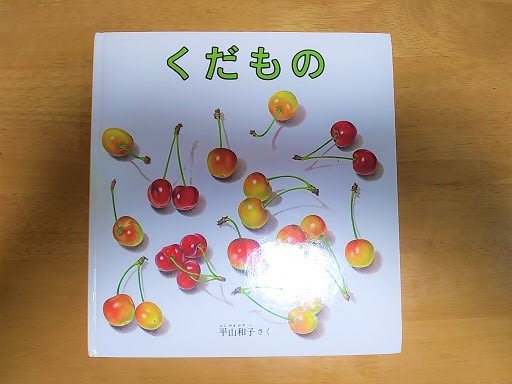25日が夫の誕生日だったので、お家でお祝いしました。
今回のメニューは、ステーキ、クラムチャウダー、カボチャとサツマイモのサラダ、マンゴーラッシー、パン、苺のチーズケーキです。

苺のチーズケーキ。

苺を砂糖とレモン汁で煮詰めて、緩めのジャムにします。

ジャムをレアチーズの生地に混ぜて、砕いたクッキーを敷き詰めた型に流し込みます。

170度のオーブンで焼き上げた直後。

例によって、料理を作りすぎたので、ケーキは翌日のおやつの時間に食べました。

ステーキ。
キャロットグラッセと、ジャガイモと椎茸の素揚げを添えて。

具だくさんのクラムチャウダー。

カボチャとサツマイモのサラダ。

マンゴーラッシー。


夫へのプレゼントは、薄手のジャケットです。
私の好みで選ぶと、夫的には少し派手に感じるそうなので、今回はなるべく落ち着いたデザインのものを選びました。いつもよりも喜んでもらえたので、嬉しいやら申し訳ないやら。


お安くなっていたので、ワンピースも買っちゃいました。
娘と私との共用です。シンプルなデザインなので、ベルトやアクセサリー、ストールなどで色んなコーデを楽しみたいです。

キャップは母娘でお揃い。
夫にも色違いのキャップを買いたかったのですが、「こういうのは似合わないから」と、断られてしまいました。