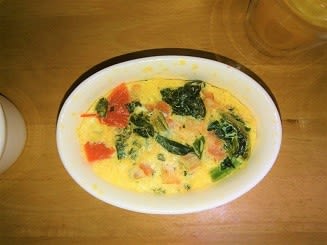ボルヘス編集『アルゼンチン短編集』には、ボルヘスによる序文と、ルゴーネス著「イスール」、ビオイ=カサレス著「烏賊はおのれの墨を選ぶ」、カンセーラ/ルサレータ著「運命の神さまはどじなお方」、コルタサル著「占拠された家」、ムヒカ=ライネス著「駅馬車」、オカンポ著「物」、ペルツァー著「チェスの師匠」、ペイロウ著「わが身にほんとうに起こったこと」、バスケス著「選ばれし人」の9編の短編が収録されている。
本書は、ボルヘス編集の“バベルの図書館” (全30巻)の20巻目にあたる。私にとっては11冊目の“バベルの図書館”の作品である。
尚、1番目の「イスール」は、“バベルの図書館” 18巻目、ルゴーネス著『塩の像』にも収録されている。理由があっての重複だと思うが、できれば別の作品の方が良かった。
“アルゼンチン文学は、アメリカ大陸の他の国々がスペイン人に提供したものとは、つねになにほどかことなっていた。前世紀の末にはアルゼンチンではガウチョ詩という固有のジャンルが発生したし、いまでは幻想文学への傾向をおびた作家、現実のたんなる転写は試みない作家が大勢いる。”
本書に収められている9つの“南米の孤独”の物語は、何れもどこかボルヘス的な匂いのする作風だった。その中で、私が特に面白いと思ったのが、ビオイ=カサレス著「烏賊はおのれの墨を選ぶ」、コルタサル著「占拠された家」、オカンポ著「物」、ペイロウ著「わが身にほんとうに起こったこと」の4編だ。
ビオイ=カサレス著「烏賊はおのれの墨を選ぶ」は、幻想文学にSFの要素を混ぜ込んだ奇妙な作風。本書の中では、最も特異な個性を発揮している作品だ。
ある村に宇宙人が訪れるとこから始まる物語なのだが、肝心の宇宙人は一度も姿を現さず、地元の人間の会話のみですべてが進行していく妙にドメスティックな作風なのだった。
事件の震源地は、地元の名士ドン・フアン・カマルゴの屋敷の資材置場だった。
ドン・フアンの屋敷は、道路側に花で覆われた庭園がある本格的な山荘風で、植物の管理は年中回っているスプリンクラーによって行われていた。
ところが、ある夏の日を境に、そのスプリンクラーが忽然と姿を消したのだ。庭園の花々はみるみる色つやを失っていく。ドン・フアンは庭園の管理を怠るような人物ではない。
一体、何者が何の目的でスプリンクラーを持ち去ったのか?
教師のぼくを中心とした地元の人々の調査と推理の結果、と言うか主にドン・フアンの養子ドン・ダデイートへの聞き取りにより、ドン・フアンが敷地内の資材置場に宇宙人を匿っていることが判明する。その宇宙人はナマズを連想させる外見と性質の持ち主で絶えず湿度を必要としており、ドン・フアンは湿度の確保のために庭園からスプリンクラーを持ち出したのだった。
ナマズ風宇宙人の来訪の目的は、原子爆弾による滅亡が目前に迫った地球の救済だった。
彼は、友人として、解放者として、この地球を救うためにやって来た。そして、計画推進のためドン・フアンの全面的な協力を要請したいと言っているのだという。
ところが、この先が分からない。
ナマズ風宇宙人とドン・フアンは、地球滅亡の回避に向けて、どのような行動をとるつもりなのか?真相に近づく唯一の弦であるドン・ダデイートは、気が利かない上に、受け答えもボケボケで、肝心なところが見えてこないのだ。
それから暫くして地元の人々は、ドン・フアンの庭園にスプリンクラーが戻ってきていることに気が付いた。もうスプリンクラーの必要は無くなったのだろうか?ナマズ風宇宙人は一体どうなったのか?
SFでありながら、ド田舎村の人々の会話だけで物語が成り立っている身近さが妙に楽しい。
この村の人々はあまり賢いとは感じられなくて、地球滅亡の危機をこの人達に任せておいて良いのかと不安になるし、実際最悪の結末を迎えつつあるところで物語は終了してしまう。が、不思議とバッドエンドな気はしない。このノホホンとした空気は何なのだろう。
特に教師のぼくとドン・ダデイートの会話の噛み合わなさは、コントみたいに珍妙で滑稽だった。地球滅亡の危機そのものより、それに対する人々の反応を楽しむ物語なのだろう。
コルタサル著「占拠された家」は、裕福な独身の兄妹が何者かに大切な屋敷をジワジワ占拠されていく話。最後まで何者かの正体が明かされないことと、これまた理由不明な兄妹の無抵抗主義、ノッタリとしたストーリー展開が良い感じに不気味である。
イレーネとぼくが独身のまま来てしまったのは、多分その家があったからだと思う。
そこにはぼくたちの祖先、父方の祖父や両親、それに子供の頃からのあらゆる思い出が残っていた。
毎月あちこちから地代が入って来るので、ぼくたちは生活のために働く必要はなかった。ぼくたちは買い物に出かける時以外は、その家から一歩も出ずに、それぞれの趣味に耽って過ごすことが出来た。イレーネは編み物、ぼくは祖父の遺した切手の整理。元々のぼくの趣味は読書だったけど、フランス文学全集を置いている部屋は既に何者かに占拠されてしまっていた。
家具の倒れるような音、或いはひそひそとした囁きの様な鈍く曖昧な音。
それらが彼等の活動音で、その音が聞こえてくるとぼくたちは彼らの侵入を防ぐために部屋に鍵をかける。だけど、彼らの占拠する範囲はジワジワと広がっており、その分ぼくたちは思い出の品を喪っていくのだった。
ある夜、ぼくたちはついに自分達のために確保していた家のこちら側も占拠されてしまう。ぼくたちは着の身着のままで家を明け渡した。家を離れる時、ぼくは玄関の鍵をしっかりと締め、それから鍵を排水溝に捨てた。
どのみち、ぼくたちが死んだら、冷淡な従兄弟たちが遺産としてこの家を手に入れ、それを取り壊して売り払い、一儲けすることになっただろう。それならば、この家を占拠している何者かにくれてやってしまった方が良いのかもしれない。
オカンポ著「物」もまた、古く愛しい物に纏わる物語。
カミラ・エルスキーは、どんなに貴重な物、思い出の詰まった物であっても、失くして嘆き悲しむということはなかった。
カミラは決して物を大切にしない人ではなかったけど、彼女にとって本当に大切なのは、人間と、飼っているカナリヤや犬たちだけだった。彼女は自分の生家から最初は火事で、二度目は貧乏のために、値打ち物だった貴重な家財が消えていくのを静かに見つめ続けた。
ところが、ある時期から、彼女の元に失われた物たちが次々と戻ってくるようになった。
最初は15年以上前に失くしたブレスレットだった。
ブレスレットを見つけた喜びに彼女の胸は何日も疼いていた。それから、彼女は自分の人生に彩りを添えてくれた様々な物たちを事細かに思い出すようになった。
そして、信じがたい事に、それらの物たちは彼女が何か働きかけたわけでもないのに、少しずつ彼女の元に戻って来たのだった。
最初のうち味わっていた懐かしさと切なさの入り混じった幸福な気持ちが、ある種の不安、恐怖、心配へと変わっていくのにそう時間はかからなかった。彼女がどこで何をしていても、それとは関係なしに物たちの方が彼女の元に帰ってくるのだ。これは一体どういう現象なのだろう?
多分、物たちが戻り始めた頃から彼女の人生は死に向かっていたのだろう。
物たちが彼女を愛していたのかどうかは分からない。ただ、彼女は大変幸せな人生を送った後、黄泉の国の人となったのだった。
ペイロウ著「わが身にほんとうに起こったこと」は、時間のズレを体験する男の物語。これもSFと言って良いだろう。
私はある時期から、毎朝十時に僅か二百メートルの間に、一人の男が彼自身の後ろを歩いていくのを何度も見かけるという異常体験を繰り返すようになった。時間が十時なのは時計で時刻を確かめていたから間違いない。
最初に地下鉄駅入り口の手前でその男を見かけたのは偶然だった。
美男でも醜男でもない、特に見るべき点のある男ではなかった。それにも関わらず、私の眼は無意識のうちにその男に向けられ、彼の細かな特徴を記憶していた。
それから数秒後、私は前方からさっきすれ違ったばかりの男が歩いてくるのを見た。この人は、もと来た道を素早く引き返し、改めて前と同じ方向に歩いてきたのだろうか?
そこまで考えた私は、ある事に気が付いてぎょっとなった。男は最初に見た時と同じ服装ではなかったのだ。
よく似た人物、例えば双子の兄弟が前後して歩いていただけかもしれない、私はそう考えて心を鎮めようとした。ところが、三度目に同じ男が先の二回とは異なる服装で歩いてくるのを目撃した時には、ただもうビックリするしかなかった。
私は記憶錯覚によって、同じ瞬間を何度も再体験したのであろうか?それならば、なぜ男は毎回違う服装をしているのか?
翌日も私は同じ体験を繰り返した。それが一ヶ月続いた頃に私はあることに気が付いた。
男との出会いが、彼にとって(私にとっても)ある時間の経過を示していたのだ。その男は過去から現在に向かって、或いは現在から過去に向かって歩いていた。私は何日もの間、どちらが正解なのか分からなかったが、並外れた記憶力によってこの問題を解決することができた。男は現在に向かって歩いており、私は彼の過去へと去っていく人生を毎朝見ていたのである。私はある人物のその日と、更に遡って、その前日と前々日を見ていたのだ。
しからば、その術を応用して見知らぬ男ではなく、見たい人物の過去を見ることが出来るようになるではないだろうか?その驚嘆すべき境地に達するには、まずその初歩をマスターしなければならない。それには、私にこの異常体験を齎したこの見知らぬ男を使って研鑽を積む必要がある…
四角張った理屈っぽい文章が、主人公のストーカー気質と絶妙にマッチしていた。技巧性も高い。“現実のたんなる転写”を由としないアルゼンチン文学は、SFとの親和性が高いようだ。アルゼンチンSF文学アンソロジーなんてものがあったら、ぜひ読んでみたいと思った。
本書は、ボルヘス編集の“バベルの図書館” (全30巻)の20巻目にあたる。私にとっては11冊目の“バベルの図書館”の作品である。
尚、1番目の「イスール」は、“バベルの図書館” 18巻目、ルゴーネス著『塩の像』にも収録されている。理由があっての重複だと思うが、できれば別の作品の方が良かった。
“アルゼンチン文学は、アメリカ大陸の他の国々がスペイン人に提供したものとは、つねになにほどかことなっていた。前世紀の末にはアルゼンチンではガウチョ詩という固有のジャンルが発生したし、いまでは幻想文学への傾向をおびた作家、現実のたんなる転写は試みない作家が大勢いる。”
本書に収められている9つの“南米の孤独”の物語は、何れもどこかボルヘス的な匂いのする作風だった。その中で、私が特に面白いと思ったのが、ビオイ=カサレス著「烏賊はおのれの墨を選ぶ」、コルタサル著「占拠された家」、オカンポ著「物」、ペイロウ著「わが身にほんとうに起こったこと」の4編だ。
ビオイ=カサレス著「烏賊はおのれの墨を選ぶ」は、幻想文学にSFの要素を混ぜ込んだ奇妙な作風。本書の中では、最も特異な個性を発揮している作品だ。
ある村に宇宙人が訪れるとこから始まる物語なのだが、肝心の宇宙人は一度も姿を現さず、地元の人間の会話のみですべてが進行していく妙にドメスティックな作風なのだった。
事件の震源地は、地元の名士ドン・フアン・カマルゴの屋敷の資材置場だった。
ドン・フアンの屋敷は、道路側に花で覆われた庭園がある本格的な山荘風で、植物の管理は年中回っているスプリンクラーによって行われていた。
ところが、ある夏の日を境に、そのスプリンクラーが忽然と姿を消したのだ。庭園の花々はみるみる色つやを失っていく。ドン・フアンは庭園の管理を怠るような人物ではない。
一体、何者が何の目的でスプリンクラーを持ち去ったのか?
教師のぼくを中心とした地元の人々の調査と推理の結果、と言うか主にドン・フアンの養子ドン・ダデイートへの聞き取りにより、ドン・フアンが敷地内の資材置場に宇宙人を匿っていることが判明する。その宇宙人はナマズを連想させる外見と性質の持ち主で絶えず湿度を必要としており、ドン・フアンは湿度の確保のために庭園からスプリンクラーを持ち出したのだった。
ナマズ風宇宙人の来訪の目的は、原子爆弾による滅亡が目前に迫った地球の救済だった。
彼は、友人として、解放者として、この地球を救うためにやって来た。そして、計画推進のためドン・フアンの全面的な協力を要請したいと言っているのだという。
ところが、この先が分からない。
ナマズ風宇宙人とドン・フアンは、地球滅亡の回避に向けて、どのような行動をとるつもりなのか?真相に近づく唯一の弦であるドン・ダデイートは、気が利かない上に、受け答えもボケボケで、肝心なところが見えてこないのだ。
それから暫くして地元の人々は、ドン・フアンの庭園にスプリンクラーが戻ってきていることに気が付いた。もうスプリンクラーの必要は無くなったのだろうか?ナマズ風宇宙人は一体どうなったのか?
SFでありながら、ド田舎村の人々の会話だけで物語が成り立っている身近さが妙に楽しい。
この村の人々はあまり賢いとは感じられなくて、地球滅亡の危機をこの人達に任せておいて良いのかと不安になるし、実際最悪の結末を迎えつつあるところで物語は終了してしまう。が、不思議とバッドエンドな気はしない。このノホホンとした空気は何なのだろう。
特に教師のぼくとドン・ダデイートの会話の噛み合わなさは、コントみたいに珍妙で滑稽だった。地球滅亡の危機そのものより、それに対する人々の反応を楽しむ物語なのだろう。
コルタサル著「占拠された家」は、裕福な独身の兄妹が何者かに大切な屋敷をジワジワ占拠されていく話。最後まで何者かの正体が明かされないことと、これまた理由不明な兄妹の無抵抗主義、ノッタリとしたストーリー展開が良い感じに不気味である。
イレーネとぼくが独身のまま来てしまったのは、多分その家があったからだと思う。
そこにはぼくたちの祖先、父方の祖父や両親、それに子供の頃からのあらゆる思い出が残っていた。
毎月あちこちから地代が入って来るので、ぼくたちは生活のために働く必要はなかった。ぼくたちは買い物に出かける時以外は、その家から一歩も出ずに、それぞれの趣味に耽って過ごすことが出来た。イレーネは編み物、ぼくは祖父の遺した切手の整理。元々のぼくの趣味は読書だったけど、フランス文学全集を置いている部屋は既に何者かに占拠されてしまっていた。
家具の倒れるような音、或いはひそひそとした囁きの様な鈍く曖昧な音。
それらが彼等の活動音で、その音が聞こえてくるとぼくたちは彼らの侵入を防ぐために部屋に鍵をかける。だけど、彼らの占拠する範囲はジワジワと広がっており、その分ぼくたちは思い出の品を喪っていくのだった。
ある夜、ぼくたちはついに自分達のために確保していた家のこちら側も占拠されてしまう。ぼくたちは着の身着のままで家を明け渡した。家を離れる時、ぼくは玄関の鍵をしっかりと締め、それから鍵を排水溝に捨てた。
どのみち、ぼくたちが死んだら、冷淡な従兄弟たちが遺産としてこの家を手に入れ、それを取り壊して売り払い、一儲けすることになっただろう。それならば、この家を占拠している何者かにくれてやってしまった方が良いのかもしれない。
オカンポ著「物」もまた、古く愛しい物に纏わる物語。
カミラ・エルスキーは、どんなに貴重な物、思い出の詰まった物であっても、失くして嘆き悲しむということはなかった。
カミラは決して物を大切にしない人ではなかったけど、彼女にとって本当に大切なのは、人間と、飼っているカナリヤや犬たちだけだった。彼女は自分の生家から最初は火事で、二度目は貧乏のために、値打ち物だった貴重な家財が消えていくのを静かに見つめ続けた。
ところが、ある時期から、彼女の元に失われた物たちが次々と戻ってくるようになった。
最初は15年以上前に失くしたブレスレットだった。
ブレスレットを見つけた喜びに彼女の胸は何日も疼いていた。それから、彼女は自分の人生に彩りを添えてくれた様々な物たちを事細かに思い出すようになった。
そして、信じがたい事に、それらの物たちは彼女が何か働きかけたわけでもないのに、少しずつ彼女の元に戻って来たのだった。
最初のうち味わっていた懐かしさと切なさの入り混じった幸福な気持ちが、ある種の不安、恐怖、心配へと変わっていくのにそう時間はかからなかった。彼女がどこで何をしていても、それとは関係なしに物たちの方が彼女の元に帰ってくるのだ。これは一体どういう現象なのだろう?
多分、物たちが戻り始めた頃から彼女の人生は死に向かっていたのだろう。
物たちが彼女を愛していたのかどうかは分からない。ただ、彼女は大変幸せな人生を送った後、黄泉の国の人となったのだった。
ペイロウ著「わが身にほんとうに起こったこと」は、時間のズレを体験する男の物語。これもSFと言って良いだろう。
私はある時期から、毎朝十時に僅か二百メートルの間に、一人の男が彼自身の後ろを歩いていくのを何度も見かけるという異常体験を繰り返すようになった。時間が十時なのは時計で時刻を確かめていたから間違いない。
最初に地下鉄駅入り口の手前でその男を見かけたのは偶然だった。
美男でも醜男でもない、特に見るべき点のある男ではなかった。それにも関わらず、私の眼は無意識のうちにその男に向けられ、彼の細かな特徴を記憶していた。
それから数秒後、私は前方からさっきすれ違ったばかりの男が歩いてくるのを見た。この人は、もと来た道を素早く引き返し、改めて前と同じ方向に歩いてきたのだろうか?
そこまで考えた私は、ある事に気が付いてぎょっとなった。男は最初に見た時と同じ服装ではなかったのだ。
よく似た人物、例えば双子の兄弟が前後して歩いていただけかもしれない、私はそう考えて心を鎮めようとした。ところが、三度目に同じ男が先の二回とは異なる服装で歩いてくるのを目撃した時には、ただもうビックリするしかなかった。
私は記憶錯覚によって、同じ瞬間を何度も再体験したのであろうか?それならば、なぜ男は毎回違う服装をしているのか?
翌日も私は同じ体験を繰り返した。それが一ヶ月続いた頃に私はあることに気が付いた。
男との出会いが、彼にとって(私にとっても)ある時間の経過を示していたのだ。その男は過去から現在に向かって、或いは現在から過去に向かって歩いていた。私は何日もの間、どちらが正解なのか分からなかったが、並外れた記憶力によってこの問題を解決することができた。男は現在に向かって歩いており、私は彼の過去へと去っていく人生を毎朝見ていたのである。私はある人物のその日と、更に遡って、その前日と前々日を見ていたのだ。
しからば、その術を応用して見知らぬ男ではなく、見たい人物の過去を見ることが出来るようになるではないだろうか?その驚嘆すべき境地に達するには、まずその初歩をマスターしなければならない。それには、私にこの異常体験を齎したこの見知らぬ男を使って研鑽を積む必要がある…
四角張った理屈っぽい文章が、主人公のストーカー気質と絶妙にマッチしていた。技巧性も高い。“現実のたんなる転写”を由としないアルゼンチン文学は、SFとの親和性が高いようだ。アルゼンチンSF文学アンソロジーなんてものがあったら、ぜひ読んでみたいと思った。