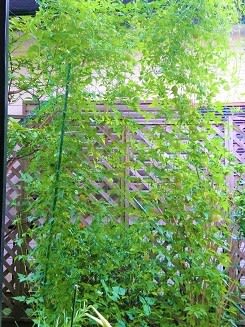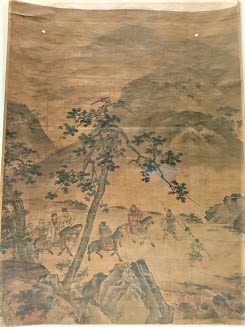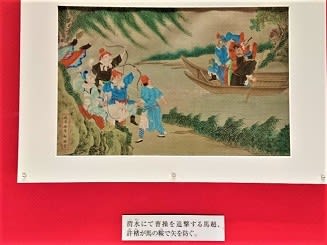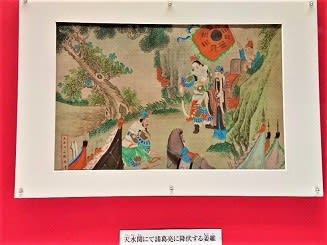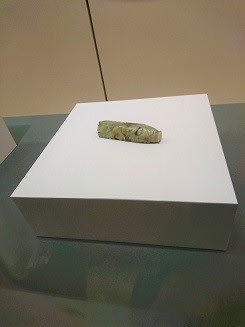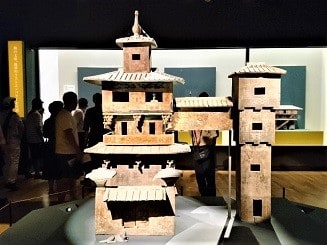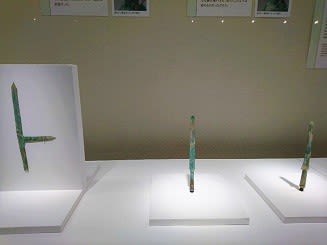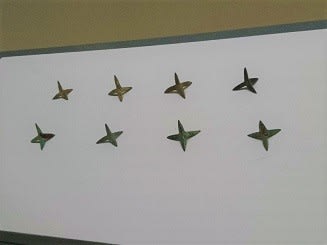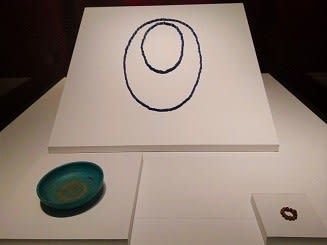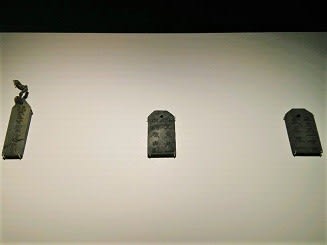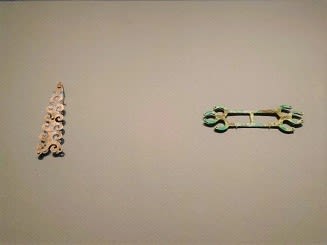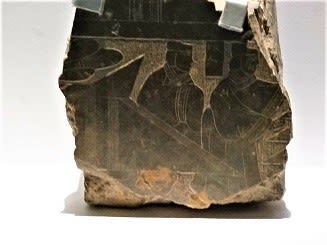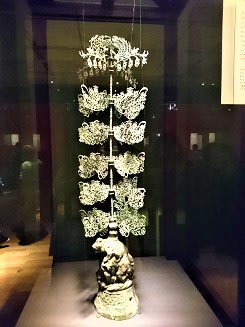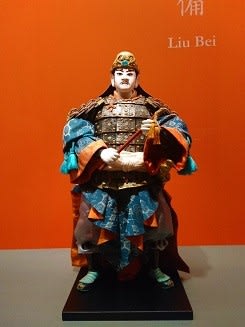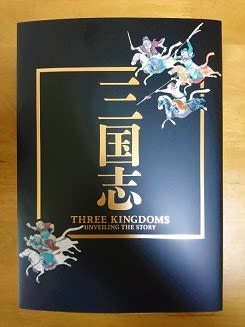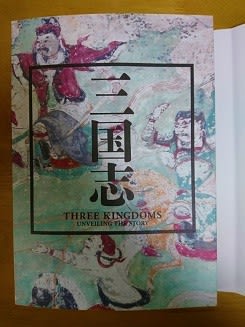ヒントン著『科学的ロマンス集』は、ボルヘスによる序文と、「第四の次元とは何か」「平面世界」「ペルシアの王」の三編が収録されている。
本書は、ボルヘス編集の“バベルの図書館”シリーズの25巻目にあたる。私にとっては、22冊目の“バベルの図書館”の作品である。
本書によって、ヒントンという名を初めて知った。付録の解説によると、ヒントンはオクスフォードで学位を取った数学者だ。
ヒントンの関心は、“四次元空間の直接で直感的な知識であり、高次の空間の知識を用いて形而上・形而下の問題を解決すること”と、“幾何学を直接的知覚の訓練として学ぶ”ことにあったらしい。
……もうこの段階で言っている意味がよく分からない。これは難物だな、と感じた。
“彼の著作は生前から特に神智学系のサークルでさかんに論議された。いわゆる心霊現象が四次元という考え方によってうまく説明されていると考えられたのである。また、過去・現在・未来がすべて高次元において現存するという考えは、予知やサイコメトリーがいかにして可能かを説明するだろうし、ヒントンが想定した究極の物質は、錬金術におけるプリマ・マテリアに似る。 ”
ヒントンは四次元世界へ潜入するための訓練に超能力は必要ないと考えていた。
では、彼は何を必要としていたのか?
それは、“無限数の体積によって作られ、体積によって限定される超体積の概念”なのだ。
“彼は超立方体、超角柱、超角錐、超円錐、超円錐台、超球体、等々といったものの客観的実在性を信じた。この宇宙に奥行きのないものは何もない以上、あらゆる幾何学的概念のうちで実現性を帯びているのはただひとつ体積のみであるというふうには彼は考えなかった。(略)ヒントンは二次元の世界、四次元の世界、五次元の、六次元のというように、自然数の数列が尽きるまでの次元の世界が存在すると考えた。”
「第四の次元とは何か」と「平面世界」の二編には、ヒントンの四次元世界への潜入法が記されている。
これらを小説と言って良いのかは、ちょっと分からない。数式や図表が多用されていて、まるで論文を読まされている気分になる。面白いか面白くないかと問われれば、面白いと答える。が、スッと頭に入ってこない。論理的思考が身についていないと読み解けない作品だと思った。この取っ付きにくさが、ヒルトンの存在を無名の闇に沈めているのだろう。
「第四の次元とは何か」において、ヒントンは、実際的な確定性を持った領域を超えた世界に目を向けるのには、「知識とは何か?経験を構成するものは何か?」と問うことと、“知の領域において恣意的で非合理な制限を受けていると思われることのすべてを疑問視する”ことの二通りの方法があると述べている。
われわれの住む三次元の世界とは、空間が縦・横・高さの三座標で表せる世界のことだが、逆に言うと、三つの方向しか存在しないという制限を受けている状態でもある。
この制限がどのようなものであるのかについて、ヒントンは、より制限を受けている次元――つまりは二次元、一次元の状態について丁寧に解説している。それがあまりにも微に入り細に入りなので、つい彼の言葉の端々を追うことに熱中してしまい、ふと気が付いた時に「私は何を読ませられているのか」と茫然としてしまったりもする。
一次元の世界とは、直線を両方向に無限の距離に延長したものでしかないので、その世界の存在者は(そんな者がいるとすれば)、経験の及ぶ全範囲が一本の直線内に限られているので、他者とすれ違うという経験をすることが永遠にない。彼らの他者との接触は、両脇に一名ずつという制限を受けているのだ。そして、すべての行動が直線の内に制限されている彼らには、別種の移動方向の概念を持つことができない。
二次元の世界とは、一平面の表面が経験の及ぶ全範囲の世界のことだ。
平面の世界にあるのは、長さと幅の二方向だけである。故にこの世界の存在者は、我々が上下と呼ぶ方向に動くことは出来ないし、上下という方向があるという考えに到達することが出来ない。彼らが置かれた状況が、それを教えないからである。
しかし、ここで二次元の存在者が、彼らよりさらに制限を受けている、一本の直線に閉じ込められた存在を想像することができるならば、直線内の存在が一つの方向にしか動けないのに、自分は二つの方向に動けるということを認識できるかもしれない。次元が一つ増えるとそれだけ存在者の状況は恵まれたものになる。平面内では、姿形の多様性が無限になるし、不定の数の他者との接触が可能になる。こう考察した後で、彼は「だが、なぜ方向の数は二つに制限されているのか?なぜ三つでは無いのか?」と疑問を抱くかもしれない。
そして、この問いを三次元の世界にスライドさせれば、「なぜ方向の数は三つに制限されているのか?なぜ四つでは無いのか?」と、我々の知る空間が制限を受けていることへの問いが生まれるかもしれない。
……という感じで、我々が自分たちの住む三次元の世界より高次の四次元の世界を想像するにあたって、まず三次元の世界よりも次元の低い世界を想像し、その世界の存在者と三次元にいる我々との比較によって、四次元の世界を推測するというアプローチをとっているのだ。このやり方を応用すれば、五次元、六次元と数列の続く限り、つまりは無限に次元の世界を増やしていくことが可能かもしれない。
一次元の図形が「直線」、二次元の図形が「平面」、三次元の図形が「立方」なら、四次元の図形は何なのだろう。
われわれが第四の方向を想像することが出来ないのは、正方形2が立方体3となるような動きの方向を平面内の存在者が想像できないのと同様だ。彼にとっての第三の次元とは、我々にとっての第四の次元と同様に理解不能なものだ。
我々が第四の次元をイメージするには、1から2、2から3、3から4が形成される過程の間に存在する類比関係を追及することによって、四次元におけるもっとも単純な図形の特性がどんなものかを探求する必要がある。
ヒントンは、四次元におけるもっとも単純な図形に「四平方」と命名し、それがどのような図形であるのかを考察していく。ここで、AだのBだの言いだすので、数学音痴の私は眩暈がしてきたが、根気よく解き明かしていくうちに、ヨチヨチながら法則が見えてきた。
まず、点について。
直線には二個の点、平方には四個の点、立方には八個の点がある。ならば、四平方には、同一の法則にしたがえば、十六個の点があることになる。
次に線について。
直線の線は一本である。平方は線が四本だ。立方には十二本の線がある。ならば、四平方には何本の線があるか?1、4、12。同一の法則にしたがえば、つまりは、先行の図形の線の数を二倍して、それに先行の図形の点の数を加えると、四平方の線は、2×12+8で三十二本になる。
更に面について。
線は零面。平方は一面。立方は六面。ここで、0、1、6という三つの数値を得た。ならば、四平方の面の数はいくつか?
立方体がどのようにして生じるか。正方形は、その動きの始まりにおいて立方体の面の一つを決定し、終わりにおいてその対面になり、移動の間に正方形の各線が立方体の平面をなぞり出す。ので、先行の図形の平面の数は二倍になり、先行の線のすべてが、後の図形の平面の一つをなぞる。この法則を当てはめると、四平方は、表面の数を立方の倍にして十二、それに直線の各々について平面を一つ加えると直線が十二本なので、さらに十二、即ち二十四の平面があるという答えが導き出される。
16の点、32の線、24の面、これが四平方という形態だ。
このようにして四次元内のもっとも単純な形態の特性を叙述することがいかにして可能となるかを見れば、さらに複雑な図形の心的構築もまた、時間と忍耐さえあれば可能になる。四次元存在者が、我々に対してどのような関係を持っているかも解答可能だ。
思考の抽象化、つまりは、想像し得ない事柄に関して筋道を立てて論じ、結論を引き出すことによって我々は、我々がイメージを形成できない事柄を、理解可能な言葉で表現できる。思弁によって、精神は諸々の概念を築き上げることが可能になる。我々が享受している経験から抽象としての存在者をこのように想起できるというのは、なかなか面白いものだ。
「第四の次元とは何か」の感想というか体験談に終始してしまったが(頑張って算数したので、その苦闘の跡を記したかった)、本作で一番面白かったのは、「ペルシアの王」である。第一部が寓話で、第二部はそれの数学的解説である。
これはヒントン的天地創造物語なのだ。
とある谷間に落ちた王が、謎の老人に谷間の世界の創造者になることを命じられる。自力では鈍麻状態から抜け出そうとしない被造物に連続活動を起こさせるために、感覚のモーメントが用いられる。王は快楽と苦痛の二つの感覚をコントロールすることで、習慣的動作を起こす。当然のことながら、快楽100と苦痛100では、被造物は鈍麻状態から抜け出さない。そこで苦痛の一部を王が負担すれば、どうなるか。王は自分が負担する苦痛の数値を加減することで、被造物の行動をプログラミングしていく。行動は思考を生み、被造物、つまり人間は、彼らなりの法則を組み立てていく――。
数式を用いた幻想小説というのは、かなり珍しい。
ヒントンは1800年代の人なので、時代的には全然新しくはないのだが、誰もこの路線を継承しなかったのだろう。ヒントン的小説作法は、現時点においてもヒントン自身が最新版である。
ヒントンが、「ペルシアの王」の中で、“(小さな数量は)今は読み飛ばして、後で参照のため戻るのが良いかもしれない”と促しているにも拘らず、つい目の前の数量計算に必死になってしまうので、かなり疲れる読書体験になった。
それでも、ヒントンの創造する世界は美しい。それは、数学的思考の筋道に従って無限に広がっていく整然とした美の世界、ヒルトンに言わせれば、“知的な美の景観”なのだ。
本書は、ボルヘス編集の“バベルの図書館”シリーズの25巻目にあたる。私にとっては、22冊目の“バベルの図書館”の作品である。
本書によって、ヒントンという名を初めて知った。付録の解説によると、ヒントンはオクスフォードで学位を取った数学者だ。
ヒントンの関心は、“四次元空間の直接で直感的な知識であり、高次の空間の知識を用いて形而上・形而下の問題を解決すること”と、“幾何学を直接的知覚の訓練として学ぶ”ことにあったらしい。
……もうこの段階で言っている意味がよく分からない。これは難物だな、と感じた。
“彼の著作は生前から特に神智学系のサークルでさかんに論議された。いわゆる心霊現象が四次元という考え方によってうまく説明されていると考えられたのである。また、過去・現在・未来がすべて高次元において現存するという考えは、予知やサイコメトリーがいかにして可能かを説明するだろうし、ヒントンが想定した究極の物質は、錬金術におけるプリマ・マテリアに似る。 ”
ヒントンは四次元世界へ潜入するための訓練に超能力は必要ないと考えていた。
では、彼は何を必要としていたのか?
それは、“無限数の体積によって作られ、体積によって限定される超体積の概念”なのだ。
“彼は超立方体、超角柱、超角錐、超円錐、超円錐台、超球体、等々といったものの客観的実在性を信じた。この宇宙に奥行きのないものは何もない以上、あらゆる幾何学的概念のうちで実現性を帯びているのはただひとつ体積のみであるというふうには彼は考えなかった。(略)ヒントンは二次元の世界、四次元の世界、五次元の、六次元のというように、自然数の数列が尽きるまでの次元の世界が存在すると考えた。”
「第四の次元とは何か」と「平面世界」の二編には、ヒントンの四次元世界への潜入法が記されている。
これらを小説と言って良いのかは、ちょっと分からない。数式や図表が多用されていて、まるで論文を読まされている気分になる。面白いか面白くないかと問われれば、面白いと答える。が、スッと頭に入ってこない。論理的思考が身についていないと読み解けない作品だと思った。この取っ付きにくさが、ヒルトンの存在を無名の闇に沈めているのだろう。
「第四の次元とは何か」において、ヒントンは、実際的な確定性を持った領域を超えた世界に目を向けるのには、「知識とは何か?経験を構成するものは何か?」と問うことと、“知の領域において恣意的で非合理な制限を受けていると思われることのすべてを疑問視する”ことの二通りの方法があると述べている。
われわれの住む三次元の世界とは、空間が縦・横・高さの三座標で表せる世界のことだが、逆に言うと、三つの方向しか存在しないという制限を受けている状態でもある。
この制限がどのようなものであるのかについて、ヒントンは、より制限を受けている次元――つまりは二次元、一次元の状態について丁寧に解説している。それがあまりにも微に入り細に入りなので、つい彼の言葉の端々を追うことに熱中してしまい、ふと気が付いた時に「私は何を読ませられているのか」と茫然としてしまったりもする。
一次元の世界とは、直線を両方向に無限の距離に延長したものでしかないので、その世界の存在者は(そんな者がいるとすれば)、経験の及ぶ全範囲が一本の直線内に限られているので、他者とすれ違うという経験をすることが永遠にない。彼らの他者との接触は、両脇に一名ずつという制限を受けているのだ。そして、すべての行動が直線の内に制限されている彼らには、別種の移動方向の概念を持つことができない。
二次元の世界とは、一平面の表面が経験の及ぶ全範囲の世界のことだ。
平面の世界にあるのは、長さと幅の二方向だけである。故にこの世界の存在者は、我々が上下と呼ぶ方向に動くことは出来ないし、上下という方向があるという考えに到達することが出来ない。彼らが置かれた状況が、それを教えないからである。
しかし、ここで二次元の存在者が、彼らよりさらに制限を受けている、一本の直線に閉じ込められた存在を想像することができるならば、直線内の存在が一つの方向にしか動けないのに、自分は二つの方向に動けるということを認識できるかもしれない。次元が一つ増えるとそれだけ存在者の状況は恵まれたものになる。平面内では、姿形の多様性が無限になるし、不定の数の他者との接触が可能になる。こう考察した後で、彼は「だが、なぜ方向の数は二つに制限されているのか?なぜ三つでは無いのか?」と疑問を抱くかもしれない。
そして、この問いを三次元の世界にスライドさせれば、「なぜ方向の数は三つに制限されているのか?なぜ四つでは無いのか?」と、我々の知る空間が制限を受けていることへの問いが生まれるかもしれない。
……という感じで、我々が自分たちの住む三次元の世界より高次の四次元の世界を想像するにあたって、まず三次元の世界よりも次元の低い世界を想像し、その世界の存在者と三次元にいる我々との比較によって、四次元の世界を推測するというアプローチをとっているのだ。このやり方を応用すれば、五次元、六次元と数列の続く限り、つまりは無限に次元の世界を増やしていくことが可能かもしれない。
一次元の図形が「直線」、二次元の図形が「平面」、三次元の図形が「立方」なら、四次元の図形は何なのだろう。
われわれが第四の方向を想像することが出来ないのは、正方形2が立方体3となるような動きの方向を平面内の存在者が想像できないのと同様だ。彼にとっての第三の次元とは、我々にとっての第四の次元と同様に理解不能なものだ。
我々が第四の次元をイメージするには、1から2、2から3、3から4が形成される過程の間に存在する類比関係を追及することによって、四次元におけるもっとも単純な図形の特性がどんなものかを探求する必要がある。
ヒントンは、四次元におけるもっとも単純な図形に「四平方」と命名し、それがどのような図形であるのかを考察していく。ここで、AだのBだの言いだすので、数学音痴の私は眩暈がしてきたが、根気よく解き明かしていくうちに、ヨチヨチながら法則が見えてきた。
まず、点について。
直線には二個の点、平方には四個の点、立方には八個の点がある。ならば、四平方には、同一の法則にしたがえば、十六個の点があることになる。
次に線について。
直線の線は一本である。平方は線が四本だ。立方には十二本の線がある。ならば、四平方には何本の線があるか?1、4、12。同一の法則にしたがえば、つまりは、先行の図形の線の数を二倍して、それに先行の図形の点の数を加えると、四平方の線は、2×12+8で三十二本になる。
更に面について。
線は零面。平方は一面。立方は六面。ここで、0、1、6という三つの数値を得た。ならば、四平方の面の数はいくつか?
立方体がどのようにして生じるか。正方形は、その動きの始まりにおいて立方体の面の一つを決定し、終わりにおいてその対面になり、移動の間に正方形の各線が立方体の平面をなぞり出す。ので、先行の図形の平面の数は二倍になり、先行の線のすべてが、後の図形の平面の一つをなぞる。この法則を当てはめると、四平方は、表面の数を立方の倍にして十二、それに直線の各々について平面を一つ加えると直線が十二本なので、さらに十二、即ち二十四の平面があるという答えが導き出される。
16の点、32の線、24の面、これが四平方という形態だ。
このようにして四次元内のもっとも単純な形態の特性を叙述することがいかにして可能となるかを見れば、さらに複雑な図形の心的構築もまた、時間と忍耐さえあれば可能になる。四次元存在者が、我々に対してどのような関係を持っているかも解答可能だ。
思考の抽象化、つまりは、想像し得ない事柄に関して筋道を立てて論じ、結論を引き出すことによって我々は、我々がイメージを形成できない事柄を、理解可能な言葉で表現できる。思弁によって、精神は諸々の概念を築き上げることが可能になる。我々が享受している経験から抽象としての存在者をこのように想起できるというのは、なかなか面白いものだ。
「第四の次元とは何か」の感想というか体験談に終始してしまったが(頑張って算数したので、その苦闘の跡を記したかった)、本作で一番面白かったのは、「ペルシアの王」である。第一部が寓話で、第二部はそれの数学的解説である。
これはヒントン的天地創造物語なのだ。
とある谷間に落ちた王が、謎の老人に谷間の世界の創造者になることを命じられる。自力では鈍麻状態から抜け出そうとしない被造物に連続活動を起こさせるために、感覚のモーメントが用いられる。王は快楽と苦痛の二つの感覚をコントロールすることで、習慣的動作を起こす。当然のことながら、快楽100と苦痛100では、被造物は鈍麻状態から抜け出さない。そこで苦痛の一部を王が負担すれば、どうなるか。王は自分が負担する苦痛の数値を加減することで、被造物の行動をプログラミングしていく。行動は思考を生み、被造物、つまり人間は、彼らなりの法則を組み立てていく――。
数式を用いた幻想小説というのは、かなり珍しい。
ヒントンは1800年代の人なので、時代的には全然新しくはないのだが、誰もこの路線を継承しなかったのだろう。ヒントン的小説作法は、現時点においてもヒントン自身が最新版である。
ヒントンが、「ペルシアの王」の中で、“(小さな数量は)今は読み飛ばして、後で参照のため戻るのが良いかもしれない”と促しているにも拘らず、つい目の前の数量計算に必死になってしまうので、かなり疲れる読書体験になった。
それでも、ヒントンの創造する世界は美しい。それは、数学的思考の筋道に従って無限に広がっていく整然とした美の世界、ヒルトンに言わせれば、“知的な美の景観”なのだ。