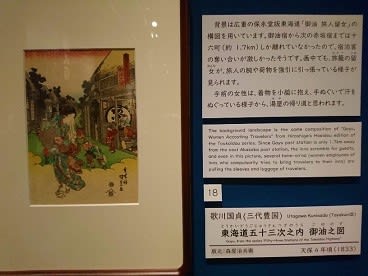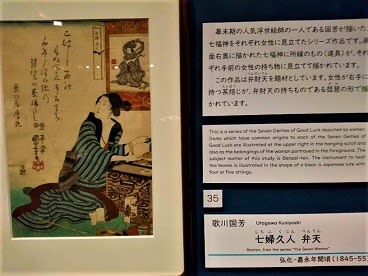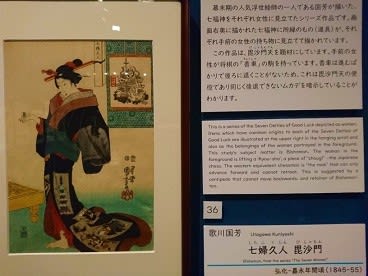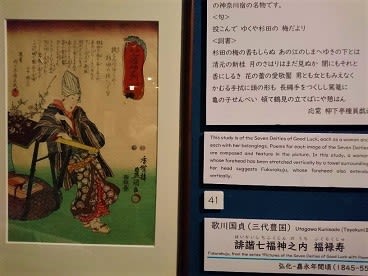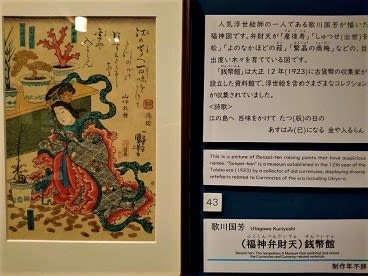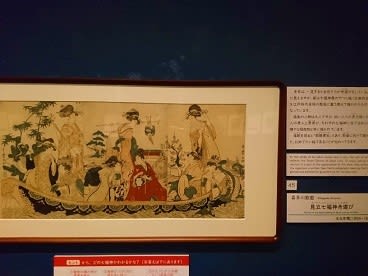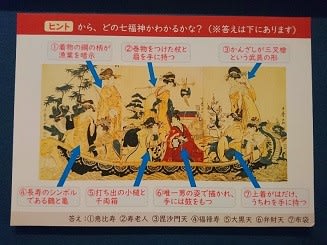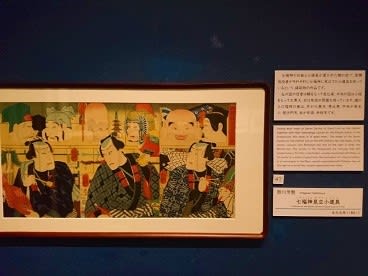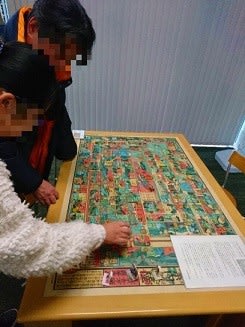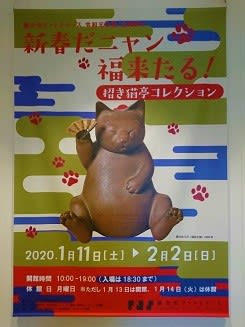『ラテンアメリカ五人集』には、J・E・パチェーコ(メキシコ)、М・バルガス=リョサ(ペルー)、シルビーナ・オカンポ(アルゼンチン)、オクタビオ・パス(メキシコ)、M・A・アストゥリアス(グアマテラ)という、ラテンアメリカ各地から選ばれた五人の作家の短編を収録している。
このメンバーの中では、バルガス=リョサが2010年、パスが1990年、アストゥリアスが1968年にノーベル文学賞を受賞している。
収録順は、J・E・パチェーコ「砂漠の戦い」、М・バルガス=リョサ「子犬たち」、シルビーナ・オカンポ「鏡の前のコルネリア」、オクタビオ・パス「白」、「青い目の花束」、「見知らぬふたりへの手紙」、М・A・アストゥリアス「グアマテラ伝説集」の並びだ。
本書は、パスが目当てで手に取った。
ガルシア・マルケス他『
美しい水死人 ラテンアメリカ文学アンソロジー』(2018-10-05 の当ブログ)に収められていたパスの「波と暮らして」があまりにも私好みだったので。
アンソロジーの良いところは一定の括りで作品が編集されているので、カンで適当に選ぶよりは好みの作品に出会える確率がグンと高くなるところだ。本書はラテンアメリカ文学で、しかもパスが選ばれている。これは、ほかの作家の作品にも期待できる……。
今回は、J・E・パチェーコの「砂漠の戦い」と、М・A・アストゥリアスの「グアマテラ伝説集」が好きになった。
特に「砂漠の戦い」は、出会った時期が今で本当に良かった。時期が違っていたらそれほど心に響かなかったかもしれない。パチェ-コの作品は、『美しい水死人』の中にも「遊園地」が載っていたのだが、こちらはあまり記憶に残っていないのだ。印象が変わるかもしれないので、「遊園地」ももう一度読んでみよう。
アストゥリアスは、いつの時期に読んでも好きになったと思う。
「砂漠の戦い」は、タイトルからメキシコ革命の話かと思ったら、胸の疼くようなノスタルジーに浸された青春文学だった。失われた故郷の町と初恋の記憶。思い出の中で、マリアーナはいつまでも世界一美しい女性のままだ。
不潔で不味い食事。下品でがさつな人々。家も学校も町も、喧騒と貧困と悪臭に塗れていた。あの頃、まだ十代前半の少年だった主人公の目には、マリアーナだけが優しく、美しく、エレガントに映っていたのだ。
少年時代の回想ということで、当時の社会情勢、政治、風俗、テレビやラジオの番組、流行歌、人気車種など、細かく固有名詞を挙げながら、回顧録的な調子で綴られている。
それらのすべてがすでに失われているという事実と、マリアーナ母子の曖昧な存在感とが、奇妙に不安定で夢見心地な印象を読者に与えるのだ。
“過去は外国である。そこでは人は変わった振る舞いをする L・P・ハートリー『仲介者』”
それは、はっきり思い出せないが、30年は昔の話、ミゲル・アレマンが政権(1946-52年)をとった頃のことだ。主人公の名はカルロス。物語はカルロスの一人称〈わたし〉で綴られていく。
〈わたし〉たちの住む町では、階層によって住む区画が異なり、子供たちの通う学校も違った。教室の中でも階級差は歴然としていた。ロサーレスと比べれば〈わたし〉は百万長者、ハリー・アサトンと比べれば乞食だった、という具合に。
〈わたし〉は、クラスメイトのジムの住む高級アパートに遊びに行き、彼の母親マリアーナに一目惚れする。
マリアーナは当時28歳、〈わたし〉の母親よりはだいぶ若かった。美しく親切でエレガントな物腰の彼女は、〈わたし〉の周囲にいる人々とは何もかもが違っていた。
〈わたし〉の初恋は障壁だらけだった。
友人の母親で、かなり年上。それよりなにより、メキシコを代表する実業家の愛人で、一人息子ジムの父親は、その愛人とは別の男。〈わたし〉の母親をはじめとする町の大人たちからの評判はかなり悪い。
誰にも言えない片想いに苦しむ〈わたし〉は、ある日、発作的に学校を抜け出してマリアーナに会いに行き、想いを伝える。それに対して、マリアーナは、今まで通り息子の友人として遊びに来て欲しいと、〈わたし〉の告白を聞かなかったことにした。〈わたし〉たちの間には何も起こらなかった。しかし、アパートの管理人の口から悪い噂が広まり、〈わたし〉は学校に行けなくなる。
完全に問題児扱いとなった〈わたし〉は、ある日は牧師には告解をさせられ、また別のある日は精神科医に分析されと、苦い思いを噛み締める日々を送ることとなる。
唯一好意的なのは、大学で〈活動家〉をしている兄のエクトルだが、この人は家庭内で厄介者ポジションなので、〈わたし〉の力にはなり得ない。ただ恋をしただけで、〈わたし〉はひとりぼっちになってしまった。
“あなたたちは誰にも恋をしたことがないんですか?”
〈わたし〉は転校させられ、二度とマリアーナにもジムにも会うことがなかった。
ある日、〈わたし〉はロサーレスから、マリアーナが愛人からパーティの席上で侮辱を受け、自殺したと聞かされる。
〈わたし〉は泣きながら彼女のアパートに駆けつける。しかし、そこには別の住人が住んでいて、その人物もアパートの管理人もマリアーナなんて知らないと言う。アパートの所有者はマリアーナの愛人だ。管理人を雇っているのもあの男だ。〈わたし〉はアパートの部屋を一軒一軒聞いて回ったが、誰もが、「知らないね」「1939年からこのビルに住んでいるけど、あたしの知るかぎり。ここにはマリアーナなんて人はいたためしがないね」「ジム?そんな子も知らないね」といった具合だった。
〈わたし〉は家に帰った。その後、どうしたかは思い出せない。やがて、〈わたし〉たちはニューヨークに渡った。
あれからロサーレスにも、当時の仲間にも会ったことがない。学校はつぶされ、マリアーナのいた建物はつぶされ、〈わたし〉の家はつぶされ、町は無くなった。あの頃のメキシコを偲ばせるものは何もない。
だが、マリアーナはいたのだ。ジムもいた。マリアーナの自殺が本当のことなのか、実は彼女はまだ生きているのか、〈わたし〉は絶対に知ることはないだろう。
このあたりの描写があっさりしているのが、却って深く切ない余韻を残す。
マリアーナは本当に自殺したのかとか、その後の〈わたし〉がどんな思いで生きて来たかとか、余計な描写をくどくどと重ねず、読者の想像にゆだねる思い切りの良さにセンスを感じた。
“自然なものは憎悪だけといった世界では、恋はひとつの病なのだ。”
急速なスピードで近代化していった40~50年代のメキシコ。
人々は僅かな期待と多大な不安に包まれていた。その目まぐるしい時代の動きに合わせるように、この物語の場面展開も早い。そして、思い出せないこと、分からないことが放り出されたまま物語は終わる。得体の知れない社会の闇に飲まれてしまったマリアーナや、カルロス少年の初恋、失われた故郷への、限りない哀切を瞬間冷却保存するかのような鮮やかな幕切れだった。
オクタビオ・パス「青い目の花束」は、これものすごく好きだなぁ、と幸福感でいっぱいになりながら読んだ。
目覚めるとぐっしょり汗をかいていた〈私〉は、ハンモックから飛び降りると、宿の主人が止めるのに対して、「すぐにもどる」と告げて、散歩に出かける。
道中の自然や〈私〉の仕草、心情の描写は、詩人パスらしい夢見るような繊細さだ。
“私は宇宙とは巨大な信号のシステムであり、森羅万象の間で交わされる会話であると思った。私の行為、コオロギの鳴き声、星のまたたきは、この会話の中にちりばめられた休止と音節にほかならない。私が音節であるのはどんな言葉だろうか。”
“煙草が落ちるとき、この上なく小さな彗星のように火花を散らしながら、光の曲線を描いた。”
〈私〉は自分が自由で確かな存在であることを感じながらゆっくりと歩き続けた。
だが、暫くすると、何かがひたひたと近づいてくる気配を感じるようになった。走ろうと思ったが出来なかった。背中から、ナイフを突きつけられている感触と、優しい声がした。
その穏やかな、恥ずかしげなと言ってもよさそうな声の持ち主は、〈私〉の目が欲しいというのだ。怖がらないでほしい。殺すつもりはない。ただ目が欲しいだけ。声の持ち主は、恋人のために青い目の花束を作りたいだけなのだ。
“恋人の気まぐれなんです。青い目の花束が欲しいって。この辺りに青い目をした者はほとんどいません”
男の出現から、それまで物語を覆っていた、潤んだような夢幻が霧消し、別の悪い夢が始まる。
愛し合う恋人同士に花束は欠かせないアイテムだ。
それがただの青い花束ならどうということはない。なのに、「青い」と「花束」の間に「目の」が入るだけで、途端に世界が足元から歪むような恐怖を感じる。男の妙に穏やかな口調が、シチュエーションの異様さを増長させる。そして、〈私〉が逃げ帰った宿の主人は、片目を失っているのだ……。
冷たくロマンティックな狂気に、青という色はよく似合うと思った。
М・A・アストゥリアス「グアマテラ伝説集」は、グアマテラの伝説をそのまま集めた作品集ではなく、伝説を下敷きにしたシュールレアリスム的な掌編集である。
本書にはその中から、「「火山」の伝説」、「「長角獣」の伝説」、「「刺青女」の伝説」、「「大帽子男」の伝説」、「「花咲く地」の財宝の伝説」、「春嵐の妖術師たち」の6篇が選ばれている。タイトルを並べただけで、詩的な異国情緒に陶然とする。
難解という感想が多いようだが、風も、花も、鳥も、海も、根も、道も、この世に存在するものがひとしなみに自我と魂を持っている世界観は大変心地よい。フレーズの一つ一つから、色彩と、香りと、命の息吹を感じた。
岩波文庫から『グアマテラ伝説集』が出ているので、そちらを読んでから感想を纏めようと思う。