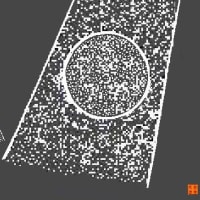幽霊パッション 第二章 水本爽涼

第五十七回
係員に控え票をもらうと、幽霊平林は大切に胸の襟元(えりもと)へ入れた。そして、とりあえず邪魔になるのでスコップ型を手でコンパクトに丸めた。さらに、輝く小球に変化したスコップは、控え票を挟んだ胸元へと納められた。幽霊平林は係員に、「また、お願いします」と云って軽く礼をすると、いつものようにスゥ~っと格好よく、その場を去った。
霊水が湧く小池に現れた幽霊平林は、僅(わず)かに十センチほどの溝を掘り始めた。もちろん、胸元へ納めた輝く小球を取り出し、スコップ型へと戻してからである。形状が自由自在に変えられる道具は、人間界では考えられない。作業衣は羽織って出たから、それで事は足りた。死んだ身だから、人間界とは違い汗が出ることはない。しかも、溝を掘るといっても、軽く線を引く感覚で溝になるのだから楽だ。それもその筈(はず)で、小池の周囲は人間界の地面ではなく、霞(かすみ)のような緑と茶色の霊気で覆(おお)われ、形作られていた。
さて、瞬く間に溝は出来上がっていき、とうとう幽霊平林の住処(すみか)まで近づいた。ここというところまで完成したとき、幽霊平林が小池を塞(ふさ)ぐ水門関を切ると、湧き出る水は当然、その作られた溝へと流れ、幽霊平林のの住処近くで溢れだした。そし、水流は低い方向へと下る。幽霊平林はその一角に瓶(かめ)を置き、水の嵩(かさ)による時の経過を知る算段を実行した。いわゆる、水時計の発想である。そして、これで上山がいる人間界が今、いつ頃なのか知ることが出来る…と、確信するのだった。一、二度は人間界へ現れ、時間を知る必要があった。その時間差で、どれだけの水嵩(みずかさ)が溜まるか、とうことである。一時間で一センチならば、五センチで五時間となる。もちろん、溝から瓶へ注ぎ入れる水量は少なく調整し、あとの水は下方へと流す。いわば、流水システムである。
ひと通り、作業を終えると、幽霊平林は瓶(かめ)を空(から)にした状態から、流入量の嵩の上昇が1センチに対し、一時間経過するという調整確認を済ませた。そして、瓶を流入口にセットし終えると、住処の小屋内へと入って静かに停止した。
最新の画像[もっと見る]












![連載小説 幽霊パッション 第三章 (第百五[最終]回)](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/19/cf/a4d652a78f65b5a64a7098195c68c8c7.jpg)