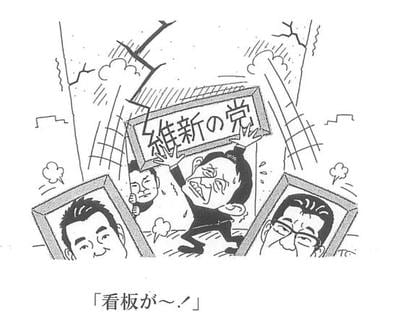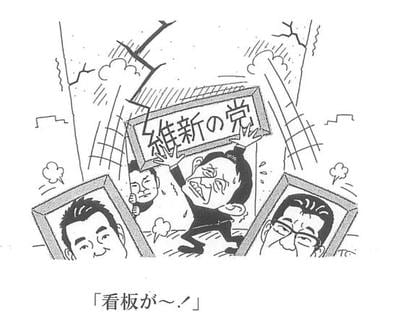
維新の党の橋下徹最高顧問(大阪市長)は27日午後の記者会見で「国政政党から離れ、大阪の地方政治に軸足を移す」と述べ、同党離党を正式に表明した。
同日は、松井一郎顧問(大阪府知事)も離党を表明。柿沢未途幹事長の地方選挙への対応をめぐる対立は党の「創業者」である橋下氏らの離脱に発展し、維新の内紛は深刻な局面を迎えた。
柿沢氏は、9月13日投開票の山形市長選で党の地元組織が反対している中、野党系候補の応援のため現地入り。これを松井氏らが問題視し辞任を迫っていた。
橋下、松井両氏の離党表明を受けて維新は27日、両院議員総会を国会内で開き、両氏の離党を事実上了承する一方、柿沢氏については続投を決めた。
☆
維新も大きな看板失いゴタゴタでもう残った議員の再選は無理だろう。野党さらに落ち目となり自民にくら替えする議員が出ると安部さん有利となるのか...。
「初耳で驚いている」。維新の党の橋下徹最高顧問(大阪市長)と松井一郎顧問(大阪府知事)が離党する見通しとなった27日、橋下氏が率いる地域政党「大阪維新の会」をはじめ、維新関係の地方議員らに衝撃が走った。両氏に近い大阪系の国会議員が集団離党する可能性も浮上し、党分裂含みのあわただしい動きに困惑が広がった。今後、両氏の任期満了に伴う11月22日投開票の大阪府知事、大阪市長のダブル選挙への影響が焦点となる。
「11月1日の党代表選まで動向を見極めてもよかったのではないか」
橋下、松井両氏が維新の党を離党し党が分裂の危機に直面-という衝撃のニュースに、ある大阪市議は困惑の声を上げた。
一方、別の若手市議は問題の発端となった柿沢未途幹事長の山形市長選をめぐる対応を批判し、「反発は当然。松井氏らを支持する」。ベテラン市議も松野頼久代表の態度を「煮え切らない」と非難した上で「橋下、松井両氏は『維新』の理念と異なる旧民主系や非大阪系と今後もやり合うことに見切りをつけたのだろう」と一定の理解を示した。
党代表選に向け党員獲得に奔走していた議員も多い中での離党劇。情報が錯綜(さくそう)し、地方議員の思いは揺れ動いた。大阪市議の一人は「党員になるようお願いした有権者にどう説明すればいいのか」と話したが、堺市議は「柿沢氏問題はけじめをつけるべきものだった。改革を続けてきた大阪維新としては何も揺らがない」と話した。
動揺は大阪以外の近畿の議員にも広がった。
維新の党京都府総支部の田坂幾太代表は「政党としてまだ成長段階にあり、いろいろ問題が起きるのは仕方がない」。同党兵庫県議団の関口正人副幹事長は「橋下、松井両氏は存在感があるので辞めるのは残念。党分裂の動きがあるなかでどうなるか不安」と懸念を示した。
地方議員も続いて離党するかどうかは突然の動きだったこともあって二分されている。ある大阪市議は「維新の党に思い入れはない。当然、離党することになる」と話す。「現段階では一緒に離党しようとのお誘いはなく、そんなに急がなくてもよい」(大阪府議)との声も上がった。
それよりも大阪の地方議員の関心の中心は、大阪ダブル選への影響だ。
一部には「国政をめぐるゴタゴタに労力を割かれるのでは」との懸念もあるが大阪維新の大阪府議団幹部は「離党するということはダブル選に集中するということ。松井氏は知事選に出るつもりだと受け取っている」と松井氏再選出馬の環境が整うとの期待感を示した。大阪市議団の大内啓治幹事長も「発祥の原点に立ち返って、大阪の地方改革に専念する、というメッセージが強まるのはよいことだ」と語った。
今後は近畿2府4県の地方議員で19日に発足したばかりの政治団体「関西維新の会」の国政政党化など改めて地方を起点とした国政への関与の仕方も焦点になる。
ある大阪市議はいう。
「任期満了での市長引退を表明している橋下氏を国政に、という声が再び上がるかもしれない」