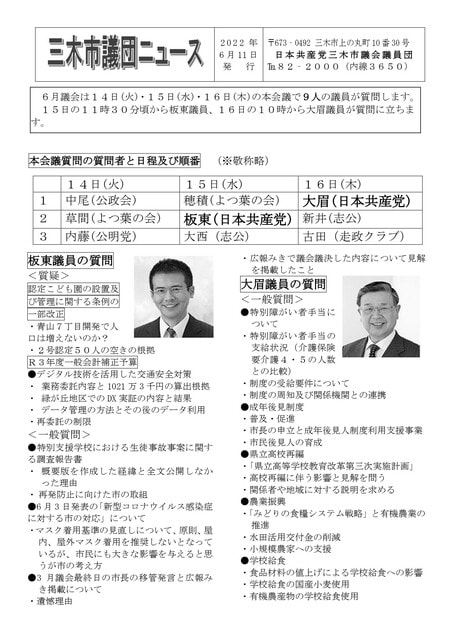第48号議案、三木市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について(スケートボードパーク)
Q1:利用料年間2,000円の根拠
(松原議員に対する答弁)県内施設の県内施設の料金が1回300円。それを参考に2,000円に設定した。
Q1:1回300円がなぜ年間2,000円の設定になるのか。
A1:県近隣市町の公共スケートボードパークの状況確認と併せて、三木スケートボードパークの減価償却費を含めた年間維持管理経費見込みを基に使用料を利用者に負担していただく場合の試算も行った。その結果、市内の方が御利用される場合は1人につき年額3,000円、市外の方が利用される場合は1人につき年額4,500円となった。
しかし、当施設は現在無料で、激変緩和の考慮や、誰でも気軽に利用できる施設として市民のコミュニケーションの場や市内外の住民の交流の場などの効果が期待出来ること、近年の利用登録者は子どもさんの割合が増えていることを重視し、試算結果の3分の2として市内利用者年額2,000円、市外利用者年額3,000円とした。
Q2:木曜日を休場日とする理由
(岸本議員の質問に対する答弁)指定管理者が管理する三木山総合公園が木曜日を休園としているから。
Q3:5歳未満の使用料
A:利用しやすい料金設定であるため、維持管理費経費の一部を利用者に負担してもらう。使用料は(正規で)もらう必要がある。ボードを使用されない付添いの保護者の方は無料。
Q4:指定管理者の管理範囲
A4:開園、閉園時の施錠管理、清掃、施設点検、除草作業。三木山総合公園で、案内、受付、使用料の徴収など。
Q5:使用料の未払い利用者とヘルメット未使用利用者の把握と対策
(松原議員の質問に対する答弁)スピーカーと連動した監視カメラを1台設置予定。
2回目以降
(板東)市内の方で2,000円、市外の利用者の方で3,000円は少し5歳未満に対しては高い。社会一般的に見ても、電車やバスなどの利用の際にも5歳児未満は無料。また、三木市の屋内プール場の使用料も幼稚園以下は無料。
Q:なぜスケートボードパークは例外なのか。
A:(都市整備部長)5歳未満の方もパークを占有して利用するので、一定の維持管理経費等を負担するのが適正と考える。
(板東)三木山総合公園の(5歳未満のプール)利用者は当然無料で今使用している。小さなお子さんたちが利用しやすいように、たくさん来てもらえるようにというのが趣旨ではないか。スケートボードパークも、同じように考えるべき。使用料を維持管理の足しにする考え方は理解するが、そこに5歳未満まで徴収するのは、ちょっと行き過ぎ。
Q:カメラの台数、柵から侵入する利用者の管理方法は。
A:カメラは、1台設置を考えている。ズーム機能で広角や狭角での映像を捉える。また、巡回管理も行い、未払い利用者には声をかける。
(板東)巡回管理の頻度を増やせば人件費がかかる。カメラの台数を増やすことも一つの考え方だと思う。
Q:今回の監視カメラの管理で、人数把握もできるのか。
A:指定管理者に一定利用状況を確認し人数把握に努めてもらう。
(板東)土日は体育館の利用者も多く、管理者の負担も大きくなる。アプリによる管理など、安価な方法は模索できないのか。研究して欲しい。