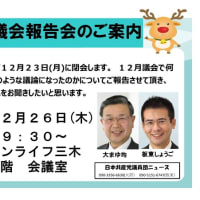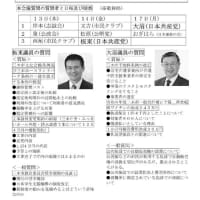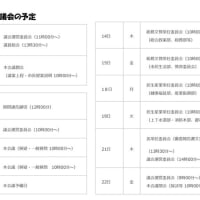12月議会が始まりました。
1日目の今日は市長から議案提案と決算の採決が行われました。
私は、平成24年度決算について反対討論を行いました。討論原稿をアップします。
日本共産党の板東聖悟でございます。私は、平成24年度一般会計歳入歳出決算、介護保険特別会計決算、後期高齢者医療事業特別会計決算の3件について、反対の討論を行います。
まず、一般会計歳入歳出決算についてでございます。
一般職の市職員の給与が本来の給与より6%から8%下げられました。本来、賃下げについては、労働組合と交渉をして合意の上ですべきものであります。また、地方公務員の給与体系は民間企業の給与体系にも影響を及ぼすものでもあります。
一方で、職員の数をどんどん減らしています。委員会の議論の中では人口1000人に対して6人の職員にするという三木市独自の目標があることをお聞きしました。職員削減の穴埋めとして業務委託、アルバイトや派遣職員を増やしています。これでは業務がやっていけないと悲鳴を上げている管理職の声をたくさん聞いています。
学校給食の委託化について決算特別委員会の議論の中で同一水準であれば直営方式でなく委託すればいいではないか、同一職種の中では公務員給与は高いので委託化により人件費を削減することは必要ではないかという議論がありました。
まず、何が同一水準なのか考える必要があると思います。生徒・児童に出される食事は同じ材料で同じ調理方法で行えば確かに同一水準なのでしょう。しかし、それは食事提供の観点しか見てないのではないでしょうか。学校給食は食育という観点が必要です。現在各調理場に配置された栄養士がその推進の大きな役割を担っています。
三木市教育振興基本計画には具体的な食育の推進項目として
○家庭・地域と連携した食育の推進
○食に関する指導計画の作成
○地元産食材の使用
○行事食、季節食などを取り入れた献立の工夫
などが上げられています。
ここで、栄養士が調理員どこまで業務の指示をするのか。また、調理員がそれに答えられるのか。公務員としての調理員と事業者としての調理員が同一水準の仕事が出来るのか。一般的な調理業務と学校給食の調理業務は同一職種ではありますが求められる仕事は大きく違ってくるのではないでしょうか。
これらのことは、調理業務に限った事ではなく、公務員の行っている業務全般に言えることだと思います。公務員の仕事にこれだけやっていればいいという仕事は無いと思います。効率化も勿論大事ですが、よりクオリティの高い市民サービスを追求することが必要です。担当部署では、誰よりもその分野について精通して必要な時には上司にも意見を言い、市民には分かりやすく説明出来る職員が求められています。また、全庁的に公務員一人ひとりが一市民として地域の問題点に気づき、迅速に対応することも求められています。
職責のある職員は上司からの指示を部下に押し付けるだけでなく、部下の意見も十分取り入れながら、必要な時には上司にも意見を申し上げる。市民の為にならないと思う事案には、しっかり対案を示して上司に意見することが求められています。
首長は市民にしっかりビジョンを示し、市民や部下の意見を聞く度量が必要です。また職員を信頼し職員の能力を伸ばすための環境を整備することが大切です。
公務員パッシングに同調するのではなく、「職員は何処の市よりも住民サービスに徹し、政策立案能力を持っている。市職員の賃金を下げたり、職員の数を減らすことは市民の皆さんへのサービスの質を落とすことになるので行わないと」言って頂ける日が来ることを待ち望んでいます。
また、先程、調理業務の委託の話を致しましたが、民営化や民間委託がすすめられていることにもう一言申し上げます。この度水道料金徴収業務を委託していた事業者の所長が水道料金を横領していたことが今年9月26日に発覚しました。この問題は事業者所長と委託事業者の責任として幕引きがなされました。市としての責任はないとのことでした。
一方で他の市において職員横領事件がありました。本人は勿論懲戒免職処分となり、監督責任を怠ったとして、当時担当の課長が減給懲戒処分、市長も市議会に減給を提案しています。
この場で三木市の責任を追及することはしませんが、三木市の態度として、業務委託というのは業務の合理化だけではなく、行政の責任がなくなることを意味することが明らかになったということではないでしょうか。今後の民営化・民間委託化についても市民サービスが低下しても行政として責任を取らないことが考えられます。
商工業振興関連では企業誘致促進事業として9100万円が使われました。この事業の対象となったのは、9社で1社あたり1000万円の助成を1年間の間に受けたことになります。正規社員として働いているのは169名で三木市在住の正規社員を雇用している企業に対して助成される雇用助成は41名が受けています。三木市内の企業なのに三木市民は25%弱しかいないことになります。
勿論アルバイト、パート、派遣社員などの雇用の場はそれ以上に広がっていますし、出入り業者等の波及効果も一部あることも理解しています。しかし、今一番求められているのは、三木市民にとって正規社員が当たり前の社会を目指すことだと思います。また、本当に元気にならなければならないのは、地元の中小企業であります。地元の中小企業の実態調査を行って、行政が求められる支援が何なのかを聞いて、そこへの予算の投入と施策を行うべきだと考えます。
人権に関する事業がたくさんあります。人権に関する問題がをはじめとする差別問題だけを問題とするのは本来の人権問題として狭すぎます。憲法は国家権力が国民の権利を侵害しないためにたくさんの縛りかけて、国民の権利を保障しています。
三木市が人権啓発の事業を行うのであれば、憲法そのものを学習する必要があるし、どんな権利があるのか、それをどうすれば行使できるのかを市民に教える必要があります。サービス残業を強いられている市民にはそれが違法であることと、何処に相談すればいいのかを教える必要があります。生活保護の申請用紙を窓口に置くなど申請しやすくするとともに申請を却下され、最低限の生活が保障されないと感じている市民には不服申し立ての手続きの仕方を教える必要があります。人権問題をもっと広く捉えて、啓発事業を行うべきです。
三木市独自の母子父子年金の福祉年金がなくなりました。国の制度で子ども手当が支給され現状より6万円程度所得がふえるという理由でした。子ども手当の制度は国の政権が民主党から自民党に変わり廃止されました復活させるべきだと考えます。
また、国が社会保障制度をどんどん改悪する中で、三木市は最低限の生活を保障し、三木市民が人間らしく生きられるための社会福祉保障を行うべきです。
次に三木市介護保険特別会計決算についてです。
本来、介護保険は国の制度であり、問題は国にあると理解しています。しかし、地方公共団体は国政の問題点に対しては市民の立場で対抗することが求められています。三木市として所得段階を6段階から8段階という区分へ変更するなどの努力はなされています。しかし、それでもなお非課税の方に対しても月500円以上のさらなる負担を強いるわけで、介護保険料の抑制のために一般財源を入れるべきだと考えます。
次に、後期高齢者医療事業特別会計決算についてです。
後期高齢者医療制度とは75歳以上の高齢者を別枠の医療保険に囲い込み、高い負担を押しつけ、診療報酬も別立てにすることで安上がりの差別医療を押しつけ医療費削減を目的につくられた制度であり、この制度にそのものに反対であります。
保険料は2年ごとに改定されますが、2010年の改定では平均で1,054円引き上げられました。さらに2014年度の保険料は、均等割額が46,003円と2,079円の引き上げ、所得割率が9.14%と0.91ポイントの引き上げで被保険者平均では75,027円と4,310円、6.09%引き上げになっています。75歳以上人口の増加と医療費増が、保険料に直接はね返る仕掛けになっているためです。今後もさらに上がることは避けられません。
年金が減額されるなど、高齢者の生活がますます苦しくなっているなかで高齢者の負担軽減を求めるものであります。
公的年金からの保険料天引き対象外になっている低年金・無年金の高齢者など保険料を払えない滞納者数がおられます。それらの人に対し、病院窓口で全額負担となる資格証明書の発行はされておりませんが、有効期間が短い短期保険証の発行が行われています。有効期限が切れているにもかかわらず短期保険証が手元にない高齢者もあります。
また、保険料の軽減や一部負担金減免の充実、また健診内容の充実など、高齢者の健康を増進するために力を尽くすことを強く求めるものであります。
病気になりがちなうえ、収入の手段も限られている高齢者だけをひとつの医療制度に集め、“負担増か、給付減か”を迫る後期高齢者医療制度を廃止しすべきであり、高齢者が安心して医療を受けることができる制度にすべきであります。
以上3件の決算についての反対討論と致します。
1日目の今日は市長から議案提案と決算の採決が行われました。
私は、平成24年度決算について反対討論を行いました。討論原稿をアップします。
日本共産党の板東聖悟でございます。私は、平成24年度一般会計歳入歳出決算、介護保険特別会計決算、後期高齢者医療事業特別会計決算の3件について、反対の討論を行います。
まず、一般会計歳入歳出決算についてでございます。
一般職の市職員の給与が本来の給与より6%から8%下げられました。本来、賃下げについては、労働組合と交渉をして合意の上ですべきものであります。また、地方公務員の給与体系は民間企業の給与体系にも影響を及ぼすものでもあります。
一方で、職員の数をどんどん減らしています。委員会の議論の中では人口1000人に対して6人の職員にするという三木市独自の目標があることをお聞きしました。職員削減の穴埋めとして業務委託、アルバイトや派遣職員を増やしています。これでは業務がやっていけないと悲鳴を上げている管理職の声をたくさん聞いています。
学校給食の委託化について決算特別委員会の議論の中で同一水準であれば直営方式でなく委託すればいいではないか、同一職種の中では公務員給与は高いので委託化により人件費を削減することは必要ではないかという議論がありました。
まず、何が同一水準なのか考える必要があると思います。生徒・児童に出される食事は同じ材料で同じ調理方法で行えば確かに同一水準なのでしょう。しかし、それは食事提供の観点しか見てないのではないでしょうか。学校給食は食育という観点が必要です。現在各調理場に配置された栄養士がその推進の大きな役割を担っています。
三木市教育振興基本計画には具体的な食育の推進項目として
○家庭・地域と連携した食育の推進
○食に関する指導計画の作成
○地元産食材の使用
○行事食、季節食などを取り入れた献立の工夫
などが上げられています。
ここで、栄養士が調理員どこまで業務の指示をするのか。また、調理員がそれに答えられるのか。公務員としての調理員と事業者としての調理員が同一水準の仕事が出来るのか。一般的な調理業務と学校給食の調理業務は同一職種ではありますが求められる仕事は大きく違ってくるのではないでしょうか。
これらのことは、調理業務に限った事ではなく、公務員の行っている業務全般に言えることだと思います。公務員の仕事にこれだけやっていればいいという仕事は無いと思います。効率化も勿論大事ですが、よりクオリティの高い市民サービスを追求することが必要です。担当部署では、誰よりもその分野について精通して必要な時には上司にも意見を言い、市民には分かりやすく説明出来る職員が求められています。また、全庁的に公務員一人ひとりが一市民として地域の問題点に気づき、迅速に対応することも求められています。
職責のある職員は上司からの指示を部下に押し付けるだけでなく、部下の意見も十分取り入れながら、必要な時には上司にも意見を申し上げる。市民の為にならないと思う事案には、しっかり対案を示して上司に意見することが求められています。
首長は市民にしっかりビジョンを示し、市民や部下の意見を聞く度量が必要です。また職員を信頼し職員の能力を伸ばすための環境を整備することが大切です。
公務員パッシングに同調するのではなく、「職員は何処の市よりも住民サービスに徹し、政策立案能力を持っている。市職員の賃金を下げたり、職員の数を減らすことは市民の皆さんへのサービスの質を落とすことになるので行わないと」言って頂ける日が来ることを待ち望んでいます。
また、先程、調理業務の委託の話を致しましたが、民営化や民間委託がすすめられていることにもう一言申し上げます。この度水道料金徴収業務を委託していた事業者の所長が水道料金を横領していたことが今年9月26日に発覚しました。この問題は事業者所長と委託事業者の責任として幕引きがなされました。市としての責任はないとのことでした。
一方で他の市において職員横領事件がありました。本人は勿論懲戒免職処分となり、監督責任を怠ったとして、当時担当の課長が減給懲戒処分、市長も市議会に減給を提案しています。
この場で三木市の責任を追及することはしませんが、三木市の態度として、業務委託というのは業務の合理化だけではなく、行政の責任がなくなることを意味することが明らかになったということではないでしょうか。今後の民営化・民間委託化についても市民サービスが低下しても行政として責任を取らないことが考えられます。
商工業振興関連では企業誘致促進事業として9100万円が使われました。この事業の対象となったのは、9社で1社あたり1000万円の助成を1年間の間に受けたことになります。正規社員として働いているのは169名で三木市在住の正規社員を雇用している企業に対して助成される雇用助成は41名が受けています。三木市内の企業なのに三木市民は25%弱しかいないことになります。
勿論アルバイト、パート、派遣社員などの雇用の場はそれ以上に広がっていますし、出入り業者等の波及効果も一部あることも理解しています。しかし、今一番求められているのは、三木市民にとって正規社員が当たり前の社会を目指すことだと思います。また、本当に元気にならなければならないのは、地元の中小企業であります。地元の中小企業の実態調査を行って、行政が求められる支援が何なのかを聞いて、そこへの予算の投入と施策を行うべきだと考えます。
人権に関する事業がたくさんあります。人権に関する問題がをはじめとする差別問題だけを問題とするのは本来の人権問題として狭すぎます。憲法は国家権力が国民の権利を侵害しないためにたくさんの縛りかけて、国民の権利を保障しています。
三木市が人権啓発の事業を行うのであれば、憲法そのものを学習する必要があるし、どんな権利があるのか、それをどうすれば行使できるのかを市民に教える必要があります。サービス残業を強いられている市民にはそれが違法であることと、何処に相談すればいいのかを教える必要があります。生活保護の申請用紙を窓口に置くなど申請しやすくするとともに申請を却下され、最低限の生活が保障されないと感じている市民には不服申し立ての手続きの仕方を教える必要があります。人権問題をもっと広く捉えて、啓発事業を行うべきです。
三木市独自の母子父子年金の福祉年金がなくなりました。国の制度で子ども手当が支給され現状より6万円程度所得がふえるという理由でした。子ども手当の制度は国の政権が民主党から自民党に変わり廃止されました復活させるべきだと考えます。
また、国が社会保障制度をどんどん改悪する中で、三木市は最低限の生活を保障し、三木市民が人間らしく生きられるための社会福祉保障を行うべきです。
次に三木市介護保険特別会計決算についてです。
本来、介護保険は国の制度であり、問題は国にあると理解しています。しかし、地方公共団体は国政の問題点に対しては市民の立場で対抗することが求められています。三木市として所得段階を6段階から8段階という区分へ変更するなどの努力はなされています。しかし、それでもなお非課税の方に対しても月500円以上のさらなる負担を強いるわけで、介護保険料の抑制のために一般財源を入れるべきだと考えます。
次に、後期高齢者医療事業特別会計決算についてです。
後期高齢者医療制度とは75歳以上の高齢者を別枠の医療保険に囲い込み、高い負担を押しつけ、診療報酬も別立てにすることで安上がりの差別医療を押しつけ医療費削減を目的につくられた制度であり、この制度にそのものに反対であります。
保険料は2年ごとに改定されますが、2010年の改定では平均で1,054円引き上げられました。さらに2014年度の保険料は、均等割額が46,003円と2,079円の引き上げ、所得割率が9.14%と0.91ポイントの引き上げで被保険者平均では75,027円と4,310円、6.09%引き上げになっています。75歳以上人口の増加と医療費増が、保険料に直接はね返る仕掛けになっているためです。今後もさらに上がることは避けられません。
年金が減額されるなど、高齢者の生活がますます苦しくなっているなかで高齢者の負担軽減を求めるものであります。
公的年金からの保険料天引き対象外になっている低年金・無年金の高齢者など保険料を払えない滞納者数がおられます。それらの人に対し、病院窓口で全額負担となる資格証明書の発行はされておりませんが、有効期間が短い短期保険証の発行が行われています。有効期限が切れているにもかかわらず短期保険証が手元にない高齢者もあります。
また、保険料の軽減や一部負担金減免の充実、また健診内容の充実など、高齢者の健康を増進するために力を尽くすことを強く求めるものであります。
病気になりがちなうえ、収入の手段も限られている高齢者だけをひとつの医療制度に集め、“負担増か、給付減か”を迫る後期高齢者医療制度を廃止しすべきであり、高齢者が安心して医療を受けることができる制度にすべきであります。
以上3件の決算についての反対討論と致します。