佗の茶は、茶室を狭くし暗くすることで、視覚に無駄な情報を与えないようにしました。入口は人が入れるほどの広さにし、壁で囲った部屋の中では、釜の煮え音や茶筅を振る音しか聞かせません。触れることができるのは、茶の入れものである茶碗と、茶の器である茶器など、限られたものになります。茶の味や香りを保持する努力は、茶葉の選定や、茶壺や保存方法の工夫に見ることができ、食事としての懐石は、淡い味付けにしてあります。それは、茶の香りに触らないようにとの心遣いであり、炭の香りにも心を配り香を焚くほどです。茶室・炭手前・懐石・茶道具・所作などすべてを必要最小限にしていくことで、それぞれの本質を知ろうとしたのです。わび茶は、可能な限り、余分というものを排除していくことにより、五感の働きを最小限に制御し、茶道の本質を浮び上がらせようとする実践なのであります。
最新の画像[もっと見る]
-
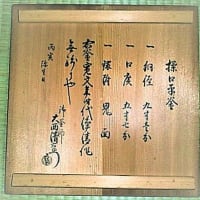 如月(きさらぎ)の釜
7年前
如月(きさらぎ)の釜
7年前
-
 如月(きさらぎ)の釜
7年前
如月(きさらぎ)の釜
7年前
-
 無賓主の茶会 熊谷市 星渓園
7年前
無賓主の茶会 熊谷市 星渓園
7年前
-
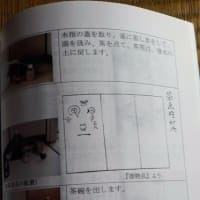 点前指南書 第二回配布
7年前
点前指南書 第二回配布
7年前
-
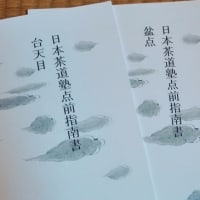 点前指南書 第二回配布
7年前
点前指南書 第二回配布
7年前
-
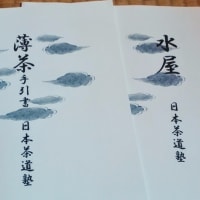 点前指南書 第二回配布
7年前
点前指南書 第二回配布
7年前
-
 子ども芸術大学
8年前
子ども芸術大学
8年前
-
 掛川東山 茶の歴史紹介マップ
8年前
掛川東山 茶の歴史紹介マップ
8年前
-
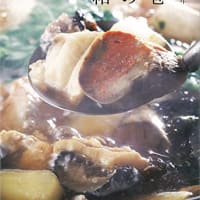 日本茶道塾東京初釜 平成二十九年
8年前
日本茶道塾東京初釜 平成二十九年
8年前
-
 雪竇寺 中韓日仏教大会の花 ご報告
8年前
雪竇寺 中韓日仏教大会の花 ご報告
8年前









