
「エトワール」
昔は「舞台の踊り子」と云っていたのですが、何時の頃からか、
このような呼び名に変わりました。
もっとも「スターの踊り子」と云う別名がありましたから、スター
すなわちエトワール(星)と呼ばれるようになったものと思われます。
エトワールとは、パリのオペラ座でプリンシパル(主役を踊る踊り
子)のなかでも特に花形だけに与えられる称号だそうです。
脂の乗ったドガ42、3歳(1876-7年)のときの作品ですが、
僅かに58×42cmの小品です。
しかし、そのコンポジションと云うか空間処理の巧みさが、絵に
実物以上の大きさを感じさせます。
僕が初めてこの図版を眼にしたのは中学生の頃だと思うのですが、
煌くような甘美なエトワールに魅入られて以来幾星霜、やっと今年
実物と向合うことができました。
横浜美術館「ドガ展」(9/18~12/31)にて。
パステル画へと僕を誘った絵ですから、心ときめくのは当然のこと。
でもそれはパッションと云うより、感慨にふけると云う表現が相応
しいものでしたが。
未だご覧になっていない方、12/9、12/16は休館ですが、後は大晦日
までやっています(10:00~18:00、金曜日は20:00まで)ので、この
機会に是非足をお運びください。
「エトワール」は、今回が日本初公開。僕等の足腰が丈夫なうちに
再び巡ってくるかどうか。と云うわけで、お見逃し無く。
ブログトップへ戻る











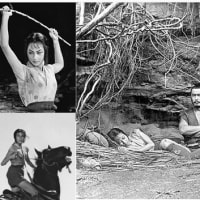
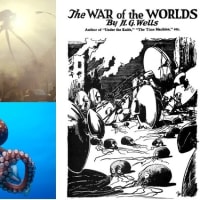







週刊新潮12月16日号のコラム「B級重大ニュース」に「龍馬婚
約者のその後」と題して千葉佐那が結婚していた旨の記事が載って
いたのでビックリ!
しかも本の記事は7月だったと云うのですから、迂闊と云うか・・・。
それでその本記事を探してみたら、7月3、4日のスポニチでした。
3日のものは「“龍馬のいいなずけ”暗殺後に結婚していた?」、
4日のものは「龍馬ショックぜよ!?千葉佐那、結婚していた」、
とそれぞれ題するもので、それらを要約すると以下のような内容に
なります。
明治期に横浜で創刊された毎日新聞(現在の毎日新聞とは無関係との
こと)に明治36年8月から11月まで連載された記事「千葉の名灸」
は、佐那(明治29年10月15日に没)の親族に取材して千住の千葉
灸治院の来歴などを書いたものですが、その中の10月4、5日の記
事によると、「1873(明治6)年に横浜に移り住んださなが、定吉
が剣術師範役を務めていた鳥取藩の元藩士山口菊次郎から求婚され、
龍馬の七回忌も済んだことから受諾した。しかし家格の低さもあり定
吉が反対。『おまえの命はかつて龍馬の霊前にささげようとしたもの
ではなかったのか』などと怒ってさなを切ろうとしたため、近くの商
家が仲裁に入り、翌年(明治8年)7月に結婚した。菊次郎の身持ちの
悪さなどから、10年たたず離縁、千住に移り住み亡くなるまで再婚
しなかった」とあるそうです。
週刊新潮の記事で補足すると、「菊次郎は維新後、東京で魚市場を設
立すると称して主家の親戚(幕末期は兄弟の関係)にあたる旧岡山藩主
池田家から預った出資金を返さず訴えられた」とあり、この金銭トラ
ブルも離縁の原因のひとつとしています。
この古記事を発見した歴史研究家のあさくらゆう氏は、旧鳥取藩主の
伝記などから、菊次郎の名前や当時横浜在住だったことを割り出して、
横浜市史の関連文書から商家の存在まで確認しているそうですから(た
だし佐那の横浜時代の戸籍などの資料は関東大震災や戦災で焼失)、信
憑性は高そうです。
ちょっとショック!
聞本誌に「千葉さなの錦絵発見」との記事があったそうです。
錦絵の右下に「千葉貞女」と書かれてあるものですから、慌て者が
千葉定(貞)吉の娘(女)、すなわち佐那に違いないと飛び付いたので
しょう。
宇和島藩八代藩主伊達宗城が残した記録を纏めた『稿本藍山公記
(こうほんらんざんこうき)』によると、安政3年(1856年)に
19歳だった佐那が伊達家の姫君の剣術師範として伊達屋敷に通
っていたことの他に、宗城の感想として「左那ハ、容色モ、両御
殿中、第一ニテ」(佐那は腕前だけでなく容色の点でも、2つの宇
和島藩江戸屋敷に出入りする女性の中で一番である)とあり、その
容貌を知りたくなるのが人情と云うものですが、NHKで「龍馬伝」
が話題になっていた時と云うのがミソ。
後に千葉周作の孫の周之助之胤、その姉妹にあたる千葉貞(てい)で
あることが分かりました。
この錦絵が描かれた撃剣会の番付表が残っており、そこに「千葉
てゐ」の名前が確認(明治6年に深川で開催された千葉一門の撃剣
会の様子を描いた3枚1組の錦絵)できることや、菩提寺の仁寿院
の墓所にも「千葉貞」の名前が刻まれていること。
東都新聞の明治17年7月19日版にも千葉貞が当時、神田錦町
にあった玄武館で長刀を教えているという記事が存在するとのこと。
幸いにも後世に誤って伝えられるようなことには至りませんでしたが、
この慌て者、例の若き日のお龍と称する写真を平成13年に再び持ち
出した張本人でもあるのです。
僕のような市井の無頼の徒の戯言ならいざ知らず、この慌て者、れ
っきとした京都国立博物館の学芸員(主任研究官)なのです。
そもそもその写真が若き日のお龍の写真発見として発表されたのは
昭和57年12月22日付の高知新聞でした。
龍馬研究(立命館史学会員)の西尾秋風(平成15年2月6日没)が発表
したもので、以下のものです。
「来る一月十五日は、坂本竜馬の妻お竜(明治八年に再婚して西村つ
ると改名)の七十八回忌である。この日を目前にして、彼女の若き日
の艶姿写真を発見したのである。
だいたいお竜の写真は、明治三十一、二年ごろに撮した六十歳ぐらい
のもの一枚きりということになっていた。ところが今回新発見のもの
は、近江屋(竜馬が遭難死した寄宿先)のご子孫井口新助氏所蔵のアル
バムから撮影させていただいたものである。他のいわゆる維新の志士
と称せられる人物の肖像写真と一緒に保存されているため、これらの
志士たちとも有縁の女性と推察され、あるいは若き日の寺田屋お登勢
か、お竜かとも思えたのであるが、裏面に記名がなく、空しく放置さ
れていた。
さて最近、以外な事実が判明した。お竜こと―西村つる女の子孫が京
都で健在だったのである。京都市下京区に住む西村兵造氏は、お竜の
第二の夫(西村松兵衛)の兄兵蔵の直系で、その祖母ふさ刀自(明治五年
生まれ)は兵蔵の二女で、お竜の養女となっていた。同氏は『この写真
に見覚えがある。祖母の所持品で、小学二、三年ごろ、たしかに手に
とった記憶がある…』と言う。この写真はバックの特色から、明治初年、
東京浅草で開業の内田九一スタジオであることが判明、お竜は明治四~
七年ごろ(三十一~四歳)東京にいた形跡がある。この写真は、まさに
本邦最初の見合い写真かもしれない……。」
養女の孫にあたる西村兵造というひとが語る「この写真に見覚えがある。
祖母の所持品で、小学二、三年ごろ、たしかに手にとった記憶がある…」
と云うのでは、何とも心許無いですね。
「お竜かとも思えたのであるが、裏面に記名がなく、空しく放置されて
いた」ものが、京都国立博物館に寄贈されたこのアルバムの写真には、
鉛筆で「お竜」と書かれてあるのですから不思議としか云いようがあり
ません。
『竜馬がゆく』で龍馬ブームの巻き起こった後のことですから、わざと
「竜」の文字を使用して記事を書いたのかしらん、なんて思ったら大きな
間違いかもね。意図的に「竜」を使用したとしたら・・・。
もう一枚(椅子に腰掛けた写真)の裏書に「たつ」とあることを聞き付けて、
「辰」から「竜」、そして「お竜」に繋げようとしたのであればかなり悪
質です。それを西尾秋風が行ったかどうか分かりませんが、筆跡鑑定くら
いは行ってしかるべきです。
この若き日のお龍の写真とされているものが、偽者であるという理由は
以前に(「つぶやきの部屋4」、「団塊の世代雑感(32)」「同(37)」
などで)触れましたが、新たな論証として、「内田九一は一般庶民の撮影を
行っていなかったので、九一没後に同写真館を継いだ長谷川吉次郎により
明治九年ないし十年に撮影されたものと考えられることから(そのときには
お龍は東京には居ないし、年齢も三十六、七歳になっているので)、年齢的
に合わない」とし、「写真は東京土産として写真館で売っていたプロマイド
で、モデルは吉原か深川あたりの芸者である」とするものがあります。
さらに別の論者は「内田写真館の内装が変わっていなければ」との前提で、
「明治十四年十月一日『旧内田舎』の屋号で再開させた北庭筑波撮影の可能
性も含め考慮すべき」とし、「風俗写真や写真館の見本写真ではないか」と
推察しています。
これだけ反論・反証のある胡散臭い代物を京都国立博物館学芸員の身であ
りながら再び取り上げて、「新発見『おりょう』さんの古写真」(新人物往
来社編『歴史読本―特集新選組最後の戦い―』平成十四年二月号)なんて書
いたりもしているのはどうなんでしょうか。
先の佐那の錦絵の一件と云い、功名心に逸った粗忽さは学者としては不適
格としか思えません。
スポニチの7月21日の記事に「坂本竜馬もビックリ!写真無断使用?おり
ょうの切手販売中止」と云うのがありました。
京都市内の郵便局で販売していたオリジナルフレーム切手「龍馬が駆け抜け
た町 京都・伏見」(龍馬やお龍の写真をカラーにした80円切手が10枚
シートになったもので、8日から1セット1200円で発売)の販売を中止
したと云うものです。
「神戸市の印刷会社が企画、製作し」とありますから、「つぶやきの部屋
5」に掲載した龍馬のカラー写真を手がけたサンメディアと云う会社が企
画・製作したものだと思います。
中止の理由は、13日に匿名で「おりょうの写真は無断転用ではないか」と
郵便局会社近畿支社(大阪市)に電話があったからだと云います。
「切手に使用された写真は東京都の古写真研究家の井桜直美さん(45)が
所有しているものとそっくりで、井桜さんは『切手を見る限り、わたしが
持っている写真だと思う。神戸市の印刷会社からは何の連絡もなかった』
と話している。」と記事にありますので、例の若き日のお龍とされている
写真(それも椅子に腰掛けた方かも)であることは確か。
兎にも角にも、そんなものが出回らなくて良かったと思います。
今日、旧暦だと11月15日なんです。慶応3年のときには12月
10日でしたが。
当時は、それも京都盆地のことですから、もう寒かったのですが、
それに比べて今年は暖かいですよね。特に東京、それも海に近い大
田区は。
それでちょっと外出しました。暖かい大田区からちょっと低めの
千代田区と中央区の間へ。
そこに「最後の忠臣蔵」が掛かっていたからです。
本所松坂の吉良邸へ赤穂浪士が討ち入ったのは元禄15年12月
14日(不定時法での話。実際に討ち入ったのは15日の午前4時
頃)。西暦だと1703年1月31日に当たりますので、雪が降っ
ていても当たり前ですが、それは芝居「仮名手本忠臣蔵」での脚色。
実際は快晴だったそうです。
それでこの時期になると「忠臣蔵」が色々な形で掛かることになる
のですが、この「最後の忠臣蔵」はちょっと毛色が違っていて、討
ち入りから16年後の話。
討ち入った四十七士の一人で、大石内蔵助から「真実を後世に伝え、
浪士の遺族を援助せよ」との命を受けた寺坂吉右衛門(佐藤浩市)と、
内蔵助からの密命を帯びて、討ち入り前夜に姿を消した瀬尾孫左衛
門(役所広司)の物語です。もっとも物語は瀬尾孫左衛門と内蔵助の
隠し子である可音(かね、桜庭ななみ)が軸となって展開して行くの
ですが。
池宮彰一郎の原作には無い人形浄瑠璃(近松門左衛門の「曽根崎心中」)
が効果的に使われていて、瀬尾孫左衛門と可音のそれぞれの心の葛藤と
か行く末の隠喩となっていて、物語りに奥行きを与えています。
今年は時代劇の当たり年で、何本も上映されましたが、残念ながら僕が
観たのは3本だけ。
あとの2本は「十三人の刺客」(9月、リメイク版)と「桜田門外ノ変」
(10月)ですが、「最後の忠臣蔵」は抜きん出て良い作品だと思います。
あちこちで鼻をすする音やハンカチで目頭を押さえる姿が。ま、涙腺
の緩んでいるシルバー世代が大半だから仕方ないか。
まだ始まったばかりですし、ロングランになるような気もしますが、何せ
時季物ですので、なるべくお早目にご賞味くださいますよう。
♪ラリラリラリラ しらべは アマリリスよ
ラリラリラリラ しらべは アマリリス
小学校で習いましたよね。でも覚えているのは、上記のフレーズだけ。
だけど調べてみたら、歌詞も違っていました。
正しくは
♪みんなで聞こう 楽しい オルゴールを
ラリラリラリラ しらべは アマリリス
月の光 花園を あおく照らして
ああ 夢を見てる 花々の眠りよ
フランスみやげ やさしい その音色よ
ラリラリラリラ しらべは アマリリス
でした。
メロディーもうろ覚え。これもインターネットで調べてみたら、転調
するところがあって、それが「月の光~花々の眠りよ」の箇所なのか
しらん。
フランスの民謡なのに、作曲者の名前はヘンリー・ギース。英国人の
ような名前ですが、フランスの読みではアンリ・ギス。どのような人
物なのか謎に包まれているのですが、ルイ13世が作曲者とされてい
た時期もあったことから、暗殺された父アンリ4世と関係があるのか
もしれません。
原詩がどのようなものであったのか全くもって存じませんが、ローマ
の詩人ヴェルギリウスが作った詩が、曲名からしてそれではないかと。
なぜならその詩に登場する羊飼いの娘がアマリリスと云う名だからです。
日本にはオルゴールの曲として入ってきたのでしょう。それで岩佐東一
郎が上記のような日本の歌詞を付けたのだと思います。転調のところの
歌詞からして、岩佐は唱歌として相応しい同名の花に置き換えたのでし
ょう。
実は、昨年の12月中旬に友人から鉢植えのアマリリスを頂いたのです。
曖昧ながらも歌は覚えていても、花の実物は見たことがありません。
頂いたときは芽が僅かに顔を出しているような状態ですから、どのような
花が咲くのか全く知識の無い僕には見当も付きません。
直径が14cmほどの鉢に二つの芽があるので、小さな花が咲くのかしら
ん、などと暢気に構えて、一週間に一回、コップ一杯の水遣りをしていた
ら、あれよあれよと云う間に茎がどんどんと逞しく伸びていって、50数
cmにもなって、その先端に合掌したような蕾が一つあって、それが花開
くのだろうと思っていたのですが、パカッと割れたら中に四つの蕾があっ
て、それが水遣りしてから丁度一月後にまず一輪が花開き、次から次へと
四つとも開花。赤味がかったピンクに白い筋の入ったその花の大きなこと。
6枚の花弁から成っているのですが、直径は18cmもあろうかと云うほ
どの大輪の花が、古い蓄音機のラッパのように、四方に向いて一斉に花開
いた有様は頭でっかちの赤子のようで、甚だバランスに心許無い思いがし
たものですが、もう一本の茎と4枚の大きな葉とが巧みに連携しあって上
手くバランスを取っているのです。
その四輪の花がしぼみ始めようとするときに、もう一つの茎の四輪が花開
き始めました。小さな鉢植えで大きな花が8つも咲いているのですから、
平均台の上でのV字バランスのような超技巧で、茎や葉の向きを変えてし
っかり踏ん張っている有様は健気としか云い様がありません。
それ以外はちょっと高い台の上に置いていました。
初めに花開いた方が大分枯れてきたので、そろそろその茎を根元から切ら
なければと思っていた矢先のこと、一辺に四輪とも萎んでしまって、微妙
なバランスが崩れたのでしょうか、台の上から転げ落ちてしまったのです。
後から開花した四輪の花の一つが、その花弁を一つ失いました。それと4
枚あった葉のうちの2枚が根元から折れてしまいました。
それで古い方の茎を根元から切り取ったのですが、切り口から赤い血なら
ぬ透明の水滴がポタリと落ちたときには心が一寸疼きました。
それでも残った一本の茎は、二本あったときには互いがV字状に傾いてい
たのですが、その傾きを残った二枚の葉と協力しあって僅かづつながらも
真っ直ぐに矯正しつつあります。
そんな姿を目にすると、愛しさも一入で、花が萎んでしまっても、球根を
大切に保存して(水遣りもしないで休眠させれば良いらしいので、比較的
暖かい所に置いておくだけ)、もう一度花を咲かせてみようと思うのです。
それにしても、南アメリカ原産で初夏に花をつけると云うアマリリスが、
冬の最中に開花したのはなぜかしらん。
不思議に思って調べたら、輸入されたものは冷蔵処理(冬眠状態のようなも
のでしょうか)されていて、そういったものは水遣りだけで花をつけるそう
です。それに暖房が効いていますから、アマリリスも勘違いをしてしまう
のでしょうね。
アマリリスの花言葉は、誇り、内気、素晴らしく美しい、だそうです。ヴェ
ルギリウスが想い描いた羊飼いの娘、そのような名花だったのかしらん。
大安吉日の今日は、このブログ開設から777日目でもあります、
・・・だったらよかったのですが、残念ながら778日目。
今日は久し振りに神保町シアターへ行ってきました。
5日から「文豪と女優とエロスの風景」と銘打った情念の文芸作
品が一月間掛かることになったからです。
詳細は以下のところでご覧ください。
http://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/bungei_eros.html
今日観てきたのは谷崎潤一郎原作の「痴人の愛」。
「痴人の愛」は、以下の3本がこれまでに制作されているのですが、
①1949年大映
監督:木村恵吾
ナオミ:京マチ子
河合譲治:宇野重吉
②1960年大映
監督:木村恵吾
ナオミ:叶順子
河合譲治:船越英二
③1967年大映
監督:増村保造
ナオミ:安田道代
河合譲治:小沢昭一
③は数十年前に既に観ています。①と②は同じ監督・脚本ですので、
配役が違うだけだと思います。で、この作品にこだわる大映の最初
の映画をずっと観たいと思っていたのですが、やっとその機会が巡
って来たわけです。
③が原作に近くて、調教しようとした譲治がナオミに屈服するという、
谷崎の女性礼賛・耽美調のもので、大変気に入った作品でした。
京マチ子の豊満な肉体がナオミをどのように演じているのか興味津々
でしたが(実際、それについては満足)、そのことが結末を変えること
に繋がったように思えて何とも皮肉。
それに宇野重吉はちょっと堅っ苦しい譲治でしたね。もっとも小沢昭一
は地ですから比べるのは酷と云うものですが。
それにしても満員でしたね。僕は余裕を見て1時間半ほど前に行った
のですが、それでも整理番号は37番でした。99席しかありません
ので、後ろの方の席が取れるか心配でしたが、何とかなりました。
殆どがシルバー世代で、それも女性が1割強で大半が男性。ま、当然
と云えば当然なのですが。
まだ何本か観たい作品があるので花粉症の僕は大きめのマスクでしっ
かり防禦して通うことになります。後ろめたさから顔を隠しているの
ではありませんので念のため。
今年の飛散量は昨年の5倍(東京)とか。寝ているときにもマスクをし
たのは今年が初めてです。日本国民の3割ほどが花粉症と云いますが、
マスク姿のひとをそんなには見掛けませんね。薬や鼻の中をあれこれ
処置してマスクをしていないひとが結構いるということなのかしらん。
ま、インフルエンザの予防にもなるかも知れないし、隣に座ったひと
のいろんな臭いも遮断できることだし、これからもマスクでがっちり
ガードして花粉やなんだらかんだらが渦巻く街へと精出して通うのだ!
今日(2/20)は水上勉原作の「越前竹人形」(S38、大映)を観てきま
した。(この間にも2本ほど観ているのですが、それは秘密。)
原作も読んでいて、映画もTVで何十年か前に放映されたものを
観ているのですが、やはり大きな画面で見たかったのです。
若尾文子、好いですね。しっとりとした湿度を感じさせてくれる
本当に上手い女優さんです。
モノクロの映像(宮川一夫)も素晴らしいですが、大映作品で常に
思うことは音声技術が良いことです。ですから若尾文子の湿り気
を帯びた声がより活きたものになります。
若尾の相手役(竹細工職人)は山下洵一郎ですが、このひと、3組の
小林修一くんの知合いなんです。
といっても山下洵一郎(本名だそうです)が松竹にスカウトされる前
のことなのですが、小林くんは山下洵一郎が夜間高校に通っていた
ときと記憶しているようなのですが、「中央」の名が付くところで
夜間高校があるのかどうか分かりませんが、プロフィールを見る限
りにおいては中央大学の法学部在学中にスカウトされていますので、
二部の大学生のときだったと思います。
山下洵一郎は昼間、小林君のお父さんの店(半分)を間借りしていた
「アメリカベアリング」という会社の従業員として働いていたので、
そのときに小林くんを可愛がってくれたそうです。
小林くんはそれが小学校の低学年(3年生くらい)のときと記憶して
いるようです。山下洵一郎は昭和14年2月19日生(おっ、昨日が
誕生日だ!)ですから僕等より10歳ほど年上ですので、丁度大学に
進学したときであれば辻褄が合います。